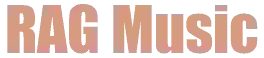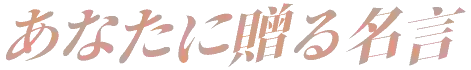儒家の始祖・孔子が遺した人生のヒットになる名言
春秋時代の中国において思想家、哲学者として活躍し、釈迦、キリスト、ソクラテスと並ぶ四聖人にも数えられる孔子。
その教えを弟子達が編纂したという論語は、長い月日を経ても人々の生活にリンクするものが多いことをご存じでしたでしょうか。
今回は、そんな孔子が遺した名言をご紹介します。
悩んでいるときにハッとさせられる言葉や、当たり前すぎて忘れてしまっていた考え方など、さまざまな角度から生きていく上でのヒントを得られますよ!
- 心を豊かにする孟子の名言!人生の指針となる言葉集
- 論語の名言で導く人生の道しるべ。心震える孔子の教え
- 知っていればきっと生きる指針になる!心に刻んでおきたい大切な言葉
- 1日1日を大切に!心に響く至極の名言で人生が輝く
- 座右の銘も見つかるかもしれない?心に残る短い言葉
- その一言にハッとさせられること間違いなし!短いけどかっこいい言葉
- 明日への原動力に!自分を奮い立たせる言葉で人生を変える
- 古代ギリシャを起源とする、世界中の哲学者による名言
- 偉人や著名人による、人生を照らしてくれる素敵な言葉
- 【春の名言】新しいスタートを彩りたいときにおすすめの華やかな言葉
- あなたの心をきっと前向きにしてくれる!ポジティブな座右の銘
- 思い出すだけで勇気が湧いてくる!偉人や著名人による心に刺さる名言
- 心に刺さる面白い一言!短い言葉なのに深い意味が込められた至言集
儒家の始祖・孔子が遺した人生のヒットになる名言(1〜10)
良薬は口に苦くして病に利あり。忠言は耳に逆らいて行いに利あり。孔子
病気に対処するための苦い薬など、なにかの効果を得るためには時に我慢することも要求されますよね。
そんな効果を得るために我慢しなければいけないことについて、わかりやすく紹介していくような名言です。
良い薬が苦いように、良い忠告は素直に聞き入れられないものが多いのだということが描かれています。
苦い薬の効果を実感したことがある人ほど、聞き入れにくい忠告も我慢して受けいれてみようかと思わせてくれるような言葉ですね。
怒りが湧いたら、その結末を想像しなさい孔子
怒りは人の感情の中でも特に大きなもので、抑えきれずにトラブルに発展することもあるかもしれませんよね。
そんな怒りを抑える方法を伝えつつ、トラブルの回避をサポートしてくれるような孔子の名言です。
心の中にわきあがった怒りをぶつけるとどのような結末につながるのかをイメージ、その結果から怒りをどうするのかを判断するべきだと表現されています。
怒りの結末を想像という段階をはさむことで、冷静な気持ちを取り戻してほしいという戦略も感じられるような言葉ですね。
義を見て為さざるは、勇なきなり。孔子
正義だと知りながらも実行しないのは勇気がないからだという、正しい行いをうながす意味を込めた名言です。
目の前に困っている人がいたときに、手を差し伸べられる人こそが、勇気を持っている人だとして、武士道の中でも大切にされてきた言葉です。
関わりを持つことはリスクもある行動ですが、そこで一歩を踏み出すことが人としての成長につながるのだと語りかけていますね。
見て見ぬふりをすることがどれほどおろかなことなのかという、日々の行動を注意されているようにも感じられる言葉ではないでしょうか。
儒家の始祖・孔子が遺した人生のヒットになる名言(11〜20)
人の本性は皆ほとんど同じである。違いが生じるのはそれぞれの習慣によってである。孔子
この言葉は、人間は生まれたときは皆同じスタートラインに立っているが、その後の習慣によって大きく異なる人間になるということを意味しています。
つまり、先天的なものではなく、後天的な努力や習慣などでどんな人間になるのかが決まるということです。
この言葉を目にすると、日々の努力や鍛錬を絶やさずに、努力を積み上げることの大切さが身にしみますよね。
何か目標をかなえるために頑張っている人に大事にしてもらいたい言葉です。
徳は孤ならず、必ず隣あり。孔子
人と違う優れた才能を持った人は、孤独である事が多いかもしれません。
しかし孔子は、「徳は孤ならず、必ず隣あり」という言葉を残しています。
これは、徳のある人は孤独にならず、必ず理解者や賛同者が現れるといった意味ですね。
もし自分の進むべき道を歩み孤独を感じている方がおられるなら、この言葉を思い出してみてはいかがでしょうか。
きっと勇気が湧いて、このまま突き進もうと思えるでしょう。
あなたを理解して助けてくれる方が現れますように。
人間は逆境において人間の真価を試される。人生の達人は逆境を楽しみ、順境もまた楽しむのです。孔子
ピンチになったときこそ、人の本性が見えたと感じたことってこれまでにないでしょうか?
スポーツの試合で追い込まれたときのキャプテンの態度に頼りがいを感じたり、旅行先でのトラブルで恋人にほれ直したり、反対に幻滅してしまったり……。
孔子によるこの言葉は、まさにそういった場面を言い表しているんです。
逆境に立たされたときにこそ、どうすればその状況を脱せるのか考える大切さを説いています。
そしてこの言葉は、人生の達人は逆境を楽しみ、順調に進んでいるときも楽しんでいると続きます。
それもまた、人生においてとても大切なことですよね。
性相近し習い相遠し孔子
持って生まれた才能が違うように思えて、劣等感を持ってしまうことは誰にでも起こり得る状況ですよね。
そんな生まれ持った才能や性質と、その後の環境によって育まれるものの関係性についてを考えさせられる、孔子の名言です。
生まれ持った才能に個人差はなく、その後の習慣や環境によって差が生まれるのだと表現されています。
後天的なものが影響しているのだと思えると、現状をより良く変えていこうとする力もわいてくるのではないでしょうか。