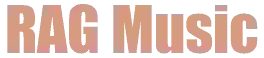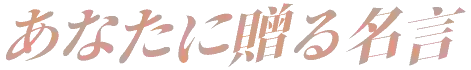儒家の始祖・孔子が遺した人生のヒットになる名言
春秋時代の中国において思想家、哲学者として活躍し、釈迦、キリスト、ソクラテスと並ぶ四聖人にも数えられる孔子。
その教えを弟子達が編纂したという論語は、長い月日を経ても人々の生活にリンクするものが多いことをご存じでしたでしょうか。
今回は、そんな孔子が遺した名言をご紹介します。
悩んでいるときにハッとさせられる言葉や、当たり前すぎて忘れてしまっていた考え方など、さまざまな角度から生きていく上でのヒントを得られますよ!
儒家の始祖・孔子が遺した人生のヒットになる名言(1〜10)
過ぎたるは、なお及ばざるが如し。孔子
何事にも多くて余裕がある方が良いという考え方は誰もが持ってしまう考えかと思います。
そんな誰にでも起こり得る、つい過剰にやってしまう姿勢に警告を投げかけるような、何事もほどよさが大切なのだと主張する孔子の名言です。
過剰は不十分とおなじくらいに良くないものであり、そのほどよいラインを見極めることが重要だと伝えています。
食べ物も学問も、適切な量の方が健やかな日々につながるのだと語りかけているようなイメージですね。
己の欲せざる所、人に施すこと勿かれ。孔子
孔子の言葉として、論語の中で二度も語られる言葉なんです。
この言葉は「自分が他人からされたくないことは、自分も他人にしてはいけない」ということを意味しています。
これこそが人に対する思いやりであり、政治の場面だけでなく、家庭内でも人間関係を良好に築いていくために欠かせないことなんだと説いています。
この言葉は白銀律と呼ばれるもので、似たような言葉はいろいろな宗教の教えの中にあるので、興味がある方は調べてみてください。
何事も楽しんでやりなさい。楽しんでやることで、思わぬ力が発揮されるものなのだ。孔子
成果を出そうとする気持ちが高まるほどに、それに向き合う時間を困難で苦しいものだと感じてしまいますよね。
そんな人にこそ思い出してほしい、物事に楽しんで取り組み事がどれほど大切なのかを表現した孔子の名言です。
肩の力を抜くことを推奨する内容で、余計な力を抜くことがパフォーマンスの向上や成果にもつながるのだと伝えています。
行き詰ったときにこそこの言葉を思い出してリラックスすれば、視野が広がって解決策が見えてくるかもしれませんよ。
仁に当たりては、師にも譲らず。孔子
親や先生など、尊敬するべき存在がいることは人生を豊かにすることにもつながっていきますよね。
そんな重要な存在である先生に対してでも、ゆずれないものがあるのだという、信念を貫く姿勢を感じさせる名言です。
仁徳を重ねること、徳を高めることは先生にも遠慮しないという表現で、自分なりの徳の積み方で進んでいくべきなのだと伝えています。
仁徳の重ね方については誰かに教わるのではなく、自分で考えて進んでいくべきだという思いも感じられる言葉ではないでしょうか。
朝に道を聞かば、夕べに死すとも可なり。孔子
人間としてどのように生きるべきなのかを悟ることが何よりも重要で、それさえ悟れば心残りはないのだという考え方を示した言葉です。
言葉の後ろから考えてみると、心残りがないように道を追及していこうという孔子の姿勢も伝わってきますよね。
生きるべき道が簡単に見つかるものではないからこそ、心残りが尽きない、道がまだまだ途中なのだという表現にも思えてきます。
生涯をかけて学問に向き合っていこうとする決意、それほどの決意がないと道は見つからないという部分も主張するような名言ですね。
優れた人物は、人と協調するが主体性を失わず、小人物は、表面では同調するが心から親しくなることはない。孔子
道徳心や教育の大切さも伝えてきた孔子さんですが有名な名言で、優れた人物は、人と協調するが主体性を失わず、小人物は、表面では同調するが心から親しくなることはないという言葉があります。
周りの人と協力しながらも、自分の軸や価値観をしっかり持ち、どんな相手でも表面上はうまく振る舞うが、自分を大切にするといった言葉です。
仕事でも人間関係や協調性が求められてきますが、この言葉のように上手く付き合いながらも自分の軸を大切にしていこうという現代にも通じる言葉ですね。
知らざるを知らずとなす、これ知るなり。孔子
日々のやり取りの中で自分が知らないことがあったとき、それを知らないと認めることが時には恥ずかしかったりもしますよね。
そんな知らない部分を知らなかったと認めることの重要性や、今後のつながりを感じさせる孔子の名言です。
知らなかったと認めることで、そのことを教えてもらえるかもしれない、新たな知識につながる可能性があるのだということも伝わりますね。
自分が何を知っていて、何を知らないのか、自己分析を進めることが幅広い知識のきっかけになるのだと感じさせる言葉ですね。