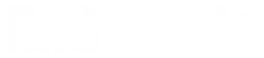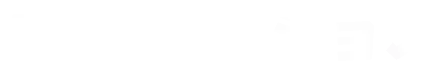【高齢者向け】夏の俳句。夏を感じるアイディア
夏は、高齢者の方にとって懐かしい思い出がよみがえる季節ですよね。
そんな夏のひとコマを、俳句で気軽に表現してみませんか?
俳句はたった17音で作れる、日本ならではの詩の形式です。
難しく考えずに、目の前に広がる季節の風景や心に浮かんだ気持ちを素直に詠むのがコツです。
五・七・五のリズムに乗せることで、情景がより鮮やかに伝わります。
本記事では、夏をテーマにした簡単で親しみやすい俳句をご紹介します。
言葉に季節を込める楽しさを、ぜひ味わってみてください。
【高齢者向け】夏の俳句。夏を感じるアイディア(41〜50)
五月雨を 集めてはやし 最上川
夏のはじまりともいえる5月あたりは、雨も徐々に強くなってくるようなイメージで、その雨によって環境も変化していきますよね。
そんな5月の雨と、それが流れ着いた先の最上川の変化についてを描いた、松尾芭蕉による俳句です。
雨が降れば川に流れこむ水の量も増えていくもので、そうなることで流れも速くなっていくのだと表現しています。
流れが強くなった原因も語りつつ、雨を集めたような強いものだと、流れの強さについても描いている内容です。
入る月の 跡は机の 四隅哉
自分の身内が亡くなる、普通なら悲しくて何も手に付かないと思います。
ですが、芭蕉さんは故人をしのびいくつもの句を残しているんですよね。
この俳句は芭蕉さん50歳、亡くなった父への追悼として詠んだ有名な一句。
父東順も俳人として有名で「しらぬ人と物いひて見る紅葉哉」は代表句の1つです。
父は亡くなってしまったが父が愛用していた机は遺されている。
月が優しく机を照らすがそこにはもう父はいない、寂しさを寂しさとして詠まないところにも俳を感じます。
夏草や 兵どもが 夢の中
もちろん皆さんご存じ、学校の教科書にも登場する松尾芭蕉さんの有名な俳句です。
特に俳句に興味がない方もこの句は知っていることでしょう。
学生の頃は「兵」がどうして「つはもの」と読むのか?
と、何も思わないままただただ暗唱した記憶があります。
この俳句が詠まれた場所は東北は平泉。
芭蕉さんはそこで奥州藤原氏の栄華の果てをしのんだのでしょうか。
奥州藤原氏が滅んでから何度目の夏がきて、そして夏草が風になびいていることでしょう。
現地にいた芭蕉さんならずとも感慨深くなる一句ですね。
山門の 大雨だれや 夏の月
夏は日差しが強い晴れというイメージが強いですが、強い雨が降る季節でもありますよね。
そんな夏の強い雨の情景をまっすぐに描いた、小林一茶による俳句です。
山門に強い雨が降っている様子、そのあとに見える夏の月という構成で、雨の激しさと、月が輝く静かな風景を対比させています。
強い雨が降ったとしても、時間がたてば月が見えるという点で、風景の変化に思いをはせているようにも見えていますね。
変化があるからこそ、自然は美しいのだという部分も伝えているような内容ですね。
川風や 薄柿着たる 夕涼み
最近の夏は40度を超える気温も珍しくなくなってきました。
いろいろと暑い町はあると思いますが京都も暑そうですよね。
この句は元禄3年、夏の頃の作とされている一句。
今ほど冷房装置が発展していなかった京都の夏を涼ませるものといったら川床でしょうか。
この句にはよく四条の河原の夕涼みの絵がコラージュされています。
当時流行していた?
柿で染めた衣類をまとっての夕涼み、流行の最先端を走っていた景色とも。
川の風が一層涼しく感じられる一句です。