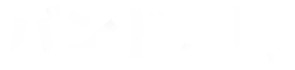- ミュージシャンのための英会話講座。ライブ編
- 作曲初心者も必見!定番のコード進行まとめ
- 【練習!】春休みのベース初心者のための練習曲
- 【音痴でも大丈夫!】カラオケで歌いやすい曲・練習曲を紹介
- 【カラオケ】Official髭男dismの歌いやすい曲を一挙紹介!
- 【初心者向け】女性ボーカルバンドにオススメの曲。曲選びの参考に!【2025】
- My Hair is Badの歌いやすい曲。邦ロック好き必見!
- ピアノ伴奏パターン|伴奏付けや弾き語りに役立つアレンジをピックアップ
- カラオケで歌われているクリスマスソング!歌いやすい曲を紹介
- 【ボーカル解説あり】misiaの歌いやすい楽曲
- 歌の練習にぴったり!miletのカラオケで歌いやすい曲
- カラオケで歌うとかっこいいヒップホップ|歌うコツも解説!
- 【ロック】初心者でも挑戦しやすいバンド系ボカロ曲【簡単】
英語ではサビってなんていうの?

http://o-dan.net/ja/
日本でリハーサルをしているとき、
「じゃあ2サビからもう一回」
「Bメロのコードおかしくない?
」
などという会話をすることもあるかと思いますが、英語で同じ内容を話そうと思ったらどうしますか?
Bメロを、B Melodyと言おうとしてはだめですよ?
実は僕の経験上、ジャズで使われる言葉とポップスやロックなどの商業音楽で使われる言葉は全く違うので、楽曲のスタイルに分けて紹介していきます。
楽曲構成の名称(商業音楽系)
AメローVerse
これが一般的な言い方でしょうね。
Verseとは、一般的に歌や詩の節という意味合いを持ちます。
それが転じてこういう意味を持つようになったのじゃないでしょうか。
BメローVerse もしくは Pre Chorus
Bメロもサビではないので、基本的にはVerse 2などといってAメロと区別します。
しかし場合によってはサビ前のメロディとなることがあるので、その場合は「サビ前」という意味のPre Chorusというフレーズを使います。
CメローVerse もしくは Bridge
基本的にはこれまでと同じです。
ただJ-POPによくある構成で考えると、Cメロは楽曲後半の大サビ前などで出てくる全く新しいメロディの場合があるので、その際にはBridgeという言葉を使ったほうがわかりやすいでしょう。
サビーChorus
一般的なコーラスという言葉の意味で考えてしまうと意味がわかりませんが、サビのこともChorusといいます。
理由はわかりません。
ぐぐってください。
商業音楽の構成を表す英語を理解する上で重要なのは、海外の楽曲のスタイルがJ-POPとはあまりにもかけ離れているということ。
上ではA,B,Cメロを分けて表記しましたが、多くの洋楽はAメロとサビ(たまに大サビ前のCメロ)しかないです。
J-POPはとにかくメロディが目まぐるしく変わりますが、洋楽はもっとシンプルです。
そのため、Verse – Chorus – 2nd Verse – Chorus – Bridge – Chorus – Chorus といった表記のされ方をよく見かけます。
Verseと言われたらサビ以外。
Chorusと言われたらサビという風に覚えておけば間違いないでしょう。
楽曲構成の名称(ジャズ編)
テーマーHead
冒頭のメロディのことですね。
ちなみに「テーマを演奏する」は“Play the head”という言い回しの他に、“Take the head”という言い方もできます。
コーラスーChorus
商業音楽ではサビの意味でしたが、ジャズでは日本語と使い方が一緒です。
ソロを演奏する尺を相談するときに、“How many choruses should I play?(何コーラス分ソロやればいい?
)”なんて使います。
ちなみにフルコーラスという言い回しは聞き慣れません。
Aメロ、BメロなどーA section, B section
これもわかりやすいですね。
なぜかジャズではVerseという言葉を聴きません。
歌詞がない場合が多いからでしょうか……
気をつけないといけないのは、ときに楽譜上のリハーサル記号を指して“A Section” “B section”などと言う場合もあるということです。
BメローBridge
え、さっきBメロはB Section っていうって説明してたじゃん!
って思ってるでしょ?
たしかにそうなんです。
でも、AABA構成の曲の場合、B section というよりも Bridgeといったほうが通じます。
最後に
ここまで説明してきてあれですけど、ぶっちゃけこんなのどうでもいいです。
覚えていたら便利だけど、全く違う言い回しを使う人だっています。
結局はリハーサル中にうまくコミュニケーションが取れれば、どんな言葉を使おうとその人たちの自由です。
英語圏の人と演奏する機会があるときは、しつこいぐらい丁寧に説明することを心がけましょう。
コード名を使ったり、小節数で説明したり、臨機応変に対応して、ストレスのないリハーサルにしましょうね。