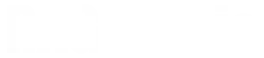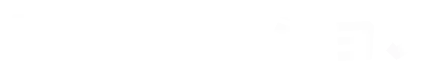日本文化・地理・健康がテーマ!高齢者の方が笑えるクイズ特集
「へぇー!」「そうだったの?」思わず声が出てしまう、笑える地理クイズや健康にまつわる豆知識を集めました。
サクランボの種飛ばし大会や、山がつく県の数、身近なコンビニと歯科の意外な関係など、日本文化にちなんだ楽しい問題ばかりです。
高齢者の方にとってなじみ深い話題から、ちょっと驚きの事実まで、クイズを通して新しい発見と笑顔をお届けします。
知ったらきっと誰かに話したくなる、そんな心温まるひとときをお過ごしください!
- 【高齢者向け】夏祭りの雑学クイズ&豆知識問題。知識が増える楽しいクイズNEW!
- 季節と行事のクイズ特集。高齢者と一緒に笑顔あふれる時間をNEW!
- 高齢者が盛り上がる!雑学豆知識クイズで頭も心もすっきりNEW!
- 【高齢者向け】7月雑学クイズ&豆知識問題。簡単で盛り上がるNEW!
- 昭和レトロが懐かしい!高齢者の方に盛り上がるクイズ特集NEW!
- 高齢者の方が楽しく学べる!健康クイズで盛り上がる時間をNEW!
- 【高齢者向け】人に話したくなる。掃除に関する雑学クイズ&豆知識問題NEW!
- 【高齢者向け】夏に挑戦しよう!海の雑学クイズ&豆知識問題まとめNEW!
- 【高齢者向け】楽しく脳トレ!都道府県クイズ
- 【高齢者向け】身体の仕組みと健康雑学クイズ・意外と知らない豆知識問題
日本の文化・地理・健康知識
目が疲れたときに、何色を見ると目の疲れが癒えるのでしょうか?
答えは「緑色」です。
緑色には心理的な作用として気持ちをリラックスさせ、心や体の緊張をゆるめる効果があるとされています。
部屋に観葉植物を置いたりするのは、私たち現代人が知らず識らずのうちに癒やしやリラックスといったことを求めているからなのでしょうか。
また、「目が疲れたときは遠くの山を見るとよい」と聞いたことはありませんか。
近くより遠くを見るときのほうが、目の筋肉をゆるめることができるそうです。
これも先人の知恵ですね。
薬の飲み方の「食間」とはいつのことでしょうか?
高齢者の方の中には、病院からお薬をもらっている方も多いのではないでしょうか。
そのときに、薬の飲み方として「食間」を指定されている方もいるかもしれませんね。
では、この「食間」って、いつ薬を飲むことなのでしょうか?
食事中に飲むものだと思っている方も多いですが、それは間違いですよ!
答えはずばり、食事と食事の間。
つまり、朝ごはんと昼ごはんの間、昼ごはんと晩ごはんの間などです。
厳密には、食べた後約2〜3時間後が目安とされています。
高齢者の方は、もし「食間」と指示された薬をもらったときは、気をつけてくださいね。
人間の骨は成長とともに、数が変わります。一番、骨の数が多いのはいつでしょうか?
人間の体は成長していくとともに体のサイズや見た目が変化していきますよね。
そんな見た目から感じられる成長だけでなく、内側に存在する骨の数も成長とともに変化しています。
ではそんな骨の数がいちばん多いのはいつだといわれているでしょうか。
骨の数が増えていくのか減っていくのかということに注目すれば、答えにもたどり着けるかもしれませんよ。
答えは赤ちゃんのころ、赤ちゃんのときには約305個の骨があり、離れていたものがくっついたり、いくつかの骨がひとつになったりという流れを繰り返して、成人の時には約206個の骨になるといわれています。
健康に良いとされる感情はどのような感情でしょうか?
答えは「笑う」です。
「笑いは百薬の長」「笑いに勝る良薬なし」ということわざがあります。
笑うと免疫をコントロールしている「間脳」に興奮が伝わり、情報伝達物質が活発に生産され、血液やリンパ液を通じて体中に流れ出して体に悪影響を及ぼす物質を退治している「ナチュラルキラー細胞」を活性化し、免疫力が高まるそうです。
笑うことで脳の働きが活発になり、大きく笑った時の呼吸は深呼吸や腹式呼吸と同じような状態と、高齢者にもいいこと尽くめです。
原始時代は虫歯になる人はほとんどいませんでした。なぜでしょうか?
人間の祖先である原始人には、虫歯がなかったなんてびっくりですよね。
まだ、歯ブラシも歯磨き粉もない時代に、どうしてそんなことが起こったのでしょうか。
ヒントは、その時代に原始人が食べていた食べ物にありました。
答えは、硬い食べ物しかなかったからです。
硬い食べ物は自然に口の中でかむ回数が増えるので、唾液がしっかり分泌され、細菌などを落としてくれました。
しかし、現代はやわらかい食べ物が増えたことで食べ物が歯に挟まりやすくなってしまったり、かむ回数が大幅に減ったことで唾液が大幅に減少したことで、虫歯にかかりやすくなってしまったんです。