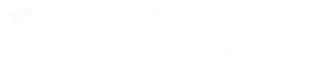【小学生向け】理科にまつわるゲーム・クイズまとめ
身近な生き物について調べたり、観察や実験を通じて物の仕組みや物理法則を学んでいく教科、理科。
虫眼鏡で紙に火を点けるなど、時には魔法のような現象を自分で起こせてしまうので、好きなお子さんは多いんじゃないでしょうか。
さて、今まで以上に興味を持って取り組んでもらうために、ここは一つ遊び感覚で勉強しちゃいましょう!
今回この記事では理科にまつわるゲーム、クイズをまとめてみました!
ぜひみんなで盛り上がってくださいね!
- 【小学生向け】生き物の知識が深まる3択クイズ
- 小学生向けの4択クイズまとめ。身の回りのものに関する雑学クイズ
- 【小学生向け】暗号クイズ。面白い謎解き問題
- 小学生向けの盛り上がるクイズ。みんなで一緒に楽しめる問題まとめ
- 【生き物クイズ】クイズを通して生き物のことを学ぼう!
- 小学校・高学年におすすめ!盛り上がる室内レクリエーション&ゲーム
- 【小学生向け】どっちが大きいクイズまとめ。大きさ比べをしてみよう
- 小学生向けクイズ。簡単!おもしろい!問題集
- 【小学生向け】知識や雑学が身に付く動物クイズ
- 【面白い】雑学クイズの問題まとめ
- 知って楽しい!宇宙の雑学まとめ【レク】
- 【小学生】お宝発見!手作りで楽しむ謎解き宝探しのアイデア集
- 【小学生向け】オススメの謎解き問題まとめ
【小学生向け】理科にまつわるゲーム・クイズまとめ(11〜20)
雲の種類クイズ
【理科 サイエンス クイズ】 雲の種類 10種類 (この雲なんだ?) ◉くもの種類 ◉空 ◉天気 ◉天気予報 ◉勉強動画 ◉cloud

変わった雲を見かけた経験はありませんか?
実は雲にはさまざまな種類があり、それぞれに名前が付いているんですよ。
雲の種類クイズで、それらの雲について学んでいきましょう。
きっと見かけたことがある雲が見るかるはずですよ。
次からは見かけた時に、家族やお友達に何という雲か教えてあげられますね。
ちなみに、雲によっては天候の変化を示しているものもあるんです。
覚えておくと私生活でも役立つかもしれません。
例えば、巻雲が現れると、数日以内に雨が降る可能性が高いです。
これなんのはながさく?
タネや球根を見て答えよう!
これなんのはながさく?
のアイデアをご紹介しますね。
皆さんの通う学校や公園には、さまざまな花が咲いていると思います。
今回は、タネや球根の写真から何の花が咲くのかを予想して答えてみましょう!
もしかすると、知っている花が登場するかもしれませんね。
覚えた知識は、友達や保護者の方にも教えてみてください!
クイズを通して、もっと自然の植物や花が好きになりそうなクイズのアイデアですよね!
おわりに
楽しく、真剣に取り組めそうなものは見つかったでしょうか。
やはり実験形式のものが、物自体の仕組みを体感しながら理解できるのでいいかもしれませんね。
ぜひともみなさんで、有意義な理科タイムをお過ごしください!