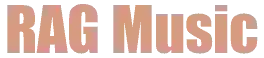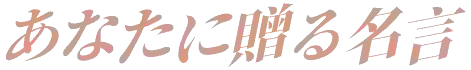風林火山で有名!甲斐の虎として恐れられた戦国武将・武田信玄の名言
戦国最強と言われる武田軍を率いたことでも知られ、「甲斐の虎」の異名で恐れられた戦国武将、武田信玄公。
まさに猛将といったイメージがありますが、実は内政にも力を注いでいたことから、部下や領民にも慕われていた一面も持ち合わせています。
また、信玄という名前は出家後の法号で、本名は「武田晴信」であることをご存知でしたでしょうか。
今回は、そんな武田信玄公が遺した名言をご紹介します。
厳しくも優しさを感じさせる金言ばかりですので、要チェックですよ!
- 伝説の俳優・高倉健が遺した珠玉の名言|魂を揺さぶる生き様
- 『キングダム』王騎将軍の名言|千人将も震えた不敗の名将の言葉
- 聞けば感動すること間違いなし!偉人や著名人による心に残る言葉
- 座右の銘にしたい有名人の言葉。言葉の力を感じる名言
- 思い出すだけで勇気が湧いてくる!偉人や著名人による心に刺さる名言
- 現代でもさまざまな創作に登場することで人気の剣豪、宮本武蔵の名言
- 昔の人の名言集。有名な武将や世界的偉人からのメッセージ
- 鱗滝左近次の名言。厳しさの中に隠された育手の愛情深い言葉
- 『鬼滅の刃』において絶大な人気を誇る、煉獄杏寿郎の名言
- 思わず胸が熱くなる!不朽の名作『北斗の拳』の名言集
- 心に響く!日本の偉人が残した名言
- 胸に刺さる神谷宗幣の名言まとめ。日本を思う熱い言葉たちNEW!
- いざという時に心の支えになる!防災にまつわる格言&名言特集
風林火山で有名!甲斐の虎として恐れられた戦国武将・武田信玄の名言(1〜10)
老人には経験という宝物があるのだ。武田信玄

「老人には経験という宝物がある」という名言からは、武田信玄公の人間性や考え方が反映されているのを感じられますよね。
確かに若者には体力があり、知識も磨けば身についていきますが、経験だけは積むことに限界があります。
生きてきた足跡そのものを重んじる考え方があるからこそ、戦国時代において強固な国を築けたのではないでしょうか。
若い世代ばかりをもてはやす現代社会とは真逆の、人を大切に考えていることが感じられる名言です。
信頼してこそ人は尽くしてくれるものだ。武田信玄
命令したり押さえつけるのではなく、まず自分が心を開くことが大切だと教えてくれる名言「信頼してこそ人は尽くしてくれるものだ」。
人は誰かに何かをしてもらいたい時、どうしても自分が求めることが先行してしまいがちですよね。
親子関係や仕事の現場など、特に上の立場の人が思ってしまいがちなのではないでしょうか。
まずは相手を信頼することこそが良好な人間関係を作り出す事を教えてくれる、現代社会においてもリンクする名言です。
我、人を使うにあらず。その業を使うにあり。武田信玄
人間ではなく、その人が持つスキルを借りるという考え方が見える名言「我、人を使うにあらず その業を使うにあり」。
歴史に名を残した戦国武将でありながら、その謙虚な姿勢が垣間見える言葉ですよね。
人が人を使うというおこがましい考え方ではなく、あくまで対等に部下を見るという考え方こそ、現代のリーダーにも必要なのではないでしょうか。
武田信玄公の人間力を一言であらわしたような、現代社会を生きる人にこそ知ってほしい名言です。
風林火山で有名!甲斐の虎として恐れられた戦国武将・武田信玄の名言(11〜20)
勝敗は六分か七分勝てば良い。八分の勝ちはすでに危険であり、九分、十分の勝ちは大敗を招く下地となる。武田信玄
勝負に勝つことだけではなく、その裏にある危険性を表した言葉「勝敗は六分か七分勝てば良い 八分の勝ちはすでに危険であり、九分、十分の勝ちは大敗を招く下地となる」。
確かに歴史上、桶狭間の戦いや一ノ谷の戦いなど、勝敗が明らかと言われていながら大逆転を果たした例は多いですよね。
成功を確信した瞬間こそ過信してはいけないという考え方が、この言葉を生み出したのではないでしょうか。
現代においても忘れてはいけない教訓を教えてくれる名言です。
自分が死した後は上杉謙信を頼れ。また三年間を喪を秘せ。武田信玄
武田信玄公が遺言として息子に残したと言われている言葉「自分が死した後は上杉謙信を頼れ また三年間を喪を秘せ。」甲斐の虎と称されていた武田信玄公に対して、越後の龍と称されていた上杉謙信公は、5回に渡る川中島の戦いでも勝敗がつかなかったことから戦国時代の代表的なライバル関係として知られています。
その上杉謙信公を頼れという遺言は、ライバルとしてそれだけ認めていたということなのではないでしょうか。
また、自分の死を三年間隠せという言葉には、それを知った敵の武将から攻め込まれないためだったと考えられます。
どこまでも国のために戦った、武田信玄公らしい名言です。
渋柿は渋柿として使え。継木をして甘くすることなど小細工である。武田信玄

個性をねじ曲げる愚かさを説いた名言「渋柿は渋柿として使え 継木をして甘くすることなど小細工である」。
渋柿には渋柿の、甘柿には甘柿の良さがあるのに、それを全部甘柿に変えてしまうのは間違っているという意味の言葉で、それぞれの長所を活かす大切さを教えてくれますよね。
個性の時代と言われている現代社会だからこそ、マイノリティーをマジョリティーに押し込んでしまうことのないように、多くの方に知っておいてほしい名言です。
為せば成る、為さねば成らぬ成る業を、成らぬと捨つる人の儚き武田信玄

強い意志で行動しなければ何事も実現できないのに、最初から無理と諦めてしまう人の弱さを表した名言「為せば成る、為さねば成らぬ成る業を、成らぬと捨つる人の儚き」。
頑張ってほしいという気持ちを持ちながらも、それでも甘えが出てしまう弱い心があることを理解している、器の広い言葉ですよね。
誰もが強い心を持ち続けられるわけではないという前提がある上で、その姿を見守ろうとする、理想的なリーダー像をイメージさせる名言なのではないでしょうか。