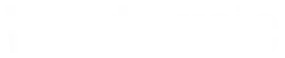吹奏楽で活躍する楽器一覧。種類別に大紹介
全国の多くの学校に設けられている吹奏楽部はコンクールや演奏会はもちろん、野球応援や文化祭などでも活躍していますね。
新入生の方の中には吹奏楽部への入部を検討している方もいらっしゃると思いますし、すでに入部を決めてどの楽器を演奏したいか考え始めている方もいらっしゃるでしょう。
ところで、吹奏楽には一体どのような楽器が活躍しているのでしょうか?
この記事では木管楽器、金管楽器、低音楽器、打楽器の4つのグループに分けて、吹奏楽で使用される楽器を紹介していきますね!
ぜひ演奏したい楽器選びの参考にしてみてください。
- オーケストラで演奏される楽器一覧。種類別に紹介
- 吹奏楽を始めようとしている新一年生のみなさまへ。楽器の種類と特徴
- 【楽器初心者のための】吹奏楽部でおすすめの楽器。フルート・トロンボーン・トランペット編
- 吹奏楽部を辞めたいと思っているあなたへ。こんな理由では辞めないほうがいい
- 世界一難しい楽器、ホルンの魅力とは?
- 【マーチ】行進曲の定番&演奏会で人気の華やかな作品を厳選!
- トランペットがかっこいい曲。吹奏楽やジャズの名曲を紹介
- 自由曲や演奏会の選曲に!吹奏楽の名曲・定番の人気曲を紹介
- 哀愁漂う木管楽器。オーボエの魅力に迫る
- 定番の吹奏楽メドレー
- 【歴代】吹奏楽コンクールの人気課題曲まとめ
- 【吹奏楽】女子が好きな吹奏楽曲。女性におすすめの吹奏楽の名曲
- 金管奏者のみなさんへ、炭酸水はいいぞ!
金管楽器(1〜10)
ホルン

構えた時にベルが後ろを向いているという独特の形状により音が壁に跳ね返り、金管楽器でありながら角のない柔らかな音色が特徴的な楽器。
その音色から「木管五重奏」といえばホルンが入るなど、木管楽器と金管楽器の橋渡し的な役割も持っています。
また、金管楽器の中でも広い音域を持つことでも知られ、その幅広い役割から「世界一難しい金管楽器」とも呼ばれています。
弾きこなすにはかなりの練習が必要となりますが、その多彩な表現力や木管と金管の中間的な役割から吹奏楽において重要なやりがいのあるパートです。
ユーフォニアム

アコースティック楽器の中でも歴史が新しい部類に入る金管楽器。
フルートからチューバまで、あらゆる管楽器と同じ運指を要求される楽器であることから、アンサンブルにいるだけで全体のバランスが良くなることでも知られています。
その優しく丸みを持った音色は、吹奏楽においても楽曲に寄り添った旋律を生み出しますよ。
歴史のある伝統的な楽器とは違った新しい世代の楽器ですので、吹奏楽部に入ったときに楽器で悩んだら手に取ってみてほしい楽器です。
低音楽器(1〜10)
チューバ
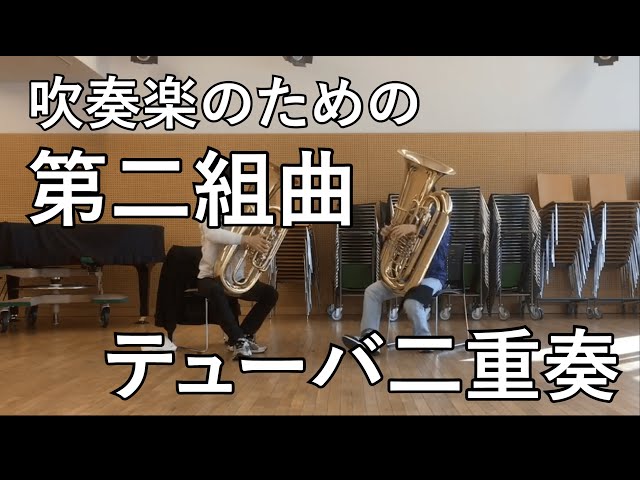
金管楽器の中でもとくにサイズが大きく、もっとも低い音域を担当する楽器。
吹奏楽において土台であり根幹を作り出す圧倒的な音量は、まさに低音パートのリーダーと言える存在感を放っています。
どんな音楽においても重要なハーモニーやリズムを作り出す役割もあり、最低音からアンサンブルを支える「縁の下の力持ち」として活躍できますよ。
トランペットやサックスなどの花形楽器とはまた違った楽曲全体を左右する重要なパートのため、客観的な視点に自信がある方にはぴったりな楽器と言えるのではないでしょうか。
バリトンサックス

木管楽器の花形として幅広いジャンルで活躍するサックスの一種。
テナーサックスとバスサックスの間となる中低音域を得意とする楽器で、他のサックスにはないローAキーを備えていることも特徴です。
クラシックにおいてはもともとはアンサンブル楽器としての使用が多かった楽器ですが、近年ではソロ楽器として脚光を浴び始めており、またジャズにおいては著名な演奏家が多く存在するなど、その独特の音色に注目が集まっています。
ソロ楽器としてもアンサンブル楽器としても幅広く機能する楽器ですので、低音の楽器が好きだけどソロでも目立ちたい、という方にオススメの楽器です。
コントラバス
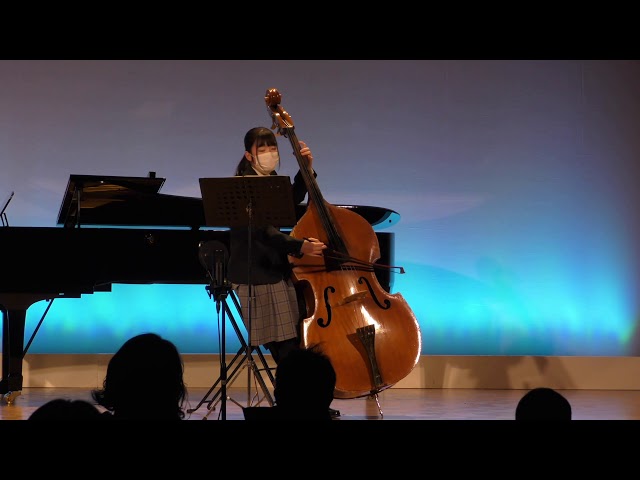
ダブルベース、アップライトベース、ウッドベースなど、いろいろな名前で呼ばれるコントラバスは、管楽器と打楽器がほとんどを占める吹奏楽の中では珍しい弦楽器です。
なぜ管楽器が中心の吹奏楽にコントラバスが唯一の弦楽器として加わっているのかというと、その理由は音楽的に低音が必要だからにほかなりません。
コントラバスはチューバよりも低い音が出せ、他の楽器と共鳴できるので、花形とは言いがたいですがとても重要な楽器なのです。
バスクラリネット

その名のとおりクラリネットの派生楽器で、通常のクラリネットの1オクターブ下の音域を持つ木管楽器。
アンサンブルにおいて全体の音を支える「縁の下の力持ち」的な役割を持ち、近年では吹奏楽に加えクラシック、ジャズ、フュージョン、現代音楽など幅広いジャンルで聴くことも増えてきましたよね。
低音な上に他の管楽器に比べて音量に限界があることからアンサンブルの中で聴き分けるのは難しいですが、似ている音色の楽器がないため全体の深みを作るのに必要不可欠な楽器です。
音楽の要を作り出す、代わりのいない音色が魅力の木管楽器です。
ファゴット

オーケストラ、コンサートバンド、室内楽作品など、幅広い場面で重要なパートとして知られている低音楽器。
発音が遅れがちな低音域でも音の立ち上がりが速く、その俊敏さや音域の広さにより吹奏楽においても重宝されています。
機構が単純であることから音程が取りにくかったり音量が小さかったりなどの難点がありますが、それを補って余りある独特の音色や多彩な個性はアンサンブルになくてはならない深みを生み出してくれますよ。
派手に目立ちたくはないけど個性を主張したいと考える方にオススメな、吹奏楽になくてはならないパートです。