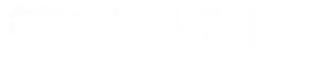哀愁漂う木管楽器。オーボエの魅力に迫る
みなさん「オーボエ」という楽器を思い浮かべてみてください。
「あれ……どんな形をしていたかな?」そう思う方が多いのではないでしょうか?
オーボエは木管楽器の中でも高級な楽器なので、特に日本では目にすることは少ないと思います。
意外と知られていない楽器、オーボエ。
今回はその魅力に迫ります!
オーボエの音色と構造
まずはこの動画を見てください。
オーボエの形は分かりましたか?
なんとなくクラリネットに似ていますよね。
分解すると、上管・下管・ベルの3つに分かれ、上管にリードをさして演奏します。
リードとは?

リードとは、乾燥させた葦(あし)を削ったものをいいます。
クラリネットやサックスは1枚のシングルリードですが、オーボエは2枚重ね合わせたダブルリードを使います。
このダブルリードが、オーボエの音色の要(かなめ)なのです。
オーボエの由来と歴史
オーボエの名前の由来はフランス語の「haut bois(高い木)」から来ており、「高音の木管楽器」を意味します。
ドイツでは「oboe」、フランスでは「haut bois」と表記します。
オーボエの祖先「ショーム」
オーボエはヨーロッパで13世紀後期から17世紀にかけて作られた、「ショーム」という木管楽器が進化したものです。
こちらがショームの演奏動画です。
当時はキーがなく、リコーダーのように穴をおさえて演奏していました。
19世紀になりシステムの機械化が進み、現代のオーボエ(コンセルバトワール式)が定着しました。
世界一難しい木管楽器

オーボエは世界一難しい木管楽器としてギネスブックに登録されています。
ちなみに世界一難しい金管楽器は、ホルンです。
なぜ世界一難しいと言われているのでしょうか?
音程
オーボエは音程がかなり不安定な楽器です。
その原因は、楽器の構造にあるのです。
円錐形なので上にいくにつれ息の通り道が狭くなり、吹き込む圧力で胸が詰まって苦しくなります。
よく「肺活量が必要な楽器」と勘違いされる方が多いですが、実は真逆で、オーボエは「とにかく息が余る楽器」なのです。
そのため、音程も不安定になりやすいのです。
リード作り
オーボエ奏者は、とにかくリード作りに悩まされます。
完成したリードは市販でも買うことができますが、1本あたり2,000~3,000円と結構お高いのです。
安定した奇麗な音を出すためには良いリードが必要ですが、そのためにはオーボエを続けている限り、何百本もリードを作ることになります。
そういった繊細さが「世界一難しい木管楽器」と言われる理由だと思います。
オーボエの神様 ハインツ・ホリガー
「オーボエの神様」と呼ばれている奏者、ハインツ・ホリガーを紹介します。
楽曲はオーボエの曲の中で一番有名なモーツァルトのオーボエ協奏曲(Cdur)です。
https://www.youtube.com/watch?v=A2UC3Fo765w
オーボエのソリストとしては、1959年にジュネーヴ国際音楽コンクールや1961年にミュンヘン国際音楽コンクールで首位を獲得しました。
国際的に名声ある演奏家であり、献呈(けんてい)されたオーボエ作品も数多いです。
最後に
最初のうちは音程が不安定で難しいですが、慣れてくると美しく哀愁漂う音色に変わります。
オーケストラではソロパートが多く、とてもやりがいのある楽器だと思います。
もし少しでも興味がありましたら、オーボエを始めてみませんか?