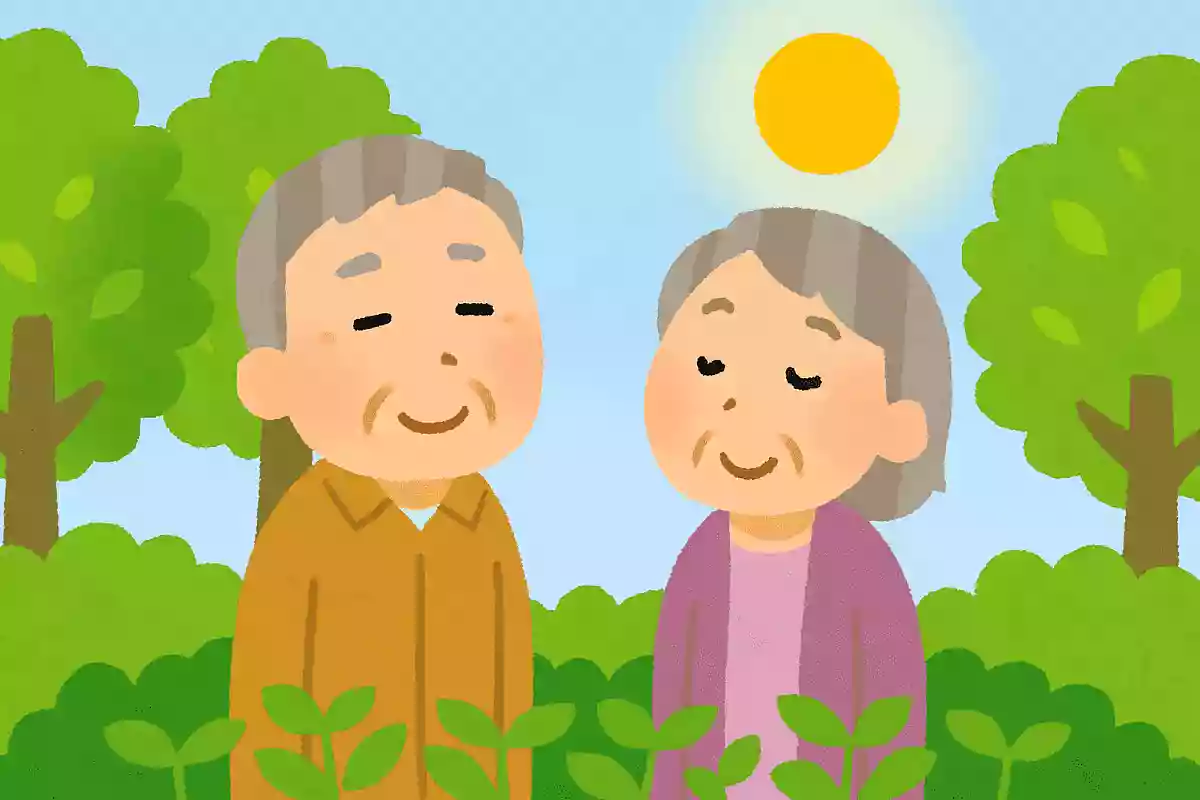6月に入ると、しっとりとした梅雨の季節がやってきます。
雨のしずくが葉を濡らし、初夏の香りが漂うこの時期は、自然の美しさをじっくり感じるのにぴったりです。
高齢者の方にとって、俳句はそんな季節の変化を楽しみながら心を豊かにしてくれる素晴らしい方法ですよね。
けれど「梅雨の季節をどう表現すればいいのか?」と迷うこともあるかもしれません。
この記事では、6月にぴったりな俳句を厳選してご紹介します。
初夏の空気を感じつつ、俳句の奥深さを一緒に楽しんでみましょう!
- 【高齢者向け】夏の俳句。夏を感じるアイディア
- 【高齢者向け】7月の俳句紹介。夏を感じるアイディア
- 【高齢者向け】梅雨を楽しく過ごす。6月にぴったりなイベントアイデア
- 【高齢者向け】6月の健康ネタ。梅雨を楽しく過ごすレクリエーション
- 【高齢者向け】6月の季節感たっぷり。楽しい工作アイデアまとめ
- 【高齢者向け】5月の俳句紹介。楽しいレクリエーション
- 【高齢者向け】春の面白い俳句。ユニークな表現や季語が印象的な句をご紹介NEW!
- 【高齢者向け】12月の有名な俳句。冬の情景や年の瀬を詠む名句と作り方のヒント
- 【高齢者向け】6月を楽しもう!簡単オススメな壁面飾りをご紹介
- 【高齢者向け】9月の俳句。秋にぴったりな句をご紹介
- 【高齢者向け】6月を感じるクイズ。雑学&豆知識問題まとめ
- 【高齢者】8月がテーマの俳句。有名な句をご紹介
- 【高齢者向け】6月にぴったり。簡単な折り紙作品をご紹介
【高齢者向け】6月の俳句紹介。夏を感じるアイディア(1〜10)
あらたうと 青葉若葉の 日の光
松尾芭蕉は江戸時代前期に活躍し、後世では俳聖として世界にも知られる日本最高の俳諧師の1人です。
この句は「奥の細道」で詠んだ句で、日の光の輝きや、それを受けて鮮やかな緑を見せる若葉の美しさや、光を受けて輝く様を表現しています。
「あたらふと」という言葉は、「尊い」という意味を表すものです。
芭蕉は旅の途中、日光で見た若葉の萌える季節の美しさとそれを照らす太陽の光の力強さ、自然の壮大さや生命力を感じ、尊いという表現をしたのかもしれませんね。
五月雨や 大河を前に 家二軒
与謝蕪村は江戸時代中期に活躍した俳人、文人画家で、松尾芭蕉に強いあこがれと尊敬の念を抱き、奥の細道を実際にたどるために東北地方や関東地方を旅したという話があります。
この句の意味は五月の長雨が降り続いて、川が勢いを増して大きくなった川が激しく流れている。
その川のほとりには小さな家が二軒、寄り添って立っている、という内容です。
強まる自然の猛威の前には、たとえ家であっても心細く、なすすべがない存在であることを印象付けるのではないでしょうか。
松尾芭蕉の有名な句にも五月雨を季語としたものがありますので、見比べてみるといった楽しさもありますね。
おもしろうて やがて悲しき 鵜舟かな
鵜飼とは、鵜という鳥を使って、アユなどの川魚をとる伝統漁法です。
たいまつの火が闇夜に浮かぶ船の上を照らすさまは、絵になる美しさがありますね。
芭蕉は岐阜県の長良川でこの鵜飼を見た時にこの句を詠んだと伝えられています。
この句を現代風に表現すると「鵜飼は見ているととても面白く風情があるものだが、その後には悲しさがこみあげてくる」という意味です。
とても面白いものが終わってしまう寂しさや、鵜飼の指示で魚を取り続ける鵜の様子が哀れである、といった、感動から感傷への心情の変化を16文字で描き出した名句です。
かたまるや 散るや蛍の 川の上
夏目漱石は「吾輩は猫である」などで有名な小説家であり、近代日本文学の文豪の1人です。
漱石は大学時代に出会った正岡子規の影響を強く受け、俳句を学びました。
この句の「かたまるや」「散るや」といった表現では、ホタルが群れて1つ光のかたまりになったかと思いきや、次の瞬間にははじけるように散っていく。
その一瞬のはかない美しさが夜の川の上で展開されているといった、夏の夜の一瞬を切り抜いたような、言葉で自然を見事に表現した句となっています。
五月雨や 名もなき川の おそろしき
与謝蕪村は江戸時代中期の俳人、文人画家として活躍しました。
この句を現代語に訳すると「梅雨の大雨の中、地図に名前もないような小さな川が、恐ろしいほどの水量で流れている」といった内容です。
普段は穏やかな川も、大雨の影響で増水し、水害などの不安を与える恐ろしい存在になっていることを表しています。
ちっぽけな存在と侮っていたものが、自分たちの存在を脅かすほどに膨れ上がる自然の力の恐ろしさや、そこにいる人間の小ささ、無力さを改めて感じさせる句ですね。
五月雨を あつめて早し 最上川
松尾芭蕉は江戸時代前期に活躍した俳諧師です。
芭蕉は46歳の時に「奥の細道」で知られるように、東北から北陸を経て、現在の岐阜県辺りまでを巡りながら心情や風景を詠んでいました。
この句は現在の山形県に流れる日本三大急流の1つと言われる最上川を詠った句です。
五月に降り続く長雨の影響で最上川に水が流れ込み、水の勢いが非常に早く、激しい水流であったことを表しています。
季節によって移り替わる自然の様子が目に浮かんでくるようです。
五月雨を 降り残してや 光堂
「奥の細道」の一句であり、東北を旅している際に立ち寄った中尊寺金色堂を見て詠んだものと言われています。
五月雨は現代の梅雨を指します。
梅雨は6月に降る印象がありますが、旧暦では5月にあたるため、この名が付きました。
雨は恵みの雨の一面もありますが、水害があったり、交通を滞らせたり、湿気で物が腐る、かびるといった面もあります。
この句ではそうした長雨の中でも、金色堂だけはまるで雨が降っていないように輝いている、という意味です。
現在では世界遺産として登録された中尊寺金色堂。
梅雨の時期に訪れて、松尾芭蕉の気持ちに重ねてみるのも一興ですね。