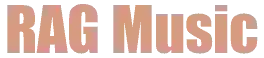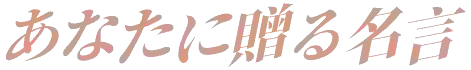別れについての英語の名言まとめ
多くの人にとって、大切にしている名言を一つや二つはお持ちなのではないでしょうか。
著名なアーティストや哲学者、詩人などさまざまな分野におけるスペシャリストは、ハッとさせられるような名言を残しているものですよね。
本稿では「別れについての英語の名言」というテーマを掲げて、映画や漫画の中のキャラクターのセリフも含めたさまざまな英語の名言を集めています。
英文の名言ということで、英語を勉強されている方も楽しめる内容となっていますよ。
本稿で紹介した名言をさらりと引用できるようになれば、カッコいいかもしれませんね!
- 悲しみを癒す別れの名言。前を向くきっかけをくれる言葉たち
- 心に響くすてきな言葉。別れを経験した人に贈りたい名言まとめ
- 失恋の名言
- 英語の失恋の名言
- 【英語の名言】英語が身近なものに感じられる!1度は聞いたことのあるかっこいい英語の名言集
- 偉人たちの胸を打つひとこと名言|心に深く刻まれる言葉集
- 【人生のひとこと名言】そっと背中を押してくれる言葉を厳選
- 短い中にもワードセンスが光る、偉人や著名人たちによる面白い名言
- 仲間を想う心を熱くする名言。信頼と絆の言葉に力をもらえます
- 卒業という旅立ちのときに贈りたい短い名言。勇気と希望が湧く言葉たち
- 洋楽アーティストの人生の名言
- 聞けば感動すること間違いなし!偉人や著名人による心に残る言葉
- 【心に響く!】アニメの名言一覧。かっこいいセリフ特集
別れについての英語の名言まとめ(1〜10)
Some cause happiness wherever they go; others whenever they goオスカー・ワイルド

オスカー・ワイルドさんといえば『ドリアン・グレイの肖像』や『幸福な王子』といった小説をはじめとして、多くの詩集などの著作を残し、破天荒な人生を歩んだ存在として多くの逸話を持つアイルランド出身の詩人にして作家です。
いわゆる19世紀末に勃発した退廃主義的なデカダン派の旗手としても知られるワイルドさんは、作品の中でも実生活でも多くの名言や格言を残しています。
今回取り上げているのは、ワイルドさん手掛けた『パドヴァ大公妃』に出てくるセリフで「Some cause happiness wherever they go; others whenever they go」というもの。
「ある者は行く先で周囲に幸せをもたらし、ある者は立ち去ることで周囲に幸せを生む」といったような意味なのですが、何とも言えず皮肉な言葉ですよね。
アメリカ史上最長のテレビ・アニメーション作品『ザ・シンプソンズ』においても引用されているそうで、なるべくなら後者の立場にはなりたくないものです……。
Only in the agony of parting do we look into the depths of love.ジョージ・エリオット

ジョージ・エリオットさんを知っていますか?
彼は1800年代に活躍したイギリスの小説家で、数々の名著を残しました。
その一方、プライベートでは、恋人が亡くなるという、つらい体験をしています。
そんな彼はこのような名言を残しています。
Only in the agony of parting do we look into the depths of love。
これは、別れの苦しみの中でこそ、私たちは愛の深えんを見つめられる、という意味。
いつの時代も人は何かを失ってから、大切さを思い知る生き物なのかもしれませんね。
The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.チャールズ・ディケンズ

The pain of parting is nothing to the joy of meeting again.これは日本語に訳すと、別れのつらさは、再会の喜びに比べれば大したことはない、という意味です。
この言葉を残したのは、1840年代から1870年代に活躍したイギリスの小説家、チャールズ・ディケンズさん。
彼は多くの名作を書き上げましたが、とくに『クリスマス・キャロル』が有名です。
ぜひ、友人や恋人と離ればなれになる時はこの名言を思い出してください。
それにしても100年以上も前の言葉が、現代人にも刺さるって驚きですよね。
別れについての英語の名言まとめ(11〜20)
It always is harder to be left behind than to be the one to go..Bodie Thoene, Brock Thoene

「It always is harder to be left behind than to be the one to go..」という言葉を目にして、英語が分かる方であれば何ともいえない気持ちにさせられるのではないでしょうか。
こちらの言葉を残したのは、アメリカ出身の夫婦で作家活動を続けているボディ、ブロック・トーネさんです。
歴史小説を手掛けている彼らの著作は世界中で20以上の言語で発売されているほどの人気作家だけあって、発する言葉も鋭いなと感じますし、立ち去るよりも残されるほうがつらい、というのは多くの場面で当てはまりますよね。
It’s better to burn out than fade away.カート・コバーン

1990年代に伝説的なロック・バンドのニルヴァーナを率いてロック・シーンを変えながら、1994年の4月に突然この世を去ったカート・コバーンさん。
音楽だけでなく、コバーンさんがインタビューなどで残した言葉の数々に思わずはっとさせられた方も多いのではないでしょうか。
今回紹介している「It’s better to burn out than fade away.」は最も有名な言葉の1つで、もともとはニール・ヤングさんの楽曲『Hey Hey, My My』の歌詞を引用したものです。
ヤングさんが込めた歌詞の意味とは裏腹に、コバーンさんは「さび付いていくより燃え尽きるほうがいい」といったようなネガティブなニュアンスで遺書にこの言葉を残してしまいました。
ロックスターや若者世代の代弁者としてもてはやされながらも、コバーンさんが望んでいた姿とは違っていたからこその言葉なのかもしれませんが、なんともやりきれないですよね……。
さよならは永遠に思えるかもしれない。お別れは終わりのようだが、私の心の中では記憶であり、あなたはいつもそこにいるだろうウォルト・ディズニー
世界的に有名なアニメーション、映画製作会社を設立するとともに、ミッキーなど多くのキャラクターを生み出したウォルト・ディズニーさん。
人々に夢や希望を届け続けた彼が伝えたのは、大切な人と離れることは永遠の別れではなく、心の奥に刻まれて続く絆があることです。
たとえ物理的に距離があいても、その人との記憶や共有した時間が消えることはありません。
記憶の中で相手はいつも存在し続け、別れが与える悲しさをむしろ温かさへと変えてくれます。
別れを通じて永遠の愛を思い出させてくれる名言です。
Don’t be dismayed at goodbyes. A farewell is necessary before you can meet again.リチャード・バック

アメリカの作家、リチャード・バックさん。
彼は主に飛行機を題材としたルポルタージュ風作品を手掛けていて、特に『イリュージョン 退屈してる救世主の冒険』が有名。
彼はこの本の中に、こんな名言を残しています。
Don’t be dismayed at goodbyes. A farewell is necessary before you can meet again。
これは、別れにうろたえることはない、別れは、再び会うために必要なものだ、という意味。
別れの後には新しい出会いがあるよと、はげましてくれているようですね。