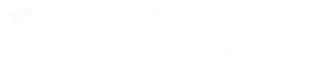【低学年から遊べる】国語のゲーム・遊び
小学生の国語、ひらがなやカタカナ、漢字など覚えることがたくさんありますよね。
子供たちも覚えることが多くて頭の中がごちゃごちゃに、そして嫌になってしまう……その前に!
遊びで楽しく覚えられる、勉強になる国語ゲームで苦手意識を改善してみるのはどうでしょうか?
漢字や文字に特化した、国語のゲームや遊び、アプリなどをたっぷりとご紹介しています。
親子で楽しめるゲームもあるので休日に親子で取り組んでみるのもオススメです!
- 【遊んで覚える!】漢字がテーマのおすすめゲーム
- 【レク】おもしろい!言葉遊びゲームまとめ
- 小学生向けの盛り上がるクイズ。みんなで一緒に楽しめる問題まとめ
- 【簡単】小学生が解ける!知恵を育むクイズ集
- 【小学生向け】暗号クイズ。面白い謎解き問題
- 【小学生向け】オススメの謎解き問題まとめ
- 遊びながら九九を覚えられるゲーム
- 【小学校】すぐ遊べる!低学年にぴったりの室内レクリエーション
- 中学生向けの楽しい遊び。レクリエーションゲーム
- 【小学生向け】Zoomで楽しめるゲームや遊びまとめ
- 【簡単】小学生向けのなぞなぞ
- 【すぐ遊べる!】小学生にオススメの盛り上がるレクリエーションゲーム
- 【こども向け】勝っても負けてもおもしろい!じゃんけんゲームのアイデア集
【低学年から遊べる】国語のゲーム・遊び(11〜20)
漢字かくれんぼ
漢字のつくりを利用したクイズです。
答えがひとつではないので、参加者同士のコミュニケーションのきっかけにも使えます。
たとえば、「田」のような4つのマス目がある四角形にかくれている漢字だと、「口」や「日」などの漢字が回答されるかと思います。
このように、図形の中にかくれている漢字を考えて、出し合っていこうという内容です。
漢字と少し形が違っているものが現われると、意見交換が白熱して盛り上がるのではないでしょうか。
図形ではない漢字を使うと、漢字に使われているパーツを考え、成り立ちについて考えるきっかけにも使えます。
小学生手書き漢字ドリル

小学校で習う漢字、1026個を学べるアプリです。
漢字の書きに注目したシンプルなつくりのアプリですね。
指でなぞって書くことも可能ですが、タッチペンを使うとより正確な書き取りに近づけるのではないでしょうか。
漢字ドリルに出題されるような問題が登場し、それに合わせた漢字を書くという形式で進行していき、正解をすぐに判定していくところも重要なポイントです。
漢字のバランスや書き順など、書きにおいて大切な部分をしっかりと判断して、教えてくれるアプリです。
部首あてゲーム

漢字の成り立ちや意味を考える際に、部首を考えることも大切なポイントです。
そんな部首について、クイズ形式で覚えていこうというゲームですね。
テーマがわかりやすいからこそ、さまざまな出題形式で、部首について考えさせることが可能です。
部首の名前を答えさせる形式で、簡単なものと難しいものを混ぜることがポイントです。
見たことはあるけれど、名前はわからないと思わせることが大切で、その体験をとおすことで部首の名前と意味を深く理解していけます。
漢字のどの部分が部首にあたるのかも合わせて考えられたら、さらにおもしろくなりそうですね。
慣用句かるた
慣用句とは、習慣として使われるひとまとまりの言葉で、独特な言い回しが特徴です。
ことわざとは違って、別のものにたとえて表現する言葉も多く、正しく理解していないと会話が成立しないことも起こりえます。
かるたでの遊びをとおして、慣用句を覚えていこうという試みです。
慣用句の意味だけでなく、解説や例文も掲載されているので、絵札を取ったら言葉の意味もしっかりと考えてみましょう。
この『慣用句かるた』から派生して、これ掲載されていない近い言い回しの言葉を調べても良いかもしれません。
漢字部首リレー
漢字にはそれぞれ部首が存在するものもあり、その部首が漢字の意味にかかわっていたりもします。
そんな感じのつくりを知る際の、大切なポイントでもある部首を使った簡単なゲームです。
部首が指定されて、その部首を持つ漢字を制限時間にどれだけ書けるかというシンプルな内容。
知識を出し合って高めていくといった点でチーム戦にした方がいいのかもしれません。
早さを競う要素があり、雑な字になるおそれもあるので、そこは厳しくポイントを付けていきましょう。
ひらがなしりとり

しりとりは言葉の最後の文字を取って、その文字から始まる単語を発表、それを繰り返していくという誰でも遊んだことのあるゲームかと思います。
単純なしりとりでも、新しい言葉を知れますが、クイズ形式にしてみても楽しく遊べます。
ひとつの言葉を発表して、制限時間内にその言葉に続くものをどれだけ思いつけるかを競う形式でおこなうと、言葉を思い出すことに集中できますよね。
2つの言葉の間をつなぐ言葉を考えてみると、難易度も上がって、さらに楽しめるのではないでしょうか。
他の人の回答と比べて、新しい言葉を知っていくのもおもしろいポイントですね。
【低学年から遊べる】国語のゲーム・遊び(21〜30)
反対言葉クイズ

知っている言葉を思い出そう!
反対言葉クイズのアイデアをご紹介しますね。
反対言葉とは、ある言葉と意味が正反対の言葉のことを指し「対義語」ともいいますよね。
今回は、反対言葉に関するクイズにチャレンジしてみましょう。
聞き覚えのある言葉を思い出しながら挑戦すると良いかもしれませんね。
例えば「うえの反対言葉は、何でしょう?」というような問題がイラストと一緒に出題されていますよ。
イラストがヒントになっているので、気軽に取り組んでみてくださいね。