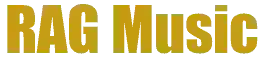【2026】カラオケでおすすめの簡単な演歌~男性歌手編
日本のふるさとのような音楽ジャンルといえば、やはり演歌が筆頭に挙げられますよね。
昭和の時代から令和の現代も歌い継がれる演歌の名曲たちは、カラオケでも根強いに人気を誇ります。
とはいえ演歌を歌うとなれば水準以上の歌唱力が求められますし、うまく歌えない……または歌ってみたいけどハードルが高そう……そんな風に感じている方も多いでしょう。
こちらの記事では、技術的に難しい曲も多い演歌の中でも比較的簡単で歌いやすい男性歌手による演歌の定番の人気曲、そして近年の楽曲も含めて紹介しています。
女性歌手のカラオケにおすすめの簡単な演歌は他の記事で紹介していますから、そちらも要チェックです!
- 【2026】高音が魅力的な男性歌手のオススメ演歌
- 【2026】歌いやすい演歌~往年の名曲から最近のヒット曲まで【男性歌手編】
- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~男性歌手編
- 【2026】高音が苦手な方にオススメ!低音で歌える男性歌手の演歌
- 【2026】歌うのが難しい演歌~男性歌手編
- 【2026】カラオケでおすすめの簡単な演歌~女性歌手編
- 【2026】歌えたらすごい!演歌の名曲【男性歌手編】
- 男性にオススメの歌いやすい演歌。カラオケで挑戦したい曲まとめ
- 【日本一の歌唱力】福田こうへいさんの歌いやすいカラオケ曲
- 【演歌】音痴の方でも歌いやすい曲【男性歌手編】
- 【サブちゃん】北島三郎の歌いやすい曲まとめ【2026】
- 【2026】歌うのが難しい演歌~女性歌手編
- 【2026】男男デュエットの演歌・歌謡曲の名曲まとめ
【2026】カラオケでおすすめの簡単な演歌~男性歌手編(21〜30)
チョメチョメホリエモン

まさかまさかの演歌歌手デビューで話題を呼んだ、ホリエモンこと堀江貴文さんによる楽曲で、2025年1月にリリースされました。
思わず口ずさみたくなる、キャッチーなサビフレーズが魅力の一つ。
歌詞は「汗水垂らして働いたあとはパーっとお酒を飲もう!」という痛快な内容です。
華やかな雰囲気の曲調も相まって、聴くとスカッとするんですよね。
気分をリセットしたいときにぴったりなナンバーだと思います!
凪か嵐か一条貫太

海洋をテーマに描かれた作品の第三弾となる本作は、波風の穏やかな時も激しい時も、たゆまぬ覚悟を持って前に進み続ける漁師の姿を力強く表現しています。
万城たかしさんの手による歌詞と、宮下健治さんが紡ぎ出すメロディが見事に調和し、一条貫太さんの伸びやかな歌声が心に響きます。
疾走感と躍動感にあふれた本作は、人生の岐路に立ったとき、新たな一歩を踏み出す勇気が必要な方に寄り添う一曲となることでしょう。
【2026】カラオケでおすすめの簡単な演歌~男性歌手編(31〜40)
まつり北島三郎

北島三郎さんの楽曲といえば、まずこちらの『まつり』を思い浮かべる方も多いのではないでしょうか?
本作はそのタイトルが示す通り、祭りをテーマにした非常に華やかなメロディーが特徴です。
力強い演奏のため、ボーカルラインにもそういった印象を持たれやすいのですが、実は本作……。
演歌のなかでも特に音域が狭い作品なのです。
特に男性であれば、誰でも問題なく発声できるでしょう。
こぶしの登場回数も意外に少ないので、間違いなく初心者向けの演歌と言えます。
北の漁場北島三郎

強風の音を取り入れた勇ましいイントロが印象的な作品『北の漁場』。
本作は北島三郎さんが最も得意としている男歌に分類される作品です。
男歌というとシャウトを取り入れた荒々しい歌い方が一般的で、本作でもそういった要素が登場します。
ただ、本作はサビ以外ではシャウトが登場しないので、彼の作品のなかでは歌いやすい部類の男歌と言えるでしょう。
伸びやかなサビですが、意外にもロングトーンは少ないため、基礎歌唱力がなくても十分に歌えます。
こぶしも北島三郎さんの作品として控えめなので、練習曲にはもってこいの作品です。
東京の空北島三郎

2024年の11月にリリースされた北島三郎さんの新曲『東京の空』。
最近の北島三郎さんは、かつての音域の広さはありませんが、その代わりに低音域を強調した楽曲をよくリリースしています。
本作も例にもれず、低音を主体としています。
そのため、音域は非常に狭いのが特徴です。
こぶしも昔のような激しい音階の変化を見せるわけではなく、あっさりとしたものが多いので、演歌の歌い回しが苦手な方でも歌いやすい楽曲と言えるでしょう。
ぜひレパートリーに加えてみてください。
橋北島三郎

男歌に定評がある北島三郎さん。
これまでにいくつもの名作と言われる男歌を世に生み出してきたわけですが、その中でも特に勇気を与えてくれる前向きな男歌として人気を集めているのがこちらの『橋』。
やや力強い歌い方が特徴ですが、それほど難しいわけではなく、歌い出しの部分にシャウトをかけているだけなので、アマチュアでも十分に再現可能です。
こぶしも力強くはあるものの、ヒーカップ唱法を使った複雑なものではないため、演歌をある程度歌い慣れている方であれば、問題なく歌いこなせるでしょう。
北の街 函館北川大介

港町を舞台に展開する、胸に染み入る大人の恋物語を紡ぎだした北川大介さん。
懐かしい昭和歌謡の雰囲気を色濃く残しつつ、テナーサックスが効果的に響き渡る本作は、切なさと温かみが見事に調和した珠玉の一曲です。
2025年2月にリリースの楽曲は、函館の街を舞台に、今は離れ離れになってしまった恋人への思いを、見事なまでの歌唱力で表現しています。
レンガ通りや夜景など、函館の情緒豊かな風景描写を織り交ぜながら、大切な人を思う気持ちが胸に迫ってきます。
ゆったりとした夜に一人で聴きたい、しっとりとした大人の演歌として、心に深く響く一曲となっています。