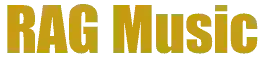昭和を代表する男性演歌歌手まとめ
2020年代の現在は「演歌第七世代」なる言葉も生まれ、若手の才能も次々とデビューを果たし活況を呈する演歌。
演歌の成り立ちは明治の時代にまでさかのぼると言われていますが、多くの人がイメージする「演歌」が確立されたのは1960年代後半辺りと言われています。
こちらの記事では、そんな根強い人気を誇る「演歌」の歴史を語る上で欠かせない、昭和の時代を彩った代表的な男性演歌歌手をまとめてみました。
すでに旅立たれた方から、令和の今も現役で活躍する歌手まで、演歌を作り上げた大御所たちの歴史をぜひこの機会に知ってくださいね。
ちなみに女性歌手は他の記事でまとめていますから、そちらも要チェックです!
- 70代の男性演歌歌手まとめ。演歌界を支える名歌手たち
- 【男性歌手編】大みそかの顔!紅白歌合戦に出演した演歌歌手
- 80代の男性演歌歌手まとめ。演歌界に名を残すベテランたち
- 【演歌】音痴の方でも歌いやすい曲【男性歌手編】
- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~男性歌手編
- 【2026】東北出身の演歌歌手
- 【2026】歌えたらすごい!演歌の名曲【男性歌手編】
- 【男性向け】難易度の高い演歌の名曲
- 昭和を代表する女性演歌歌手まとめ
- 【2026】歌うのが難しい演歌~男性歌手編
- 【2026】演歌の歴代売上枚数ランキング
- 【2026】歌いやすい演歌~往年の名曲から最近のヒット曲まで【男性歌手編】
- 【2026】演歌第七世代!若手演歌歌手まとめ
昭和を代表する男性演歌歌手まとめ(1〜10)
みちのくひとり旅山本譲二

「みちのく」をテーマにした民謡調の楽曲で一躍有名となった山本譲二さん。
1976年に読売テレビの「全日本歌謡選手権」で勝ち抜き本名でデビューしましたが、大ヒットには恵まれず。
そんな中、1980年にリリースした楽曲が、翌年のフジテレビ「夜のヒットスタジオ」出演を機に大ブレイク。
日本レコード大賞のロング・セラー賞を受賞し、NHK紅白歌合戦初出場も果たしました。
独特の哀愁漂う歌声と、繊細な表現力で多くのファンを魅了し続ける山本さん。
近年では「山本譲二 ヘヴィメタル化計画」と称し、ヘヴィメタルとのコラボにも挑戦。
演歌の枠にとらわれない新境地を開拓する姿勢は、ジャンルを超えた音楽ファンにもおすすめです。
哀愁列車三橋美智也

昭和を代表する演歌界の巨星、三橋美智也さん。
北海道生まれの彼は、幼少期から民謡の才能を発揮し、1954年に『酒の苦さよ』でデビュー。
翌年には大ヒット曲を世に送り出し、以降も数々の名曲を生み出しました。
民謡で培った伸びやかな高音と独特のこぶし回しが特徴で、「三橋で明けて三橋で暮れる」と称されるほどの人気を博しました。
1962年には日本レコード大賞歌唱賞を受賞。
津軽三味線の名手としても知られ、若者を魅了しました。
後進の育成にも力を注ぎ、「民謡三橋流」を興すなど、その功績は計り知れません。
演歌や民謡、歌謡曲を愛する方にぜひおすすめの歌手です。
北帰行小林旭

日活アクション映画の黄金期を支え、銀幕のスターとして君臨した小林旭さん。
1956年に映画『飢える魂』でデビューし、長身と屈強な身体を活かした硬派な役柄で「マイトガイ」の愛称が定着しました。
俳優業と並行して歌手としても活躍し、映画主題歌からムード歌謡、都会派演歌まで幅広いレパートリーを持っています。
バリトン寄りの中低域で語りと歌の境目を往還するフレージング、語尾の掠れとビブラートを効かせた歌唱は唯一無二。
身長180cmで柔道五段という武道の素養を持ち、スクリーンのアクションを実演で支える身体性も魅力のひとつです。
昭和を代表する男性演歌歌手まとめ(11〜20)
星影のワルツ千昌夫

深い情感と郷愁を誘う歌声で知られる千昌夫さんは、1965年に『君が好き』でデビューを飾りました。
翌年にリリースされた星影をテーマにしたワルツ曲は、1967年秋頃からヒットし、ミリオンセラーを記録。
この成功により、1968年のNHK紅白歌合戦に初出場を果たします。
1977年には北国の情景を歌った曲をリリースし、2年間にわたり歌い続けた結果、大ヒットとなりミリオンセラーを達成。
第21回日本レコード大賞のロングセラー賞を受賞し、中国やシンガポールなどアジア各国でも人気を博しました。
飛行機とヘリコプターの免許を取得し、自家用セスナを所有していたという異色の経歴も持つ千昌夫さん。
演歌好きはもちろん、昭和の歌謡曲に興味がある方にもおすすめの歌手です。
無法松の一生 (度胸千両入り)村田英雄

浪曲の世界から戦後の歌謡界のスターとなり、昭和を代表する演歌界の大御所として活躍したのが村田英雄さんです。
1958年に『無法松の一生』でデビューした村田さんは、1961年の『王将』で一躍人気歌手の仲間入りを果たしました。
浪曲で培った力強い歌声と男らしい世界観が特徴で、『柔道一代』『男の土俵』など多くのヒット曲を生み出しました。
紅白歌合戦には通算27回出場し、1961年から1972年までは12年連続で出場するなど、その実力は折り紙付き。
糖尿病と闘いながらも歌い続けた姿勢は多くのファンの心に刻まれています。
男らしい演歌の魅力に惹かれる方にぜひおすすめしたい歌手です。
酒よ吉幾三

昭和の演歌界を代表する個性派歌手として知られる吉幾三さん。
フォークソング調の『俺はぜったい!プレスリー』で1977年にデビューを果たしましたが、コミカルな方言曲や本格的な演歌まで幅広いジャンルで活躍し続けています。
1984年には千昌夫さんへの提供曲『津軽平野』がヒット。
同年、自身の『俺ら東京さ行ぐだ』が大ブレイクし、全国的な知名度を獲得しました。
1986年には『雪國』で日本レコード大賞金賞を受賞。
以降も『酒よ』『酔歌』など数々のヒット曲を生み出し、演歌歌手としての地位を確立。
2019年には全編津軽弁のラップ曲をリリースするなど、常に新しい挑戦を続けています。
吉さんの魅力は、演歌の枠にとらわれない自由な音楽性。
シンガーソングライターとしての才能も高く評価されていますよ。
別れの一本杉春日八郎

漁師の家に生まれた春日八郎さんは、1952年に『赤いランプの終列車』でデビュー。
その後『お富さん』が大ヒットし、一躍人気歌手の仲間入りを果たします。
澄んだ美しい高音と情感豊かな歌唱で多くのファンを魅了した春日さんは、生涯で1600曲以上を吹き込み、レコードの総売上は7000万枚を超えるほどの国民的演歌歌手に。
1989年には紫綬褒章を受章し、1991年には勲四等旭日小綬章を受章するなど、その功績は高く評価されています。
昭和の演歌を語る上で欠かせない存在として、今なお多くの人々に愛され続けている春日さんの楽曲は、演歌ファンはもちろん、昭和の歌謡曲に興味のある方にもぜひ聴いていただきたいですね。