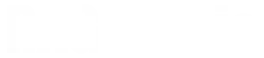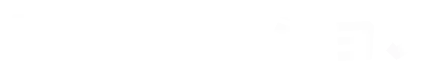昭和のレトロで懐かしい笑えるクイズ。高齢者の方と楽しむ思い出話
「ドン!」という大きな音とともにお菓子ができあがる懐かしい光景、覚えていらっしゃいますか?
昭和の時代を彩った身近なものから、レトロな暮らしのアイテムまで、思わず高齢者の方が「あったあった!」と笑ってしまう楽しいクイズをご紹介します。
黒電話や伝言板、全国に広がったボウリングブームなど、あの頃の記憶がよみがえる問題ばかりです。
ご家族やお友達と一緒に、昔話に花を咲かせながら楽しいひとときをお過ごしくださいね。
- 昭和レトロが懐かしい!高齢者の方に盛り上がるクイズ特集NEW!
- 高齢者が盛り上がる!雑学豆知識クイズで頭も心もすっきりNEW!
- 季節と行事のクイズ特集。高齢者と一緒に笑顔あふれる時間をNEW!
- 高齢者と楽しもう!食べ物・料理の盛り上がるクイズ集NEW!
- 【高齢者向け】7月雑学クイズ&豆知識問題。簡単で盛り上がるNEW!
- 【高齢者向け】夏祭りの雑学クイズ&豆知識問題。知識が増える楽しいクイズNEW!
- 高齢者が盛り上がる言葉と漢字のクイズ遊び。楽しく脳トレ!NEW!
- 【高齢者向け】とんち・なぞなぞクイズ!思わず感心して盛り上がる問題集
- 【高齢者向け】盛り上がる!面白い懐かしいクイズ
- 【高齢者向け】懐かしい!回想法にオススメな昭和クイズ
昭和のレトロ・懐かしいグッズ
野外で派手な衣装を着てディスコサウンドに合わせ「ステップダンス」を踊ることが1980年代後半に流行りました。このような人たちを何族と呼んだのでしょうか?
平成以降、たくさんのダンスボーカルグループが誕生していますが、それよりも前に、大きなダンス集団がいたんですね!
東京の代々木公園の近くや吉祥寺、池袋、そして名古屋でもその姿が見られたそうですが、一体なんという名前の方々が活動されていたのでしょうか。
ある野菜と同じ名前というのが、ヒントです。
その答えは、竹の子族!
竹の子族と呼ばれた方の中にはたくさんのグループが存在し、中にはスカウトされ芸能界デビューを果たした人もいたそうです。
現在の目覚まし時計は電池で動いていますが、昭和はなにで動いていたでしょう?
身近な家具や家電が時代とともにスタイリッシュになっているイメージですが、そこにある機能も実はさまざまな変化をとげています。
そんな生活に欠かせないものの中から目覚まし時計に注目、昭和の時代はどのような仕組みだったでしょうか。
目覚ましに限らず、何で動く時計があったのか、昔の機械の仕組みを想像すれば、答えに気付ける人もいるかもしれませんよ。
答えはぜんまい式、少なくはなっているものの、消えた技術ではないのでこれをきっかけに探してみるのもオススメです。
つまようじの先端が赤色の場合は当たりでもう一本もらえた、駄菓子は何でしょうか?
子どもたちにとっての憩いの場であった駄菓子屋さん、好きなお菓子がお財布にもやさしく楽しめるスポットですよね。
そんな駄菓子屋さんの魅力のひとつに、あたりが出たら同じものと交換できるという制度がありました。
あたりの表示にはさまざまなパターンがありましたが、その中でも、つまようじの先端が赤かったらあたりのお菓子といえば何だったでしょうか。
答えはきなこ棒、小さくて食べやすいサイズだからこそ、あたりを目指して食べ過ぎてしまったという人もいるかもしれませんね。
ベーゴマはもともとは何を回していたのでしょうか?
懐かしい遊びの代表的なものとしても扱われるベーゴマ、他のコマをはじき出すようすは心を熱くさせますよね。
そんなベーゴマは金属で作られた重たいものというイメージが強いかと思いますが、もともとは違うものを使っていたと語られています。
そんなベーゴマの材料には何を使っていたのでしょうか。
平安時代が起源、自然のものを使っていたと考えると答えにもたどり着けそうですね。
答えはバイ貝、この貝殻に砂をつめてとがった部分を軸にするように回していたそうです。
形や大きさも違う素材なので、回しやすさや強さにも差が出てしまいそうな印象ですね。
一本のヒモで指や手首にかけていろいろな形を作る遊びを何というでしょうか?
シンプルな道具でどこまで遊べるかといった部分で、子どもの発想力や遊びにかける情熱が試されます。
そんな遊びへの工夫はいつの時代も変わらず、伝統的な遊びであっても道具はシンプルな場合が多いですよね。
そんな伝統的な遊びの中で、1本のヒモを指や手にかけて形を作っていくものといえば何でしょうか。
答えはあやとり、伝わっている定番の形の再現を目指していくパターンだけでなく、オリジナルの形に挑戦したという人も多いかと思います。