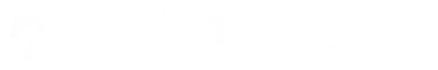【スマホ依存】知っておきたい雑学クイズ・豆知識問題まとめ
スマートフォン依存が社会問題として深刻化する中、あなたも「もしかして私も……?」と不安に感じているのではないでしょうか?
実は、誰もが陥る可能性があるスマホ依存の不思議と真実を、今回は手軽なクイズ形式でお届けします。
あなたやご家族の生活習慣を見直すきっかけにもなる豆知識の数々に、ぜひ気軽にチャレンジしてみてください。
知っているようで意外と知らない、スマホとの上手な付き合い方が見えてくるかもしれません!
- 【便利機能】思わず試したくなるiPhoneの雑学&豆知識
- 【知っていますか?】健康にまつわるおもしろ豆知識クイズ
- 知ってると役立つ豆知識クイズ。学校や家で活躍する雑学【子供向け】
- 【暇つぶし】思わず誰かに教えたくなる雑学クイズ特集
- おもしろい雑学のクイズ。新しい気づきに出あえる豆知識
- 日常で即使える!役立つ驚きの雑学&豆知識
- 【面白い】雑学クイズの問題まとめ
- 【いくつわかる?】熱中症の雑学&豆知識クイズで一般常識をチェック
- 【スピーチにも】朝礼にオススメの雑学・豆知識クイズ
- 小学生にオススメ!知ったら人に話したくなる雑学クイズ
- 小学生向けの4択クイズまとめ。身の回りのものに関する雑学クイズ
- 学校にまつわる雑学クイズ。自慢したくなる豆知識まとめ
- 盛り上がる!人に話したくなる雑学クイズ。意外に知らない雑学集
【スマホ依存】知っておきたい雑学クイズ・豆知識問題まとめ(1〜10)
スマホ依存により、目の疲れや肩凝りが生じることを何と言うでしょうか?
- ドライアイ
- 眼精疲労
- 情報過多症候群
こたえを見る
眼精疲労
スマートフォンやパソコンの画面を長時間見続けることで、目の筋肉や神経に負担がかかり、目の疲れや肩こり、頭痛などの症状が現れることを「眼精疲労」と呼びます。
眼精疲労は適切な休憩や目の体操、十分な睡眠を心がけることで予防や軽減ができます。
スマホ依存の症状として当てはまらないもは次のうちどれでしょうか?
- スマホがないと不安や焦りを感じる
- 注意力や集中力が低下する
- 外出時にスマホを忘れても気にしない
こたえを見る
外出時にスマホを忘れても気にしない
外出時にスマホを忘れても気にしないというのは、スマホ依存の傾向がない人に見られる特徴です。
スマホ依存の人は、外出時にスマホを忘れてしまうとソワソワして不安になり、わざわざ取りに帰ってしまうほど。
他の選択肢も、いずれもスマホ依存の症状として知られています。
スマホ依存は一日何時間からと言われているでしょうか?
- 3時間以上
- 5時間以上
- 明確な基準はない
こたえを見る
明確な基準はない
スマホ依存については多くの研究がありますが、明確に「何時間以上」という基準は実は存在しません。
利用時間だけでなく、日常生活への支障や自己コントロールができないかどうかが判断に用いられています。
【スマホ依存】知っておきたい雑学クイズ・豆知識問題まとめ(11〜20)
スマホ依存によって、精神面に出る影響として正しいものはどれでしょうか?
- 自己肯定感が上がる
- コミュニケーション能力の向上
- 不安やうつ症状が出現
こたえを見る
不安やうつ症状が出現
スマホ依存によりSNSなどで他人と自分を比較したり、承認欲求が満たされないことで、自己肯定感が低下する傾向があります。
他の選択肢は精神面の影響として当てはまりません。
スマホ依存になると、自己肯定感は下がり、コミュニケーション能力は低下します。
スマホ依存によって、認知機能に出る影響として正しいものはどれでしょうか?
- 記憶力の向上
- 集中力の低下
- 論理的思考力の強化
こたえを見る
集中力の低下
スマートフォンを頻繁に操作したり通知が多い環境にいると、集中が途切れやすくなり、持続して一つの課題に取り組む力が低下する傾向があります。
特に若年層において、学習効率や仕事のパフォーマンス低下の要因のひとつとされています。
スマホ依存によって、身体面に出る影響として正しいのはどれでしょうか?
- 骨密度が上がる
- 睡眠障害
- 姿勢が良くなる
こたえを見る
睡眠障害
スマホ依存による大きな身体的影響のひとつが睡眠障害です。
スマホの画面から発せられるブルーライトは、眠気を促すメラトニンというホルモンの分泌を妨げるため、寝つきが悪くなったり眠りが浅くなったりします。
一方で骨密度が上がる・姿勢が良くなるという影響はありません。
スマホ依存の人がスマホを利用する目的として、最も多いものは何でしょうか?
- 動画視聴
- 情報収集
- SNS
こたえを見る
SNS
さまざまな調査によると、スマホ依存傾向が強い人の多くはSNS(ソーシャルネットワーキングサービス)を主な利用目的としています。
SNSは他人とのコミュニケーションや情報共有、最新情報の取得などが即座にできるため、一度使い始めると通知や更新が気になりやすい特徴があります。
そのため、SNSの過剰利用がスマホ依存を助長すると言われています。