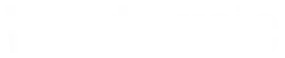吹奏楽コンクールにおすすめの曲
全国の吹奏楽人が目指すコンクール。
1年間そのコンクールに向けてたくさんの練習をしていますよね。
そんなコンクールで演奏するのは、部門にもよりますが、課題曲と自由曲の2曲。
課題曲は毎年発表される数曲の中から選びますが、自由曲はどのように決めていますか?
長年演奏してきた演奏し慣れた曲で挑むバンドもあれば、新しい曲で勝負するバンドもあると思いますが、どちらにせよ非常に悩みますよね。
そこで、この記事では、コンクールの自由曲にオススメの曲を厳選して紹介します。
定番の名曲、最近の人気曲などを紹介していきますので、ぜひ参考にしてくださいね!
- 自由曲や演奏会の選曲に!吹奏楽の名曲・定番の人気曲を紹介
- 【歴代】吹奏楽コンクールの人気課題曲まとめ
- 定番の吹奏楽メドレー
- 【吹奏楽】初心者におすすめ!練習にもピッタリの名曲&人気曲集
- 【吹奏楽】文化祭で盛り上がる!吹奏楽部が吹きたいオススメの曲
- 【マーチ】行進曲の定番&演奏会で人気の華やかな作品を厳選!
- 【定番曲から人気メドレーまで】吹奏楽で盛り上がるポップス集
- 【行進曲・マーチ】運動会や体育祭の入退場にオススメの人気曲を厳選!
- 【吹奏楽】男子が好きな吹奏楽曲。男性におすすめの吹奏楽の名曲
- 【中高生必見!】合唱コンクールのオススメ自由曲カタログ
- 吹奏楽で演奏したいゲーム音楽まとめ
- フルート初心者のための練習曲。おすすめの練習曲
- 吹奏楽部を辞めたいと思っているあなたへ。こんな理由では辞めないほうがいい
吹奏楽コンクールにおすすめの曲(21〜30)
民衆を導く自由の女神樽屋雅徳
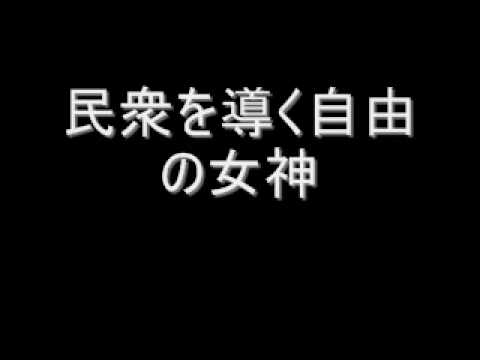
フランスの有名な革命絵画を題材にした、樽屋雅徳さん作曲のドラマティックな吹奏楽曲。
抑圧からの解放を求める民衆の姿と、革命の壮大な物語が目に浮かぶような音楽です。
この楽曲では、「Liberty」と名付けられたテーマが自由の女神の象徴として何度も登場し、聴く人の心を奮い立たせます。
2000年代前半から親しまれている作品で、アルバム『樽屋雅徳作品集II~ラザロの復活』でもその感動的な演奏を聴くことが可能です。
本作はコンクールの自由曲としても人気が高く、演奏する学生たちの熱い想いを乗せて、会場を感動の渦に巻き込んできたのかもしれませんね。
何かに挑戦するあなたの背中を、力強く押してくれる一曲です。
大阪俗謡による幻想曲大栗裕

「東洋のバルトーク」などと称されている日本を代表する作曲家、大栗裕の人気作品です。
1955年に指揮者である朝比奈隆のために作曲され、1956年に朝比奈隆が率いる関西交響楽団によって初演されました。
神道の神楽のような序奏の雰囲気、天神祭のだんじりはやしのリズム、都節音階、生國魂神社の夏祭りにおける獅子舞といった大阪の俗謡と西洋音楽を融合させ昇華させた1曲です。
多岐にわたる曲調でさまざまな大阪の顔を表している作品です。
序曲「祝典」Frank Erickson

高らかなファンファーレのような響きが、演奏会を華々しくいろどる、演奏会のオープニングにふさわしい序曲『祝典』。
作曲者のフランク・エリクソンさんはアメリカの作曲家で、吹奏楽向けの楽曲を多く作曲しており、この序曲『祝典』も代表的な作品のひとつです。
軽やかな導入部と、ミドルテンポのゆったりと伸びやかな中間部、そして中間部を経て、再び華やかなメロディーとテンポに戻ります。
動きのあるスリリングなエンディングが印象的。
小編成のバンドでも演奏可能なので、コンクールやコンサートなどでも広く選曲される人気楽曲です。
スク―ティン・オン・ハードロック~3つの即興的ジャズ風舞曲~David R. Holsinger

スウィング感があふれるジャジーなサウンドがたまらない、吹奏楽の名曲です。
アメリカの著名な作曲家David R. Holsingerさんの作品で、3つの短いスキャット風ダンスからなるエネルギッシュな組曲となっています。
寂れてしまった故郷の道を「素早く駆け抜ける」というユーモアを込めた逸話が、本作の軽快で即興的な雰囲気の源泉。
聴いているだけで体が動き出しそうです。
アルバム『The Music of Holsinger, Vol. 8』に収録されており、2012年にはドラムコーの競技会で取り上げられ、そのかっこよさで観客を魅了しました。
木管と金管がスリリングに掛け合う場面は、演奏者も聴衆も一気にテンションが上がるはず!
演奏会で目立ちたい、テクニカルな曲で沸かせたいという方にぴったりの一曲です。
セルリアン・ウィンド郷間幹男

2018年度のコンクール課題曲作曲者である郷間幹男作曲の1曲。
コンクールの自由曲としてもよく映える美しさと壮大さのある楽曲ですね。
緩急がはっきりと付けられた楽曲展開で、とくに楽曲の後半に入ってすぐの木管楽器のみのパートの美しさは至高。
さらにそこから展開していく流れるように流麗なメロディ、各楽器の絡み合い、そして勇壮な雰囲気で締めくくられる様子は必聴です。
カットやソロ楽器の変更、編成のアレンジも自由に可能な曲とのことなので、どんなバンドでも演奏しやすい曲だと思います。
華麗なる舞曲Claude Thomas Smith

技術的に最も難しい曲とも評される吹奏楽の名曲、クロード・トーマス・スミスさんの『華麗なる舞曲』は、その華やかさと音の厚みが魅力的な人気曲です。
重なる金管の音色と目まぐるしく連なる木管の連符が、技術的な難易度を示しますが、楽曲のイメージは難解というより非常にキャッチーで親しみやすいものです。
パワフルな曲調は、もともと最高実力と言われるアメリカ空軍軍楽隊のために作曲されたものだからでしょうか。
吹奏楽の王道をいくようなストレートで力強いナンバーです。
プロヴァンスの風田坂直樹

スペインとプロヴァンスの風景を見事に音楽で描き出した、爽やかで華やかな吹奏楽曲。
田坂直樹さんが生み出した本作は、情熱的なスペインのリズムと、のどかなプロヴァンスの旋律が見事に調和しています。
金管楽器の勇壮なファンファーレと木管楽器の優美な旋律が織りなす世界観は、聴く人の心をわしづかみにすることでしょう。
2015年度全日本吹奏楽コンクールの課題曲IVに選出され、多くの吹奏楽団によって演奏された本作は、コンクールはもちろん、演奏会のプログラムにも最適な1曲です。