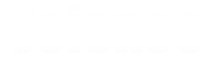先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア
理科の自主学習は、子供たちにとって楽しい冒険にもなります!
こちらでは4年生にオススメの、先生に褒められそうな自学理科のテーマを紹介します。
自由に調べてみると、学ぶことがもっと楽しくなりますよ。
身近な自然を観察したり、簡単な実験をしてみたりして、いろいろなことを発見する喜びを味わってください。
自然や科学に対する興味が育って、自分が学んだことを友達や家族に話せることも楽しいですよ。
ぜひ、こちらを参考にして、一緒に楽しい理科の世界に飛び込んでみてくださいね!
- 小学4年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア
- 先生に褒められる自主学習!5年生にオススメの自学理科のアイデア
- 先生に褒められる自主学習!3年生にオススメの自学理科のアイデア
- 【小学4年生】身近な材料でできる!楽しい自由研究のアイデア集
- 小学生にオススメ!4年生向けの作って楽しい工作アイデア集
- 小学5年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 小学生の自由研究にオススメ!身近な材料で実験&観察のアイデア
- 小学3年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】
- 【小学6年生向け】人とかぶらない!楽しい自由研究のアイデア集
先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア(11〜20)
豆腐作り

そのまま食べてもよし、調理して食べてもよしの日本人から親しまれている豆腐を作る方法を紹介します。
理科の実験のように豆腐が固まる理由が分かるとともに、完成した自家製の豆腐を食べて楽しめるのがポイント。
鍋に入れた豆乳を75度になるまで加熱したら、にがりを加えてかき混ぜます。
フタをして10分ほど蒸らしたら、布を敷いた型に固形物を移しましょう。
重しを乗せて水分をとり、ボールにセットした水に20分ほどさらしたら豆腐の完成です。
にがりに含まれるマグネシウムとタンパク質が結合することで液体が固まることを学びながら作るのもオススメですよ。
しゅわしゅわラムネの実験
水の中に入れたときの色合いや音が楽しめるしゅわしゅわラムネを夏休みの自由研究に作ってみませんか。
粉糖やコーンスターチ、食品用クエン酸などの材料をよく混ぜたあと、食紅で色をつけて視覚的にも楽しく仕上げましょう。
混ぜた生地はスプーン2つで押し固めることで、ちょうどよい形が整います。
半日ほど乾かすとラムネが完成。
食べると口の中でしゅわっと発泡し、炭酸の不思議な化学反応を体感できます。
レモン汁の酸と重曹の反応で発生する炭酸ガスを活用した自由研究で、子供でも安心して取り組める内容です。
色や味を変えてアレンジすることで、オリジナル性を高められます。
身近な材料で化学を学べるアイデアです。
カヌレを作りながら砂糖の結晶化を学ぼう
スイーツのカヌレ型を使って、実験も兼ねた作品を作ってみましょう。
水を入れた容器に粉ゼラチンを入れて、レンジで加熱。
加熱したら、砂糖を入れて食用の着色料で色を付けてレンジで加熱します。
カヌレ型に流して、固まったら型から出しますよ。
砂糖のきれいなカラフルカヌレの出来上がりです。
このときは、プルプルとした見た目ですが一週間すると、砂糖の結晶化によりキラキラした結晶のようになっています。
砂糖の変化も楽しめますよ。
キウイでハムがとける実験
キウイフルーツとハムを使った不思議で面白い自由研究を紹介します。
キウイフルーツ、ハム、紙、フェルトペンを準備して始めていきましょう。
半分に切ったハムの上にカットしたキウイフルーツを置きましょう。
この時に時間を測ることでキウイフルーツを何分置くとハムが溶け出すのかを知れます。
時間の経過を観察しながら写真に記録していくとより深みが出る自由研究になりますね。
キウイフルーツを加熱したものと加熱していないものと分けて実験すると新しい発見が生まれるかもしれませんよ。
実験の目的や結果も書いて夏の自由研究を完成させましょう。
金平糖作り
カラフルでかわいい見た目が魅力の金平糖を夏休みの自由研究に手作りしてみましょう。
砂糖と水を煮詰めて蜜を作り、そこに少量ずつ金平糖の芯を加えていくことで徐々に表面に突起ができていきます。
作業の途中で食用色素や香りを加えれば、好みの味や色にアレンジすることも可能です。
専用の機械がなくても、フライパンやボウルを使って工夫しながらかき混ぜ続けることで、時間はかかりますが少しずつ金平糖らしい形になっていきます。
糖が固まる温度や時間、混ぜ方の違いによって仕上がりが変化するため、理科の実験としても楽しめるでしょう。
お菓子づくりと観察力の両方を育てられる、達成感のあるアイデアです。
3分で凍るアイス

短時間でひんやり美味しいアイスを作る自由研究です。
生クリームとチョコレートソース、チョコチップをジッパー付きの袋に入れてしっかり閉じたら、もう1つの大きな袋に氷と塩を入れたものと一緒に入れます。
塩が加わることで氷の温度が下がり、袋の中のクリームを一気に凍らせる仕組みです。
タオルでくるんでよく振ると、3分ほどでアイスが完成。
チョコの粒感も楽しく、味も満足のいく出来上がりです。
科学的には、塩が氷の融点を下げて吸熱反応を起こし、そのエネルギーで中身が凍る現象がポイントです。
冷たさと化学の関係を体験できる、おいしさも学びも詰まったアイデアです。
先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア(21〜30)
レインボーポンチの作り方

色と状態変化を学べる自由研究にぴったりなレインボーポンチ。
かき氷シロップをいくつかのカップに分けて使い、好きな色をそれぞれ混ぜます。
ゼラチンをお湯に溶かして各色のシロップと混ぜ合わせたら、冷蔵庫で冷やしてゼリーに固めましょう。
できあがったカラフルなゼリーをグラスに入れ、最後に炭酸水を注ぐとしゅわしゅわとした泡と共に虹色のドリンクが完成。
ゼラチンが液体から固体に変わる様子や炭酸水との相性を観察することで、色彩や温度状態変化に関する理解が深まります。
見た目にも楽しめて科学的な要素も盛り込める、観察と実験の両方を味わえるアイデアです。