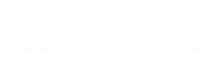先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア
理科の自主学習は、子供たちにとって楽しい冒険にもなります!
こちらでは4年生にオススメの、先生に褒められそうな自学理科のテーマを紹介します。
自由に調べてみると、学ぶことがもっと楽しくなりますよ。
身近な自然を観察したり、簡単な実験をしてみたりして、いろいろなことを発見する喜びを味わってください。
自然や科学に対する興味が育って、自分が学んだことを友達や家族に話せることも楽しいですよ。
ぜひ、こちらを参考にして、一緒に楽しい理科の世界に飛び込んでみてくださいね!
先生に褒められる自主学習!4年生にオススメの自学理科のアイデア(1〜10)
スケルトン卵

卵をお酢につけることで透明に変化していく様子が楽しめる実験です。
水で洗った卵をコップに入れて、卵が浸かる高さまでお酢を入れてキッチンペーパーでフタするだけで作業は完了。
2日間ほど時間をかけて置いておくと、少しずつ卵が透明になっていきます。
酸性のお酢が卵の殻のカルシウムを溶かすことが変化の理由。
シュワシュワと泡が出るのは二酸化炭素が発生しているからで、透明のたまごが大きくなるのは皮の小さな穴から水の分子が入るからです。
実験で作成した卵は食べないように気を付けましょう。
写真やイラスト、文章で記録を残せる自由研究にぴったりなテーマです。
お金について調べてみよう!

小学校4年生ともなると、おこづかいなどで欲しい物を買ったり、おつかいを頼まれて買い物に行ったりと、お金を使う頻度も上がってきますよね。
普段は何も思わずに手にしているお金を、自由研究のテーマとして扱ってみるのはどうでしょうか?
お金の歴史をたどって、大昔から今までの使われ方やお金自体の形の変化などをまとめてみたり、お札に印刷される歴史上の人物のまとめを作ってみましょう。
その他、お札の製造工程、お金の偽造防止のためにおこなわれていることなども盛り込んでみては?
カラフルフラワー作り

さまざまな色のインクに花をつけるとどうなるのかが学べるカラフルフラワー作り。
花の特徴を生かした実験を通して、楽しみながら知識が深まる研究です。
試験管やプラコップなどにプリンターのインクや水に溶かした食紅を入れていきます。
あとは、白いバラやガーベラ、カスミソウなどの花をつけて1〜24時間つけておくだけで完成。
茎を2つに割った花をつけてツートンカラーの花を作ってみるのもオススメですよ。
植物の道管という管から水を吸い上げることで色素を運ぶことが分かる実験です。
ソロキャンプ体験

豊かな自然にかこまれて1人で過ごす貴重な体験ができるソロキャンプをテーマにした自由研究のアイデアです。
キャンプの準備や移動、食事などを1人でおこなう体験をすることで、子供たちに非日常の体験や達成感を与えられます。
実際には1人で泊まるのではなく、遠くから保護者の方が見守ったり動画の撮影者として参加しましょう。
サイクリングや電車などでキャンプ場に向かい、到着したら1人用のテントを作成します。
焚き火台や枯れ枝、木炭を用意したものに引火したら、固形燃料でお米を炊いたりレトルト食品を温められますよ。
夜は寝袋に入って眠り、朝を迎えることで一泊二日の宿泊が体験できるプログラムです。
ピンホールカメラ

自由研究の定番の一つでもあるピンホールカメラを作ってみましょう。
ピンホールカメラとは、カメラレンズの代わりに小さな針穴を用いて像を写すカメラのことで、牛乳パックで作る方法や紙コップで作る方法などがあり、意外にも簡単に作れるんです。
自由研究でピンホールカメラに取り組む場合は、ピンホールカメラを作ったあとに実際にどのように像が写し出されるのかを観察し、なぜそのように写るのかを考察してレポートにまとめるといいでしょう。
プランクトン観察

プランクトンの観察は、身近な自然を深く探求できる自由研究テーマです。
顕微鏡で小さな生き物たちの世界をのぞき込むことは、子供たちの好奇心を刺激するとともに、生物に関する興味が深まるきっかけになるでしょう。
池や川などで水をすくって容器に入れておき、採取した水をスポイトでプレパラートに落として顕微鏡で観察します。
プランクトンの形や動きをイラストや文章で記録しておき、図鑑やインターネットで名前や特徴を調べることで生きものに関する興味を深められますよ。
授業で理科の実験を行う小学校5年生にオススメしたい自由研究のテーマの一つです。
ロックキャンディ

ゴツゴツとした見た目が印象的なロックキャンディを作り、その仕組みについても知っていく研究です。
完成した後にはおやつとして食べられるので、期待感を持ちつつ楽しい気持ちで研究を進められますね。
手順は簡単で、砂糖水をトロトロになるまで煮詰めてスティックにかけ、そのスティックを着色した砂糖水に着けておきます。
するとスティックのまわりに大きな結晶が出現、ある程度の大きさになれば完成です。
砂糖の結晶ができあがるまでの時間、使った砂糖の量による大きさの違いなども意識して観察していきましょう。