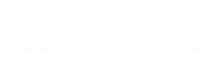小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
6年生の自主学習と言われると、何をしてよいか迷ってしまうこともありますよね。
まずは、自分が興味を持っていることを見つけてみましょう。
好きなことを学ぶと、楽しく続けられますよ。
こちらでは、毎日少しずつ学ぶことで、驚くような発見ができる簡単な自主学習のネタを集めてみました。
資料や本、動画など、いろんな方法を使ってみてくださいね。
友達や家族と一緒に学ぶと、より楽しめますよ。
学ぶことで新しい世界が広がって、新しい発見を生み出してくれることもあります。
今までの興味をいかして、楽しい自主学習に取り組んでみてくださいね。
小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集(1〜10)
手作り花火

夏といえば花火は欠かせないイベントですよね。
市販されているものを購入するイメージが強いそんな花火を自作してみるのはいかがでしょうか。
作っていくのは線香花火で、火薬の素である酸化剤や燃焼剤、閃光剤を混ぜ合わせて、紙に巻いていくという内容ですね。
パチパチとはじけるように燃えるので、安全面には注意しつつ、より長持ちする量や巻き方などを試していきましょう。
火薬の乗せ方によっては燃え方にもムラが出るので、集中して作業に挑むことも重要なポイントですよ。
【オーブン粘土】縄文土器を作ろう

縄文時代の人が料理などに使っていたといわれる縄文土器、独特な形が模様も印象的ですよね。
そんな縄文土器を粘土で作っていく、歴史の勉強にもなりそうな工作です。
使用するのは100円均一でも手に入るオーブン粘土で、ちぎった粘土を継ぎ足すような手順でオーブンに入るサイズの土器を作っていきます。
中心の筒を作り、そこに模様のパーツを貼り付けていくのがオススメで、継ぎ目をなめらかにして一体感もしっかりと出していきましょう。
教科書なども参考にしつつ、オリジナルの模様に挑戦してみるのもおもしろそうですね。
てこを利用した道具を見つけよう

弱い力で重たいものを動かせるてこの原理、理科の授業で聞いたことのある名前ですよね。
そんなてこの原理がどのようなものかを理解し、それが使われている道具について調べていきましょう。
仕組みを深く考えずに何気なく使っていた道具など、知らてみると意外な発見があるかもしれませんよ。
支点と力点、作用点がてこの原理を考えるうえでは重要なポイントなので、どの部分がそれにあたるのかもあわせて考えていくのがオススメですよ。
ソロキャンプ体験

豊かな自然にかこまれて1人で過ごす貴重な体験ができるソロキャンプをテーマにした自由研究のアイデアです。
キャンプの準備や移動、食事などを1人でおこなう体験をすることで、子供たちに非日常の体験や達成感を与えられます。
実際には1人で泊まるのではなく、遠くから保護者の方が見守ったり動画の撮影者として参加しましょう。
サイクリングや電車などでキャンプ場に向かい、到着したら1人用のテントを作成します。
焚き火台や枯れ枝、木炭を用意したものに引火したら、固形燃料でお米を炊いたりレトルト食品を温められますよ。
夜は寝袋に入って眠り、朝を迎えることで一泊二日の宿泊が体験できるプログラムです。
ダンゴムシ迷路

どうなるのか興味をそそられる、ダンゴムシ迷路のアイデアです。
その内容は段ボールで作った迷路にダンゴムシを入れて歩かせるというもの。
するとダンゴムシは、右、左、右、左と規則性を持って迷路を進んでいくはずです。
実はこれ、交替性転向反応という習性によるものです。
どうしてそんな習性が備わっているのか、考えたり調べたりしてみてくださいね。
ちなみに、同じ実験に使える虫にはミミズがいます。
セットで試してみるのもよいでしょう。
プランクトン観察

プランクトンの観察は、身近な自然を深く探求できる自由研究テーマです。
顕微鏡で小さな生き物たちの世界をのぞき込むことは、子供たちの好奇心を刺激するとともに、生物に関する興味が深まるきっかけになるでしょう。
池や川などで水をすくって容器に入れておき、採取した水をスポイトでプレパラートに落として顕微鏡で観察します。
プランクトンの形や動きをイラストや文章で記録しておき、図鑑やインターネットで名前や特徴を調べることで生きものに関する興味を深められますよ。
授業で理科の実験を行う小学校5年生にオススメしたい自由研究のテーマの一つです。
手作りクレーンゲーム

お菓子やぬいぐるみ、フィギュアなどを取るクレーンゲームは子供たちから人気を集めていますね。
「この景品はこのアームの動きで取れるかな……」というドキドキが家でも楽しめる装置を自作してみましょう。
段ボールや空き箱を使って本体を作ります。
次に、ストローや割り箸でクレーンアームを作り、糸でつなげて動かせるように工夫しましょう。
景品は、小さなオモチャやお菓子など、好きなものを用意しましょう。
クレーンゲームの仕組みを調べながら作ることで、工作の楽しさに気づくきっかけにもなります。
製作過程だけでなく、完成したゲームで遊んで楽しめる自由研究のアイデアです。