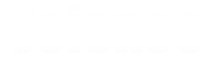小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
6年生の自主学習と言われると、何をしてよいか迷ってしまうこともありますよね。
まずは、自分が興味を持っていることを見つけてみましょう。
好きなことを学ぶと、楽しく続けられますよ。
こちらでは、毎日少しずつ学ぶことで、驚くような発見ができる簡単な自主学習のネタを集めてみました。
資料や本、動画など、いろんな方法を使ってみてくださいね。
友達や家族と一緒に学ぶと、より楽しめますよ。
学ぶことで新しい世界が広がって、新しい発見を生み出してくれることもあります。
今までの興味をいかして、楽しい自主学習に取り組んでみてくださいね。
- 小学5年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集
- 小学3年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 【小学6年生向け】人とかぶらない!楽しい自由研究のアイデア集
- 先生に褒められる自主学習!6年生にオススメの自学理科のアイデア
- 小学4年生にオススメ!簡単にチャレンジできる自主学習のネタ特集
- 小学生にオススメ!6年生向けの作って楽しい工作アイデア集
- 先生に褒められる自主学習!5年生にオススメの自学理科のアイデア
- 小学校5年生にオススメの自由研究まとめ【小学生】
- 小学3年生が夢中になる!身近な材料で作る自由研究のアイデア集
- 先生に褒められる自主学習!3年生にオススメの自学理科のアイデア
- 【小学4年生】身近な材料でできる!楽しい自由研究のアイデア集
- 小学生におすすめ!自由研究テーマ&工作アイデア
- 【小学2年生向け】身近な材料で作る!夢中になる自由研究のアイデア
小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集(51〜60)
俳句を作る3つのステップ

俳句甲子園の実行委員から学ぶ!
俳句を作る3つのステップのアイデアをご紹介しますね。
俳句を作ってみたいけど、どのような工程で作っていけば良いのか分からないという方や俳句の作り方を知りたいと思っている方も、多いのではないでしょうか?
そんな時に活用したい、俳句を作る3つのステップのアイデアです。
動画の中では、俳句甲子園の実行委員会の方から、わかりやすく丁寧にポイントを学べますよ!
ぜひ、取り組んでみてくださいね。
俳句を楽しく読んでみよう

全編手話で学ぶ!
俳句を楽しく読んでみようのアイデアをご紹介しますね。
日常的に手話を活用する人や手話を学んでいる最中という方にオススメしたいアイデアです。
動画の中では、江戸時代の俳諧三大巨匠の1人といわれる小林一茶の俳句を紹介しながら、季語について学べる内容となっていますね。
手話で俳句をどのように表現するのか知りたいという方は、学びを深められるのではないでしょうか?
ぜひ、この機会に取り入れてみてくださいね。
子供の言葉が俳句になる

素直な気持ちを書き留めましょう!
子供の言葉が俳句になるアイデアをご紹介しますね。
子供の言葉にはウソや建前がなく、素直な感情を表現していることが多いですよね。
保護者の方と一緒に取り組めるユニークなアイデアなので、ぜひチャレンジしてみてください。
日常生活やお出かけ先での子供の発言を覚えているという保護者の方も多いのではないでしょうか?
その言葉をそのまま活用して、俳句にしてみましょう。
子供と保護者の方で一緒に詠む素晴らしいアイデアです。
小学生でも使いやすい夏の季語10選

イメージをつかみやすい!
小学生でも使いやすい夏の季語10選のアイデアをご紹介しますね。
俳句には季語を使うというルールがありますが「そもそも季語は何を使えば良いのか想像できない」「季語の例があると、俳句を作りやすい」という方も多いのではないでしょうか?
そんな時に活用したい、小学生でも使いやすい夏の季語10選のアイデアです。
動画の中では、例と一緒に由来も紹介されているので、学びも深められそうですよ!
ぜひ、取り入れてみてくださいね。
小学6年生にオススメ!楽しみながらできる簡単自主学習のネタ特集(61〜70)
振り付き夏の俳句

俳句に興味を持つきっかけになる!
振り付き夏の俳句のアイデアをご紹介しますね。
日常生活の中で、俳句に触れる機会が少ないという方も多いのではないでしょうか?
江戸時代の俳諧の三大巨匠として有名な小林一茶や松尾芭蕉、そして与謝蕪村。
今回は、与謝蕪村が詠んだ有名な俳句を、リズムと振り付けに合わせながら覚えてみましょう!
動画の中では、クイズ形式やアップテンポで詠むなど、アレンジされていますね。
ぜひ、取り組んでみてくださいね。
簡単な俳句の作り方

対話形式の動画で学びましょう!
簡単な俳句の作り方のアイデアをご紹介しますね。
俳句を作るために、どのようなポイントを押さえれば良いのか分からないという方にオススメしたいアイデアです。
動画は、イラストによる対話形式で構成されているので、小学生にとっても見やすいのではないでしょうか?
楽しみながら俳句を詠むために、どのような構成で俳句を作っていくのが良いのか考えるきっかけにもなりそうですよ!
ぜひ、取り入れてみてくださいね。
身近な外来種の調査

小さいころから見慣れている野生の動物や植物、それが実は昔に海外から入ってきてそれが根付いたものだった、といったことがあります。
そんな身近な外来種について調べてみてはどうでしょうか。
それによってどのような影響があったかを、あわせて調べてみるといいでしょう。