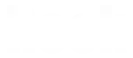【カリスマロックシンガー】清春の魅力と名曲
カリスマ、というとロックでもよく使われる言葉で、日本にもそれに該当する人は数多くいます。
矢沢永吉、氷室京介、YOSHIKI、hide、hyde、吉井和哉、布袋寅泰、大槻ケンヂ、尾崎豊、忌野清志郎……
挙げるとキリがないのですが、どの方も立ち振る舞いや言動一つ一つに強烈な個性があり、今もなお半ば神格化されるような形で熱狂的なファンと圧倒的な支持があります。
私もそんなカリスマに魅せられた人間の1人です。
さて、そんなカリスマと呼ばれる日本のロックアーティストの中で、今回は90年代のビジュアル系シーンから登場し、今なお絶大な影響力を持つボーカリスト「清春」を紹介できればと思います。
そもそも清春ってどういう人なの?
まず、基本的な情報として、清春は現在48歳のシンガーソングライター、ロックボーカリストです。
そして、そのアーティストとしての活動は大まかに分けると、
- 黒夢(1991~1998、2009年、2010年〜現在)
- SADS(1999~2003、2010年〜現在)
- ソロ(2003年~現在)
となります。
ちなみにこの3つは本人が作詞作曲の大半を行っているにもかかわらず、すべて音楽性が異なっています。
黒夢のときはビジュアル系的ないかにもダークな音楽性からJ-POP的な売れ線に行ったり、90年代後期にはパンクに変化したりとアルバムごとに音楽性を変化させていきました。
そして黒夢解活動休止直後に始動したSADSは4年という短い活動期間の間にロックンロール→グラムロック→ヘヴィロックとこちらもめまぐるしい変化を見せました。
かと思うとSADSも活動休止し、ソロでは一転してメロウなナンバーや歌もの路線になり、再始動後の黒夢とSADSはどちらともヘヴィロックに傾倒していきました。
歌詞も耽美(たんび)退廃的なものからパンクらしい社会への敵対心をむき出しにしたもの、そして一転してソロでは叙情的な歌詞へと変化していきました。
清春のビジュアルなんかもすさまじく変化していて、黒夢だけ例にとっても
中央、初期
後期
再始動時
と、この変わりようです。
ここにソロやらSADSを加えるともっとコロコロ変わっています。
ここまで見た人は「果たしてこれでファンがついてくるのか?
」と疑問を持つでしょう。
それがファンがつくんですよね。
なぜこれほど目まぐるしく変わっていくのにファンがつくのか?
カリスマとなれたのか?
これからそこを掘り下げようと思います。
カリスマって何なのか
それほどまでの変遷にかかわらず、ファンがついてくるというのはやはり魅力、そしてカリスマ性があるからにほかなりません。
ファンである僕が思うに清春のカリスマ性を2つの面から紐解きたいと思います。
まず、歌の面からなのですが、清春の歌い方には非常に特徴があります。
黒夢のデビュー時の邦楽ロック界というのは、「声をかすれさせ力強く歌う」という男らしい歌い方が主流でしたが、彼は繊細な歌声にファルセットやビブラートを多用し、要所要所で効果的にシャウトをするというそれまでのロックではありえないものでした。
個別の要素だけ拾うと彼自身もDEAD ENDのボーカルMORRIE(清春の尊敬するボーカリストの1人)に影響された歌い方ではあったのですが、それを独自なオリジナルに昇華したものでした。
その歌い方は現在のビジュアル系の歌い方の基礎となり、どのボーカルも清春の何らかの影響を確実に受けています。
ジャンルを作り上げるほどのインパクトが有ったのです。
さらに、歌い方が非常に個性的であるがゆえ歌ったカバーですら自分の曲にできる、というところがあります。
今までに、
- hide「Beauty&Stupid」
- BUCK-TICK「JUST ONE MORE KISS」
- ストリート・スライダーズ「Let’s go down the street」
- T-REX「20th Century Boy」
などのいわゆるロック系の歌から、
- 布施明「シクラメンのかほり」
- さだまさし「防人の詩」
- 中森明菜「TATTOO」
- 村下孝蔵「初恋」……(他にもたくさん有ると思いますが)
といった歌謡曲まで幅広くカバーしてきました。
そしてそのどれもが、単なるカバーを超えてもはや清春の曲のようにしか聞こえないのはファンである僕も非常に驚くばかりです。
彼の歌というのはそれほどまでに強い個性を持ったものなのです。
そしてライブですが、ファッションセンスも抜群、キメるところはキメるし、大口も叩くし、まさにロックというものの魅力を凝縮したようなパフォーマンスを同時に見せてくれるということも大きな魅力の1つです。
今のロックバンドにはなかなかいないタイプの人です。
もう1つの面として、結構めちゃくちゃな行動や言動があります。
例を挙げると
- 首吊りパフォーマンスでの失神
- 嫌いなアーティストや所属レコード会社を曲中で痛烈に批判する
- 1年間に131本のライブを行う(3日に1本以上)。
- 事務所も立ち上げ社長になる
- 9時間、69曲のライブを行う
- 化粧をやめたかと思えば、またやりだす
- フォロワーを否定したり、今度は肯定したりする
- クロムハーツを愛用し若者のファッションリーダーになる
- バーやファッションブランドを経営する
- 黒夢の無期限休止→10年後解散ライブ→その1年後に再結成
などなど……もはや自分でも何を書いているのかわかりません。
本当にめちゃくちゃなんです。
音楽であっても音楽でなくてもやるし、無謀で危険なことするかと思えば事務所経営というシビアで合理的、そんなビジネスなこともやるのです。
発言もコロコロ変わります。
そう、いわゆる厨二病的なところを持ち続けているのです。
ここまで書くと、一見それがマイナス要素になるのかと思われますが、それが先程の音楽そのものの魅力や実力でねじ伏せてしまう。
むしろプラスに転化してしまう、しかし、どちらがかけても成り立たないのです。
僕はまさしくそれがロックバンドのフロントマンの体現であり、その全てがカリスマにつながるのだなと思いました。
つまり、カリスマとは、決して言動や音楽など個別で図れるものではなく、あらゆる面で、規格外であること。
自分に絶対の自信を持つこと。
これがさまざまな人をひきつけてやまないカリスマ性のなのでしょう。
そのカリスマ性の証拠に、黒夢が2014年に出した「黒と影」というアルバムの特典映像には、hyde(L’Arc~en~Ciel)、INORAN、SUGIZO(ともにLUNA SEA)、高野哲(ZIGZO)、Masato、Katsuma(ともにcoldrain)、MORRIE(DEAD END)、有村竜太朗(Plastic Tree)、MIYAVI、葉月(lynch.)、西川貴教、RUKI(the Gazette)、マオ(シド)などジャンルも年代も違うそうそすたるメンバーが各々の言葉で清春の魅力を語っています。
凡庸な結論に思えますがここまでできているロックアーティストが今どれほどいるのでしょうか?
等身大や聴きやすさ、ライブでの盛り上がりが重視される今のロックシーンですが、こういった善悪を超えた、言葉で表せないものを清春から学ぶことができるのではないかと僕は感じました。
おすすめ楽曲のレビュー
清春のカリスマ性は百も承知ですが、楽曲そのものも魅力的です。
名義や時期によってかなり異なるのでピックアップしていくつか紹介したいと思います。
1. 黒夢
清春の最初のバンドである黒夢は、音楽性を非常に変化させていきました。
for dear
黒夢のデビューシングルで1994年のアルバム「迷える百合達~Romance of Scarlet~」に収録されています。
清春のビジュアル系全開のメイク、耽美的で退廃的な歌詞、そしてしゃくりあげる、ビブラートを効かせた繊細かつ個性的な歌声はすでにこの時から確立されています。
Miss Moonlight
黒夢が初めてオリコン1位を獲得した1995年のアルバム「feminism」に収録されています。
このアルバムの曲は非常にポップなものが多いのですが、こちらも例外ではなく、切なさとビジュアル系的耽美さを味付けられていますが、極めて王道のポップスでビジュアル系になじみのない人でも非常に聞きやすい曲になっています。
Like @ Angel
https://www.youtube.com/watch?v=gqyF7d4-vnU
黒夢のライブの定番とも言える曲で1997年のアルバム「Drug TReatment」に収録されています。
イントロのドラムの入りから、サビに至るまでシンプルに無駄なく展開され、歌詞の焦燥感と清春の歌い方、ハードコア・パンクの要素を打ち出し始めた黒夢のすべての要素が奇跡的に合致した曲です。
ポップでありながら反骨精神を持ちハードコアパンクの要素を持つという曲をこれ以外に僕は聞いたことがありません。
ゲルニカ
2010年に再始動した黒夢が2014年に発売したアルバム「黒と影」に収録されています。
再始動した黒夢の音楽性は90年代後期のパンク路線の延長ではなく、デジロック路線、そして今作のヘヴィロック路線に変わっていきました。
さらに歌唱技術の向上とSADS、ソロをへて清春の歌詞が反骨から抽象的かつ詩的への表現に変化、楽器隊がいわゆる重い音であることから、全体的に今までの黒夢とはまた違う深みのある世界を見せてくれています。
SADS
黒夢活動休止直後に始動したバンドです。
その音楽性は黒夢ほど目まぐるしくはないにしろ、変化が大きいです。
またこの頃の清春は非常に荒れていて、メンバーやライブのできに不満があったことがDVDやSADS活動休止後のインタビューで伺えます。
TOKYO
1999年のアルバム「SAD BLOOD ROCK’N’ROLL」に収録された初期のSADSを代表する曲です。
黒夢の活動休止直後にリリースされた本作はある意味黒夢で突き詰めていたシンプルでパンキッシュな路線をより磨き上げたものでした。
どこか社会風刺的でありながら前のバンドのことを明らかに匂わせる歌詞とシンプルなベース、ドラム、ギターのフレーズが非常にスリリングでまさに当時の清春らしさに溢れたナンバーです。
Masquerade
2003年にリリースされたベストアルバム「GREATEST HITS ~BEST OF 5 YEARS~」に収録されています。
本作を最後に清春はSADSを活動休止し、ソロ活動に移りました。
SADSの音楽性は相次ぐメンバーチェンジとともに初期から大きく変化し、本作はソロ以降のメロウな部分と当時のSADSのハードな路線がうまくハマった曲になりました。
清春がギターを持ち始めたのもこの頃で、その姿も恐ろしく様になっています。
DISCO
2010年に清春以外新メンバーで新しく生まれ変わったSADSはヘヴィメタルといっていいほどの音楽性に変化しています。
楽器隊全員が非常に高い技量を持っています。
2010年のアルバム「Lesson2」に収録されているのですが、ザクザク刻む7弦ギターとどこかPANTERAを髣髴(ほうふつ)とさせるような重いドラムが、ヘヴィロック色を強く0醸し出しています。
活動休止前のSADSとは完全に別物ですが、清春の持つカリスマ性と攻撃性は健在です。
ソロ
SADS活動休止後にはじめたソロ活動ですが、今ではこちらが一番長いです。
その音楽性はアコースティックなものからロック調までさまざまですが、黒夢やSADSのときとは違って、反骨精神を押し出すことはほぼなく、人生や愛、死を意識し成熟した大人の音楽に仕上がっています。
Slow
2006年のアルバム「VINNYBEACH 〜架空の海岸〜」からシングルカットされた曲で、個人的には彼のキャリアの中で屈指のバラードだと思っています。
誰かを想うということを詩的に、しかし感情を込めて高らかに歌うその姿には反骨精神をむき出しにしていた後期黒夢、SADS時代からは想像もつかない姿です。
バンドサウンドも非常にしっとりとしていて、清春というアーティストの内面の変化というものを如実に感じ取ることのできる1曲に仕上がっています。
ナザリー
2016年のアルバム「SOLOIST」に収録されたナンバーです。
このアルバムは清春というアーティストの今を物語る作品で、アップテンポの曲は少なく、ギラついたロックシンガーという雰囲気はあまりしないです。
かつて自分の歌詞を「歌詞の中に絶対的に相手がいる」と語った清春ですが、歳を重ねるごとにその傾向は強まっている気がします。
非常に不思議な言葉の並べ方をしていて、それがまた魅力につながっている1曲です。
the SUN
イントロのギターが非常に格好いいナンバーで2012年のアルバム「UNDER THE SUN」に収録されています。
今の清春がグラムロック的なことをやるとこうなるのか、と魅せてくれるナンバーで妖艶で大人なロックというものを身をもって示してくれています。
この曲、PVが非常に格好良く、女性のリズム隊はもちろん、ギターはあのLUNA SEAのINORANがPV上で共演しており、そのあまりのオーラに90年代のビジュアル系にどっぷりつかっていた私には本当にたまらない映像に仕上がっています。
清春の活動はロックバンドからより成熟したそろのシンガーへと変わっていきましたが、その活動スタイルは若いファンがどうしても中心のビジュアル系、というジャンルにおいてどのように活動を続けていくのかという1つのモデルケースになっているような気がします。
思えば「ロックとはスリリングでありそれでいて非常にグラマラスなもの」そう私に教えてくれたのは清春の存在が大きかったと思います。
始めて知ったときから今まで清春という存在はカリスマとして私の中に君臨し続けるのでしょう。