AI レビュー検索
デール・カーネギー の検索結果(201〜210)
He who would learn to fly one day must first learn to stand and walk and run and climb and dance; one cannot fly into flying.ニーチェ
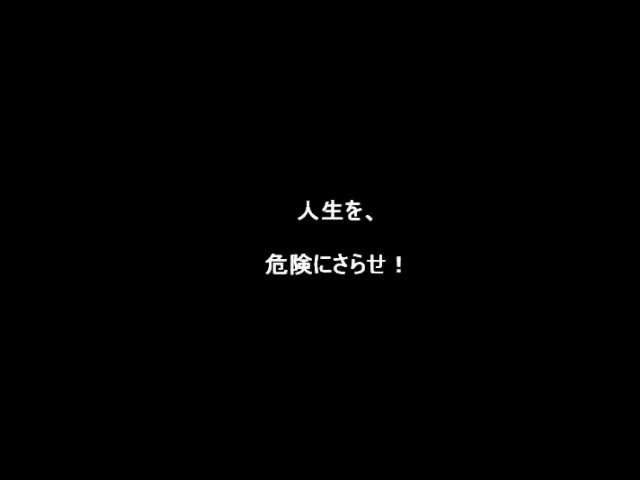
ドイツの哲学者、古典文献学者。
現代では実存主義の代表的な思想家の一人として知られています。
「いつか空の飛び方を知りたいと思っている者は、まず立ちあがり、歩き、走り、登り、踊ることを学ばなければならない。
その過程を飛ばして、飛ぶことはできないのだ」という意味です。
目標に向かって少しずつ進んでいくことの大切さを感じます。
明日死ぬかのように生きよ。永遠に生きるかのように学べ。ガンジー

1日1日を無駄にはできないという気持ちになるこの言葉は、時間を大切に過ごすことができそうですね。
もしも明日自分が死ぬとすればとても充実した日を送ると思います。
後悔しないように人生を生きていこうと思えますね。
Sara SmileDaryl Hall & John Oates
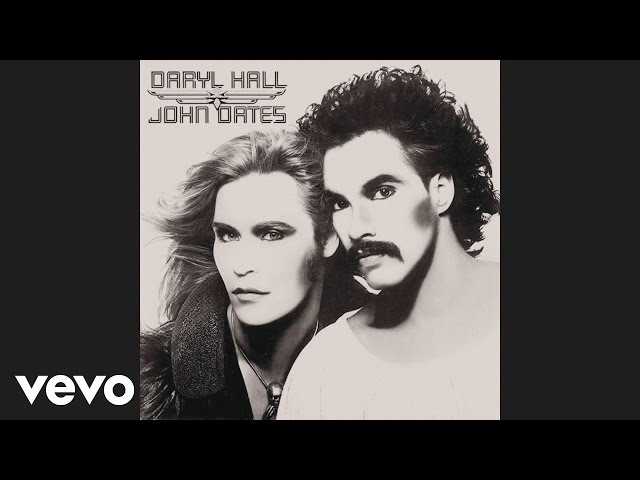
邦題「微笑んでよサラ」。
歌っているダリル・ホール&ジョン・オーツは、アメリカ出身の男性デュオグループで、本作は1976年に全米チャート4位を記録しました。
タイトルにもなっている「サラ」は、ダリル・ホールの当時の恋人のこと。
スローテンポに展開されるバラードソングで、都会的で涼しげな印象を与える楽曲です。
The truth is lived, not taught.ヘルマンヘッセ
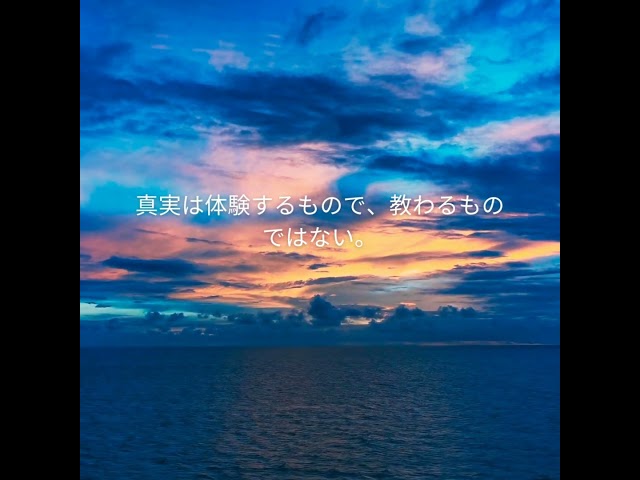
20世紀前半のドイツ文学を代表する文学者としてノーベル文学賞を受賞した小説家、ヘルマン・ヘッセ氏。
日本語で「真実は体験するもので、教わるものではない」という意味の名言は、大切なことは経験からしか分からないと説いていますよね。
現代ではSNSや動画サイトの発展により、自分で見聞きしなくても様々なことを学べます。
しかし、自分にとっての真実は体験してみて初めて分かるものだと気づかせてくれるメッセージなのではないでしょうか。
チャンスをつかむ絶好の日は今日であるジョン・C・マクスウェル
ジョン・C・マクスウェルさんは世界一のメンターとも呼ばれるアメリカの自己啓発作家、牧師であり、たくさんの著書が読まれている人物です。
また彼は「チャンスは幸運ではなく、勇気の成果である」という名言も残しており、その言葉によってチャンスを前にして勇気が出ない友達の背中をそっと押してくれるのではないでしょうか。
昔から「チャンスの女神には後ろ髪がない」ともいいますし、『思い立ったが吉日』といいますもんね。
あなたが今、夢中になっているものを大切にしなさい。ラルフ・ワルド・エマーソン
個人の内側にある力を重視する思想を広め、多くの人々に影響を与えたラルフ・ワルド・エマーソンさん。
彼は超越主義の先駆者として自分を信じ、直感に従うことの大切さを説きました。
代表作『自己信頼』では、他人の評価に左右されず、自分の信じる道を進むことが人生を豊かにすると語っています。
情熱を持って取り組めるものは自分の本質と深く結びついており、それを大切にすることで人生の可能性が広がるのでしょう。
他人の期待や世間の価値観に流されるのではなく、自分が心から没頭できることを見つけ、それに全力を注ぐことが本当の成功につながるのです。
自分の情熱を信じ、夢を追い続ける大切さを教えてくれる名言です。
女性だから無理だと言われるなら、なおさら挑戦する価値がある高市早苗
女性として力強く活躍、トップを目指し続けてきた高市さんの挑戦への思いが感じられる言葉です。
男性が中心で進んできた政治の世界だからこそ、女性というだけでもさまざまな困難があり、だからこそ挑戦に価値があるのだということを伝えています。
性別や立場にとらわれないという平等の姿勢が見えるだけでなく、それまでの慣習を変えていこうという、改革の姿勢も感じられる言葉です。
この道を切り開いていこうとする信念が、どのような結果につながるのかも気になってきますよね。



