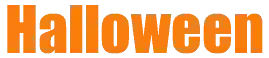【クラシック】ハロウィンにぴったりのオススメのクラシック音楽
肌寒くなったり日没が早くなったりと、冬の気配を感じ始めた頃。
少し怖いけれど楽しいイベント、ハロウィンがありますね。
仮装して非日常を楽しむハロウィンですが、そんな雰囲気をさらに盛り上げるのに効果的なのが音楽です!
その曲を聴いただけで異世界を感じたり、ゾッとしたり、音楽は一気に空間を演出してくれます。
そこで本記事では、そんな音楽の中でもクラシック音楽にしぼり、ハロウィンにぴったりの曲をピックアップしました。
ぜひ音楽とともに、ハロウィンを楽しんでくださいね。
- ハロウィンに聴きたい&弾きたい!オススメのピアノ曲をピックアップ
- ハロウィンが盛り上がる曲。パーティーのBGMにも最適な楽曲を一挙紹介!
- 【昭和×ハロウィン】怖い歌詞や不穏な雰囲気でゾクっとする曲を一挙紹介!
- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介
- 秋におすすめのクラシックの名曲
- かわいいハロウィンソング集!子供も大人も楽しめるキュートな楽曲を厳選
- 【簡単ハロウィン気分】ハロウィンパーティにピッタリなBGM・テーマ曲
- 【パークで流れる】ディズニーハロウィンの名曲・人気曲特集
- 保育のハロウィンが盛り上がる!踊って楽しめるダンスのアイデア
- 令和にリリースされたハロウィンソング|パーティーのBGMにも最適!
- 【芸術の秋】珠玉のピアノ曲とともに|聴いて&弾いて楽しむクラシック
- 背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲
【クラシック】ハロウィンにぴったりのオススメのクラシック音楽(1〜10)
交響的スケルツォ『魔法使いの弟子』Paul Dukas

フランスの作曲家ポール・デュカスさんの代表作である交響詩です。
完璧主義だったデュカスさんは、気に入らなかった作品を生前にことごとく破棄……。
本作はそうして残った数少ない名曲の一つなのだそうです。
デュカスさんの出世作として知られていたこの楽曲は、1940年公開のディズニー映画『ファンタジア』でミッキーマウスが弟子役で登場する物語の音楽に起用され、さらに広く親しまれるようになりました。
見よう見真似の魔法が大混乱を招くスリリングでコミカルな曲調は、ハロウィンのワクワクドキドキする雰囲気にピッタリだと思いませんか?
抒情小曲集 第5集 Op. 54 – 第3曲 小人の行進曲Edvard Grieg

冒頭の忍び寄るような旋律と、どこかユーモラスで軽快なリズムがハロウィンにぴったりの作品が、ノルウェーの作曲家エドワード・グリーグさんのピアノ小品です。
北欧の森にすむ妖精たちの行進を描いた本作は、不協和音が混じるスタッカートが、まるで小人たちのいたずらっぽい足音のように聞こえてきますよね。
中間部で一度、きらめくような美しいメロディに変わりますが、再び騒がしい行進に戻っていくドラマチックな展開も魅力です。
この楽曲は、1891年当時に公開されたピアノ曲集『抒情小曲集 第5集 Op. 54』に収められました。
楽しいけれど少し怖い、そんなハロウィンの雰囲気を演出したいときにぴったりですね!
ピアノで演奏すればパーティーが盛り上がること間違いなしなので、リズムの切れ味と音色の対比を意識して弾いてみましょう。
子供のアルバム Op. 39 – 第20曲 魔女Pyotr Tchaikovsky

なにか悪いことが起こりそうな、不穏な空気が漂うこの作品は、ピョートル・チャイコフスキーが甥にささげたピアノ小品集『Album pour enfants』Op.39の中の一曲です。
この作品集は1878年5月には全曲のスケッチが完成したという、愛情のこもった贈り物なのだそうです。
本作は、速いテンポで駆け抜ける中に、魔女の妖しさとコミカルな恐ろしさが描かれており、まさにハロウィンの雰囲気にぴったりですよね。
この曲を含む作品集は1878年10月に初版が出版されました。
BGMとして楽しむのも良いですが、ピアノで弾けばパーティーが盛り上がること間違いなし。
魔女が飛び回るようなスピード感と歯切れの良さを意識して、ドラマチックに演奏してみてくださいね!
【クラシック】ハロウィンにぴったりのオススメのクラシック音楽(11〜20)
ピアノ練習曲集 第2巻 第13番「悪魔の階段」György Ligeti

終わりなき階段をひたすら駆け上るような、すさまじい緊迫感に満ちた本作は、György Ligetiさんによるピアノ練習曲集の一曲です。
まるで地獄から必死に逃れようともがくかのような、絶え間ない上昇音型が聴く者の心をわしづかみにしますよね。
楽しいだけではない、本物の恐怖でハロウィンの夜を演出したい時にぴったりの作品と言えるでしょう。
この楽曲は、2001年1月に発売されたアルバム『LIGETI, G.: Piano Works – Etudes, Book 2 / Musica Ricercata / 2 Capriccios…』で聴くことができます。
演奏にはきわめて高度な技術と精神力が求められますが、その腕前を披露すれば聴衆を圧倒すること間違いなし。
BGMとして流すだけでも、その場を底知れぬ恐怖で染め上げる強烈なインパクトがありますよ。
交響詩「水の精」 Op. 107Antonín Dvořák

高名な作曲家ブラームスに才能を認められたチェコの名匠、アントニン・ドヴォルザーク。
今回は、ドヴォルザークの晩年の作品群から、民話に基づく交響詩を紹介しましょう。
本作が描くのは、水辺に棲む妖精が少女を水中に引きずり込み、生まれた赤子を惨殺するという非常に恐ろしい物語。
楽しいだけではない、ゾッとするハロウィンの夜を演出したいときにぴったりだと思いませんか?
1896年の作曲当時、一部の批評家から「醜く恐ろしい」とまで評された衝撃的な内容は、今聴いてもスリリングですよね。
チャールズ・マケラス指揮の演奏を収めた名盤『Symphonic Poems』はドイツ・レコード批評賞を受賞しています。
物語を想像しながら聴けば、ハロウィンのムードが深まること間違いなしです。
バレエ音楽「眠りの森の美女」:長靴をはいた猫と白い猫(第3幕)Pyotr Tchaikovsky

ハロウィンのいたずらっぽい雰囲気を盛り上げる、コミカルな一曲はいかがでしょうか。
いくつものバレエ音楽の名作を生んだピョートル・チャイコフスキーが手掛けた、バレエ組曲『眠りの森の美女』に収められている作品です。
本作は、おとぎ話の登場人物である2匹の猫がじゃれ合ったり、威嚇し合ったりする様子を音楽で見事に表現しています。
猫の鳴き声を模したようなフレーズや、俊敏な動きを感じさせるリズムは、まるで仮装したキャラクターが目の前で踊っているかのようで、聴いているだけで楽しくなってきますね。
この楽曲を含むバレエは1890年1月に初演されたもので、結婚式の祝宴という非日常的な舞台設定もハロウィンの雰囲気にぴったりです。
パーティーを彩るBGMとして流せば、不思議で愉快な夜を演出してくれますよ。
森の情景 Op. 82 – 第7曲 予言の鳥Robert Schumann

静寂を切り裂くように響く神秘的な和音から始まるこの楽曲は、楽しいだけではなく、ちょっと怖いハロウィンを演出したいときにぴったりですね。
ロベルト・シューマンといえばドイツ・ロマン派を代表する作曲家ですが、本作はシューマンのピアノ曲のなかでも特に幻想的な魅力を持つ作品です。
精神的に不安定な時期にあった1848年から1849年にかけて作られたピアノ曲集『森の情景 Op. 82』の第7曲で、まるで未来を告げる鳥の不吉な予言を聴いているかのよう。
そのミステリアスな響きは、聴く人を一気に異世界へと誘います。
1850年頃に公開された作品ですが、その詩的な世界観は今なお多くの人の心をとらえ続けています。
静かな秋の夜長に、本作をBGMとして物思いにふけってみてはいかがですか。