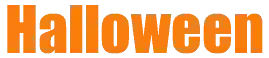【クラシック】ハロウィンにぴったりのオススメのクラシック音楽
肌寒くなったり日没が早くなったりと、冬の気配を感じ始めた頃。
少し怖いけれど楽しいイベント、ハロウィンがありますね。
仮装して非日常を楽しむハロウィンですが、そんな雰囲気をさらに盛り上げるのに効果的なのが音楽です!
その曲を聴いただけで異世界を感じたり、ゾッとしたり、音楽は一気に空間を演出してくれます。
そこで本記事では、そんな音楽の中でもクラシック音楽にしぼり、ハロウィンにぴったりの曲をピックアップしました。
ぜひ音楽とともに、ハロウィンを楽しんでくださいね。
- ハロウィンに聴きたい&弾きたい!オススメのピアノ曲をピックアップ
- ハロウィンが盛り上がる曲。パーティーのBGMにも最適な楽曲を一挙紹介!
- 【昭和×ハロウィン】怖い歌詞や不穏な雰囲気でゾクっとする曲を一挙紹介!
- かっこいいクラシックの名曲。おすすめのクラシック音楽
- バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介
- 秋におすすめのクラシックの名曲
- かわいいハロウィンソング集!子供も大人も楽しめるキュートな楽曲を厳選
- 【簡単ハロウィン気分】ハロウィンパーティにピッタリなBGM・テーマ曲
- 【パークで流れる】ディズニーハロウィンの名曲・人気曲特集
- 保育のハロウィンが盛り上がる!踊って楽しめるダンスのアイデア
- 令和にリリースされたハロウィンソング|パーティーのBGMにも最適!
- 【芸術の秋】珠玉のピアノ曲とともに|聴いて&弾いて楽しむクラシック
- 背筋の凍る怖い歌。恐怖を感じる名曲・不気味なおすすめ曲
【クラシック】ハロウィンにぴったりのオススメのクラシック音楽(21〜30)
レクイエム ニ短調より「怒りの日」Wolfgang Amadeus Mozart

キリスト教の終末思想の一つである「怒りの日」を題材にしたこの曲は、ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルトの遺作として知られています。
迫力ある合唱と緊張感のある弦楽器が特徴で、短調の急速なテンポが不安と恐怖を強調しています。
審判の日の恐ろしさを表現した歌詞と激しく劇的な音楽が見事に融合し、聴く人の心に深い畏怖の念を抱かせます。
1791年に作曲が始められたものの、モーツァルトの死により未完となり、弟子のジュスマイヤーによって完成されました。
映画やテレビ番組でもよく使用され、特に印象的なシーンを演出するのに効果的です。
ハロウィンパーティーの BGM として使えば、一気に異世界観が出ることでしょう。
トッカータとフーガ ニ短調 BWV565J.S.Bach

ヨハン・ゼバスティアン・バッハが作曲したこの作品は、ダイナミックで力強い音楽表現が印象的です。
冒頭のトッカータ部分は、誰もが一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
まるで巨大な扉が開くかのような迫力があり、オルガンの重厚な音色が聴く者を圧倒します。
続くフーガ部分では複雑な旋律が絡み合い、また違った恐怖を感じさせます。
ハロウィンの夜、古城や教会を舞台にした怪奇物語を想像しながら聴くのもオススメ。
不気味さと荘厳さが入り混じる独特な雰囲気を味わってみてくださいね。
ペール・ギュント 第1組曲 作品46より「山の魔王の宮殿にて」Edvard Grieg

エドヴァルド・グリーグ書いた劇付随音楽の一部、『ペール・ギュント』。
そのなかの『山の魔王の宮殿にて』は、北欧の民話的な要素が詰まっています。
トロールの世界の不気味さを表現しており、まるで物語を聴いているよう。
ペール・ギュントという冒険者が、トロールたちに追われる様子を描いており、だんだんとテンポが速まり迫力を増していく展開は聴く人を引き込んでいきます。
1875年に初演されましたが、今でもコンサートの人気プログラムの一つ。
ハロウィンの夜に、不思議な世界へ旅立つ気分で楽しんでみてはいかがでしょうか。
幻想交響曲より第5楽章「魔女の夜宴の夢」Hector Berlioz

エクトル・ベルリオーズが24歳のときに作曲した交響曲の最終楽章。
アヘンの影響下で見る恐ろしい幻覚を描いており、主人公の葬儀に魔女や亡霊、怪物たちが集まる狂乱の宴が繰り広げられます。
不気味で重厚な雰囲気の中、魔物たちの舞踏が描写されるさまは圧巻。
ヴァイオリンの特殊な奏法や重々しい鐘の音が、死と混沌の世界観を見事に表現しています。
ハロウィンパーティー や怖い話をする際の BGM としてぴったり。
ゾクゾクする音楽を楽しみたい方にオススメです。
カルミナ・ブラーナより「おお、運命の女神よ」Carl Orff

運命の無慈悲さを描く楽曲として、カール・オルフの作品が挙げられます。
13世紀の詩に基づき、1935年から1936年に作曲されたこの曲は、運命に翻弄される人々の苦悩を劇的に表現しています。
打楽器と重厚な合唱で始まり、徐々に緊張感を高めてクライマックスに達する曲調が特徴的。
1981年の映画『エクスカリバー』で使用されたことで広く知られるようになり、その後も映画やCMなどで多用されています。
ハロウィンの雰囲気を盛り上げたい方にぴったりの1曲。
異世界を感じさせる音楽とともに、非日常を楽しんでみてはいかがでしょうか。
死の舞踏Franz Liszt

ハロウィンの雰囲気にぴったりの曲をお探しの方に、フランツ・リストさんの作品をご紹介します。
中世の聖歌「怒りの日」を主題にした本作は、1838年に構想され、1849年に完成しました。
ピアノとオーケストラが生み出す壮大な音響が特徴的で、生と死のテーマを掘り下げています。
ピサのカンポサントで見た「死の勝利」というフレスコ画に触発されたという説もあり、その音楽は聴く人の心に強烈な印象を残します。
1865年4月にハーグで初演された本作は、その革新的なスタイルで高く評価されています。
ハロウィンパーティーのBGMとしてはもちろん、ゾクっとする雰囲気を味わいたい方にもおすすめです。
レクイエムより「怒りの日」Giuseppe Verdi

ジュゼッペ・ヴェルディが作曲した壮大な宗教音楽作品『レクイエム』の一部。
キリスト教の終末思想を象徴する「最後の審判の日」を描いた楽曲です。
激しいオーケストラと合唱が特徴的で、冒頭の強烈な管弦楽の打撃音と合唱の叫び声は、恐怖と荘厳さを伴いながら聴衆を圧倒します。
ヴェルディは、オペラ的なリズムと強弱の対比を駆使し、終末の不安と威厳を音楽的に描き出しました。
1874年5月にミラノで初演された際には、劇的な表現力と宗教的荘厳さが評価され、今日でも世界中の合唱団やオーケストラによって頻繁に演奏されています。
ハロウィンの雰囲気を盛り上げたい方にオススメですよ。