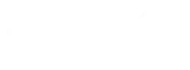【組体操】迫力満点!大人数でおこなう大技を一挙紹介
仲間と一緒に一つの演技を作り出す組体操は、運動会でもひときわ大きな盛り上がりを見せますよね。
なかでも大人数でおこなわれる技は、観客に驚きと感動を与えるとともに、演技をしている側ももっとも達成感を味わえるところではないでしょうか。
そこでこの記事では、5人以上の大人数でできる組体操の技を紹介します。
定番のピラミッドや扇を含め、迫力満点の技を集めました。
ケガには十分に気をつけながら、挑戦してみてくださいね!
- 組体操におすすめの曲。演技を盛り上げる楽曲まとめ【2026】
- 【テンションアップ】かっこいい・おもしろい円陣まとめ
- 運動会・体育祭で盛り上がる曲ランキング【2026】
- 【運動会】マスゲームにぴったりな邦楽人気曲まとめ【体育祭】
- 【体育祭ヘアアレンジ】男ウケ抜群!オススメの髪型をピックアップ
- 【白熱】運動会の騎馬戦BGMにぴったりな曲を厳選!
- 【体育祭におすすめ!】面白いスローガンの例と考え方も紹介
- 【青春ソング】運動会や体育祭を盛り上げる歌。大会の場を彩る曲
- 【本日のおすすめ】高齢者向けのやさしい健康体操
- 【ユニーク】子供も大人も楽しめる運動会のおもしろい種目
- 【青春のドラマを彩る!】運動会・体育祭にピッタリな感動ソング
- 小学生が踊れる!運動会におすすめのダンス曲&振り付け
- ZOOMで大人数でも楽しめるレクリエーション
【組体操】迫力満点!大人数でおこなう大技を一挙紹介(11〜20)
ジャンボジェット
ジャンボジェットという組体操の6人技をご紹介します。
構造はとてもシンプルです。
まず、2人が横並びに馬の形を作ります。
次の2人は翼のイメージで、馬の背中に足を置きます。
最後の2人は手押し車の形をつくって、前の1人が両手を馬の背中についたら完成。
保育園や幼稚園の年長児さんにできるので運動会にもオススメですよ。
シンプルですが、合図に合わせたバランス、素早さ、お友達を落とさない力を考えることがポイントです。
全員でそろえるためには練習が大切ですが、小さな体でも迫力が見せられる大技です。
ぜひ組体操に取り入れてみてくださいね。
ナイアガラの滝
ナイアガラの滝という組体操の技をご紹介します。
大勢で取り組むと大迫力ですが、構造はとてもシンプルです。
2人1組で手押し車の形をつくって、足を持ったら肩に置きます。
横並びに大勢で行えば完成です。
保育園や幼稚園の年長児さんにもできるので運動会にもオススメです。
シンプルですが、大迫力に見せるために、合図に合わせたバランス、素早さ、お友達を落とさない力を考えることがポイントです。
全員でそろえるためには練習が大切ですが、見ている側もビックリの大技になるのでぜひ組体操に取り入れてみてくださいね。
ブロッケン

組体操のクライマックスにオススメな大技が、ブロッケン。
こちらは5人以上でおこなうのにぴったりの技なんです!
下段が四つんばい、中段が下段の人の腰に手をついて中腰になります。
中段の2人がお尻を合わせるように4人を対照的に配置。
その上にさらに1人が立ってポーズする技です。
中段の人は上の人を腰で支えなければならないので、体格の良い人を配置するのがポイント。
土台が安定しており、ピラミッドのように危険度は高くないので、年齢が低いお子さんでも取り組めるのではないでしょうか。
カシオペア
夜空に輝く星座の一つである、カシオペア座をモチーフにした技。
カシオペア座がMやWの形に見えることに由来する技で、上段の2人が下段の3人のひざへ乗り、それを下段がしっかりと支えているような形です。
上段が乗っているだけでもMの形には見えますが、星座を表現するための上段の手の角度を工夫して、形を強調するようなパターンもあるよう。
コンセプトとバランスを考えて通常は5人でおこなう技ではありますが、シンプルな構造なので横に長くつなげていくパターンにアレンジしても盛り上るのではないでしょうか。
九十九折
少人数の組体操にオススメ!
「九十九折」を紹介します。
ポーズがとてもキレイで、その構造美でもアピール力抜群の九十九折。
構造はとてもシンプルで、1人がまず馬の形を作ります。
2人目は、1人目の肩に手を乗せ、3人目は1人目の背中に乗って、2人目の肩に手を乗せます。
最後に2人目と3人目が足をあげれば完成。
少人数でもとても見栄えがする技ですよ。
バランスによって形が変わってしまうので、3人で息を合わせることが必要です。
ぜひ、組体操の技に取り入れてみてくださいね。
琵琶湖大橋
組体操のクライマックスにもオススメ!
「琵琶湖大橋」を紹介します。
大勢で行うので見た目も華やかですよ。
左から右、右から左へと、それぞれの位置で足を支えるのが基本です。
端の人から橋のイメージでつなげていきます。
とても見栄えがする大技ですよ。
バランスによって形が変わってしまうので、真ん中の人たちの位置も大切になってきます。
人数が多い業になるので、全員で息を合わせることが必要です。
人数に合わせて工夫して取り入れてみてくださいね。
【組体操】迫力満点!大人数でおこなう大技を一挙紹介(21〜30)
タワー

タワーは、組体操のプログラムの中でも見せ場として使用されることの多い象徴的な技です。
ピラミッドと同じような、高く積みあがっていくような内容の技ですが、立った状態でおこなうことも多く、高さが出せるところがポイント。
その分バランスがとりづらいことも注意したいポイントで、安全をしっかりと考えた組み方を意識しましょう。
段を重ねることだけが魅力ではなく、2段のタワーであっても高さは伝わるため、配置や組み方を工夫した構成がオススメです。