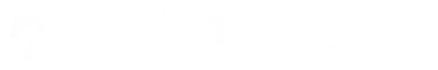7月に関する雑学&豆知識。七夕の雑学も
7月と言えば、七夕に海の日、夏休みの始まり、と楽しみなことがたくさんありますよね。
そんな7月について、あなたはどれぐらい詳しくご存じでしょうか?
この記事では、一般向けの7月に関する雑学&豆知識を紹介します。
七夕に関することはもちろん、7月の記念日や旬のものに関することなど、さまざまな方面から集めてみました。
七夕の知識を深めてもらうためにお子さんにお話したり、夏のレジャーの際にネタにしたり、さまざまな場面で活用してみてくださいね!
- 【子供向け】7月に関する雑学クイズ&豆知識問題
- 【七夕クイズ】豆知識や雑学が楽しめる3択問題
- 【子供向け】夏が楽しくなる雑学クイズ&豆知識問題
- 夏がもっと楽しくなる雑学&豆知識
- 夏祭りがもっと楽しくなる!子供向け雑学クイズ&豆知識問題
- 心が熱くなる8月に関する雑学&豆知識まとめ
- 知っているようで意外に知らない?8月の雑学・豆知識クイズ!
- 夏祭りをもっと楽しもう!雑学クイズ&豆知識問題集
- 夏といえば花火!花火にまつわる子供向けの雑学クイズ&豆知識問題
- 思わず誰かに話したくなる!12月の雑学&豆知識特集
- 【子供向け】6月に関する雑学&豆知識クイズ
- 知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学
- 知ってると役立つ豆知識クイズ。学校や家で活躍する雑学【子供向け】
7月に関する雑学&豆知識。七夕の雑学も(1〜10)
織姫は「ベガ」、彦星は「アルタイル」
織姫はこと座の1等星「ベガ」、彦星はわし座の1等星「アルタイル」であると言われています。
この二つの星のあいだに天の川が流れていますよ。
結婚してから仕事をせず、そのことで天帝の怒りをかい、天の川の両岸に引き離された2人……まさに七夕の伝説通りですね。
実は、この二つの星は距離にして14.4光年離れており、光のスピードで計算しても移動するには14年ほどかかってしまうのだとか。
つまり、本当はどんなにがんばっても1年に一度も会えないということですね……。
浅草寺では7月9,10日にほおずきを売る
7月9日〜10日に、浅草寺では「ほおずき市」が開かれます。
7月10日は一生分の功徳を得られる「四万六千日の縁日」と呼ばれており、江戸時代にはこの日にあやかろうと前日から参拝客で賑わっていたそうです。
そのため、7月9日〜10日の両日が縁日とされているんですね。
ほおずき市が立ったのは、当時ほおずきを水で丸のみすることで持病や腹痛が治ると信じられており、求める人が多かったためと言われています。
時期的にお盆も近く、盆棚飾りとして求める方も多いそうですよ。
7月の満月は「バックムーン」という
7月の満月が「バックムーン」と呼ばれているのはご存じでしょうか。
バックムーンという言葉はアメリカ発祥と言われており、バックは鹿の雄を指します。
7月は雄の角が変え変わる時期であることから、バックムーンと呼ばれるようになったそうです。
ちなみに各月の満月にはそれぞれ呼び名があります。
7月の前月である6月は、イチゴの収穫時期であることから「ストロベリームーン」。
翌月の8月は、チョウザメ漁が盛んになることから「スタージョンムーン」と呼ばれていますよ。
7月に関する雑学&豆知識。七夕の雑学も(11〜20)
七夕で食べるものはそうめん
日本にはさまざまな行事があり、各行事にはそのときに食べるといいとされる行事食がありますよね。
七夕の行事食は、そうめんなんです。
七夕は中国から伝わった文化で、当初は米粉と小麦粉を練り上げ縄状にして揚げた、索餅というお菓子が食べられていました。
それが時代とともに形を変え、そうめんになったと言われています。
しかし、行事食がそうめんになった理由には諸説あり、天の川や糸に見立てた、栄養が豊富で健康に良いからといった説もあるそうですよ。
7月の誕生石はルビー
情熱や勝利を象徴するルビーは7月の誕生石です。
深い赤色は生命力や愛情の象徴とされ、持ち主に勇気とエネルギーを与えてくれると信じられています。
災いから身を守る護符として用いられることもあり、大切な人への贈り物としても人気がある石です。
誕生月の宝石を身につけることは自分をより大切にするお守りとしての意味も持ち、日常に特別な意味を添えられます。
華やかな見た目だけでなく、込められた意味を知ることで、その輝きがより価値のあるものに感じられるでしょう。
富士山は7月に山開きされる
日本一の高さを誇る富士山は毎年7月に山開きがおこなわれ、夏の登山シーズンが本格的に始まります。
山梨県側の吉田ルートは7月1日、静岡県側のルートは7月10日頃に開通しており、多くの登山客が全国から訪れるのが特徴です。
7月から8月にかけての短い期間が登頂に最適とされており、この時期には山小屋や救護所も整備されるため安全に登山がしやすくなります。
厳しい自然環境の中で挑む登山には準備と覚悟が必要ですが、山頂からのご来光は格別な体験になるでしょう。
夏の風物詩として毎年注目を集めるイベントです。
笹に短冊を飾るのは笹が神聖なものだから
七夕といえば笹に願いごとの短冊を飾る風習が有名ですが、なぜ笹が使われるのかをご存じでしょうか。
笹は古くから神聖な植物とされてきました。
昔はまっすぐに伸びる姿や青々とした葉が「生命力の象徴」として縁起がよいと考えられていました。
笹の葉には厄を払う力があると信じられ、神様の依代(よりしろ)として用いられてきた歴史もあります。
七夕では、そんな神聖な笹に願いごとを書いた短冊を結びつけることで、願いが天に届けられるでしょう。
単なる飾りではなく心を込めて願いを書くことで、より行事を楽しめるでしょう。