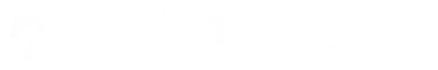7月と言えば、七夕に海の日、夏休みの始まり、と楽しみなことがたくさんありますよね。
そんな7月について、あなたはどれぐらい詳しくご存じでしょうか?
この記事では、一般向けの7月に関する雑学&豆知識を紹介します。
七夕に関することはもちろん、7月の記念日や旬のものに関することなど、さまざまな方面から集めてみました。
七夕の知識を深めてもらうためにお子さんにお話したり、夏のレジャーの際にネタにしたり、さまざまな場面で活用してみてくださいね!
- 【子供向け】7月に関する雑学クイズ&豆知識問題
- 【七夕クイズ】豆知識や雑学が楽しめる3択問題
- 【子供向け】夏が楽しくなる雑学クイズ&豆知識問題
- 夏がもっと楽しくなる雑学&豆知識
- 夏祭りがもっと楽しくなる!子供向け雑学クイズ&豆知識問題
- 心が熱くなる8月に関する雑学&豆知識まとめ
- 知っているようで意外に知らない?8月の雑学・豆知識クイズ!
- 夏祭りをもっと楽しもう!雑学クイズ&豆知識問題集
- 夏といえば花火!花火にまつわる子供向けの雑学クイズ&豆知識問題
- 思わず誰かに話したくなる!12月の雑学&豆知識特集
- 【子供向け】6月に関する雑学&豆知識クイズ
- 知ればもっと5月が好きになる?小学生に知ってほしい5月の雑学
- 知ってると役立つ豆知識クイズ。学校や家で活躍する雑学【子供向け】
7月に関する雑学&豆知識。七夕の雑学も(1〜10)
7月の旧暦は文月
7月は旧暦では文月(ふみづき)と呼ばれていました。
この名称の由来には諸説ありますが、有力とされるのが文(ふみ)=書物や手紙を意味し、七夕にちなんで短冊に願いごとを書いたり、書道に親しんだりする習慣に由来する説です。
昔の人々は書に気持ちを込めて神さまや星に願いを届けようとしたとされ、文字や言葉の力を重んじていたことがうかがえます。
文月という響きには知的で情緒のある季節の気配が感じられ、現代にも通じる言葉の魅力が伝わるでしょう。
七夕は江戸時代では祝日だった
七夕は、江戸時代では祝日でした。
現代とは違い、江戸時代の人にとって祝日は仕事や生活から離れて過ごす特別な行事の日だったと言われています。
七夕も昔の人にとっては織姫さまと彦星さまが1年に一度会える特別な日であり、夏を健康に過ごせますようにと願った日でもあると言われています。
今は短冊にお願いごとを書いたりして七夕を楽しむ傾向が強いですが、昔は行事としてお休みし、お祝していた特別な日だったそう。
昔も今も大切にされてる七夕をこれからも大切にしていきたいですね。
7月25日はかき氷の日
7月25日はかき氷の日とされています。
この日はかき氷の昔の呼び名である夏氷(なつごおり)の語呂合わせ7(な)2(つ)5(ごおり)から決められました。
1933年のこの日、山形市で日本最高気温の40.8度が記録されたことも由来のひとつです。
夏の暑さに欠かせない涼の象徴として、かき氷は昔から愛されてきました。
今では定番のいちごやメロンのほか抹茶やマンゴーなど多彩なフレーバーが登場し、見た目も味も進化しています。
記念日に合わせて食べることで、季節感をより味わえる1日になります。
夏の風物詩にまつわるこの日を知ることで、涼を取る時間が少し特別なものになるかもしれませんね。
7月から旬を迎える冬瓜は冬までもつから名前に「冬」が入る
「冬瓜」という漢字で見れば、誰もが冬の野菜なのだろうと思いますよね。
しかし、冬瓜は7月、夏に旬を迎える野菜なんです。
では、どうして名前にあえて「冬」が入っているのか。
その理由は、冬瓜のもちの良さにあります。
冬瓜は皮が分厚いため、保存性に優れており、きちんと冷所で保管しておけば冬までもつのだそうです。
そのことから、夏の野菜なのに「冬瓜」という名前がつけられたんですね。
冬瓜はカリウムやビタミンCが豊富で、高血圧の予防や便秘にも効くとされていますよ。
七夕の短冊が5色なのは中国の陰陽五行説から
七夕の短冊に青、赤、黄、白、黒の色を使うのは、中国の陰陽五行説からと言われています。
地球には陰と陽があり、二つの側面があるそうです。
陰は冷たい、暗いなどの意味で、陽は明るい、温かいなどの意味があります。
陰陽五行説を取り入れることで、七夕の願いごとがかないやすくなると言われています。
七夕の短冊はカラフルで夏を感じられ、ステキだなと思う一方で、それぞれの色にこんな人になりたいなという願いが色に込められていることを知ると、願いごとによって色も選びたくなりますね。
七夕飾りの吹き流しは裁縫の上達を願う飾り
七夕飾りの中でもひときわ華やかさが際立つ七夕飾りの吹き流しは、裁縫の上達を願う飾りとして、紙やビニールで飾られています。
七夕に登場する織姫様と深く関係があり、織姫様は機織りがとっても上手で、吹き流しは織姫様のように裁縫が上手にできますようにという願いが込められて作られたそうです。
吹き流しには、織姫様みたいに手先を器用に動かして作れますように、という願いも込められています。
七夕飾りを作るときにはぜひ、吹き流しの意味を思い出しながら作ってみるのもオススメです。
海の日は明治天皇が無事に船旅から帰ってきたことからできた
7月の祝日である海の日は、夏のレジャーを楽しむ日というイメージが強いかもしれませんが、実は明治時代の出来事に由来しています。
1876年に明治天皇が東北地方を巡幸された際、灯台視察を兼ねて明治丸で函館から横浜へと戻られました。
この航海の無事を祝して海の記念日が制定され、後に海の日として国民の祝日になったのです。
海水浴や旅行の日ではなく海の恩恵に感謝し、海洋国家である日本の発展を願うという意味が込められています。
このような背景を知ることで祝日の意味に深みが増し、自然や歴史への敬意を感じるきっかけになります。
日本ならではの祝日として大切にしたい記念日です。