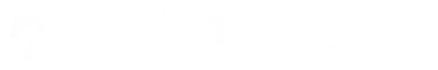お正月クイズで盛り上がろう!日本のお正月に関する一般問題
お正月について、あなたはどれくらい知っていますか?
毎年なんとなく繰り返している習慣も、その背景を知ると「そういう意味があったのか!」と思わず驚いてしまうことがたくさんあります。
そこでこの記事では、お正月にまつわる一般常識や雑学をクイズ形式で紹介!
ポチ袋の意味、おせち料理やお正月遊びに込められた思い、お正月にやってはいけないことなど、知っているようで知らなかった日本の伝統行事の雑学が盛りだくさんですよ。
家族や親せきが集まる場で、楽しみながら挑戦してみてくださいね!
- 【一般】みんなで楽しめるお正月クイズ!意外と知らない豆知識を3択で楽しく学ぼう
- 【一般向け】思わず誰かに話したくなる!1月の雑学&豆知識特集
- 【子供向け】1月の雑学クイズ&豆知識問題。お正月を楽しく学ぼう
- 【一般向け】思わず誰かに話したくなる!12月の雑学&豆知識特集
- 新年会で盛り上がる面白いクイズ。誰もが楽しめる問題集
- 【忘年会や新年会】今年振り返りや、新年に向けた心理テスト
- 【子供向け】12月の雑学クイズ&豆知識問題!行事や季節のことを学べる!
- 【高齢者向け】1月のクイズで脳トレ。お正月や冬の雑学で盛り上がろう
- 【新年会にもピッタリ】1月におすすめな心理テスト
- 【頭脳戦】知的好奇心を刺激!大人の盛り上がるクイズ問題
- みんなで一緒に盛り上がる4択クイズに挑戦しよう!
- 盛り上がるお正月ゲーム。定番から手作りまで楽しいアイデア集
- 【子供向け】今日のクイズまとめ。今日にまつわるクイズで遊ぼう!【2025年12月】
お正月クイズで盛り上がろう!日本のお正月に関する一般問題(11〜20)
鏡餅にみかんをのせる理由とは?
- 厄払い
- 子孫繁栄
- 長寿祈願
こたえを見る
子孫繁栄
鏡餅の上の果物は、実はみかんではなく橙、だいだいと呼ばれる柑橘類です。
木から落ちずに実が大きくなる橙は縁起の良い果物として飾られており、子孫が代々まで繁栄することを願う意味が込められています。
「元旦」とはいつのこと?NEW!
- 1月1日中ずっと
- 1月1~3日
- 1月1日の午前中
こたえを見る
1月1日の午前中
元旦という言葉は元日の朝を指し、厳密には1月1日の午前中を意味します。
よく「元日」と混同されがちですが、「元旦」には朝を表す漢字「旦」が使われているため、本来は日付だけではなく朝の時間帯を指しています。
大晦日に年越しをして迎えた新年の始まり、その一日のうちの朝という特別な時間を大切にした日本の風習が表れています。
おせち料理に入っている伊達巻に込められた意味は?NEW!
- 学業成就
- 商売繁盛
- 恋愛成就
こたえを見る
学業成就
伊達巻は見た目が巻物に似ていることから、昔の書物や巻物にちなんで「学業成就」や「知識が増えるように」という願いが込められています。
特に、勉強や知識の向上、新しいことの学びへの願いを年の初めに込めて食べられています。
そのため、子どもや学生のいる家庭では特に大切にされる一品です。
おせち料理に入っている数の子は何の卵?NEW!
- サケ
- ニシン
- トビウオ
こたえを見る
ニシン
数の子は、ニシンの卵です。
おせち料理に使われる数の子は、子孫繁栄や家族の繁栄を願う縁起物として、日本のお正月には欠かせない食材です。
ニシンは大量に卵を産むことから、その卵である数の子も「子宝に恵まれるように」という意味を込めて食べられています。
プチプチとした食感も特徴的で、古くから日本の伝統的な正月料理として親しまれています。
おせち料理に入っている栗きんとんに込められている意味は?NEW!
- 健康運
- 金運
- 恋愛運
こたえを見る
金運
栗きんとんは、おせち料理の中でも特に人気のある一品で、その鮮やかな黄金色は金塊や財宝を連想させることから「金運アップ」の象徴とされています。
新しい年の始まりに栗きんとんを食べることで、家庭や自分自身にたくさんの豊かさや財産が訪れるように、という願いが込められています。
栗きんとんの鮮やかな色合いが、お祝いの席を華やかにしてくれますね。
おせち料理をお重に詰める理由は何?NEW!
- 洗い物の負担を減らすため
- おすそわけするため
- 福やめでたさが重なるようにとの願い
こたえを見る
福やめでたさが重なるようにとの願い
おせち料理をお重に重ねて詰めるのは、福やめでたさが幾重にも重なって訪れるようにという願いが込められているためです。
日本の伝統的な文化では「重ねる」ことに意味があり、家族の幸せや繁栄が何重にも続くようにとの願いが込められています。
そのため、見た目の美しさや保存のためだけでなく、縁起の良さを大切にした日本らしい風習として受け継がれているのです。
お正月クイズで盛り上がろう!日本のお正月に関する一般問題(21〜30)
おみくじを引いてもいい回数は?NEW!
- 1回
- 3回
- 何回でもOK
こたえを見る
何回でもOK
おみくじは神社やお寺で引く運勢を占う紙ですが、基本的に引く回数に決まりはありません。
一度引いたおみくじの結果が気に入らなかった場合でも、もう一度引いても失礼にはなりません。
ただし、連続して何度も引くことはマナーの面で控えた方がよいとされています。
「おみくじは何回でも良い」というのは、正式なルールがないためです。
大切なのは、結果に一喜一憂しすぎず、前向きな気持ちで新年を迎えることですね。