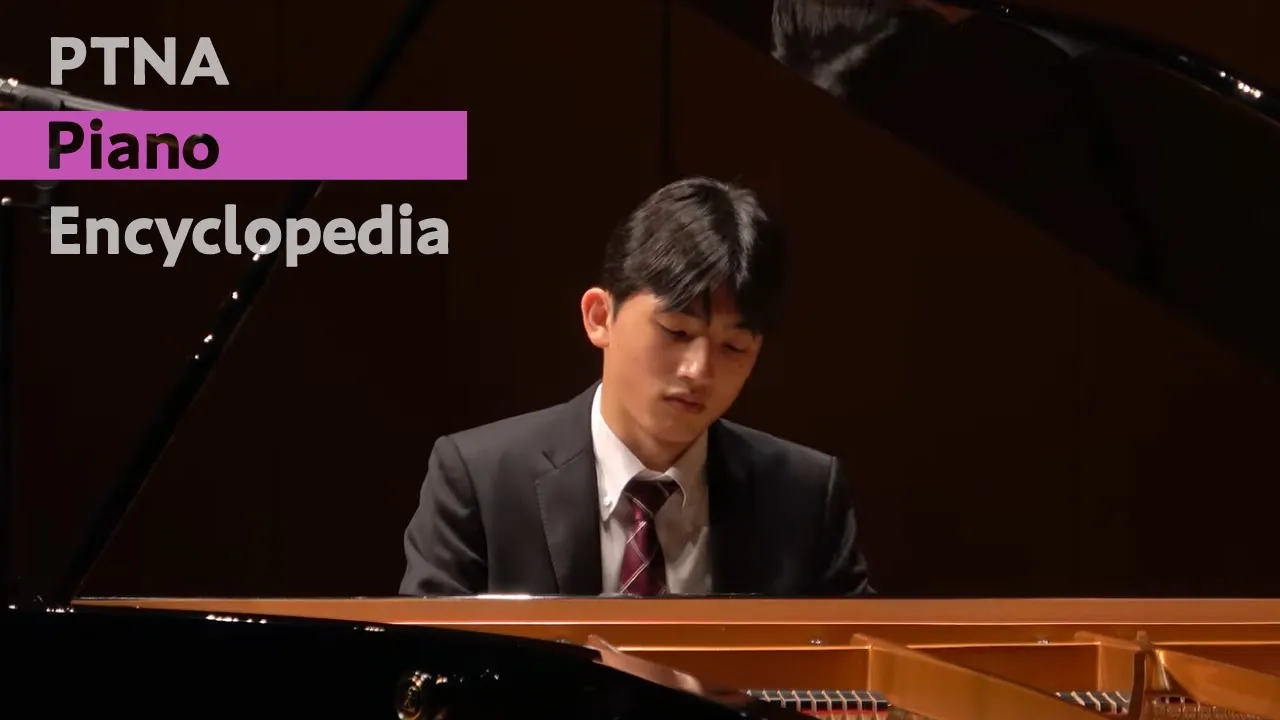Alexander Scriabinの人気曲ランキング【2026】
近年その影響が国際的な広がりを持っていることが明らかになってきたロシア出身の作曲家、アレクサンドル・スクリャービンさん。
ピアニストとして有望視されながらも学生時代に右手を壊してしまったことをきっかけに、作曲家として本格的に活動を始めました。
後期の作品では神秘和音を使った楽曲を制作し、前衛的作曲家としてその名を残しています。
今回は、そんなアレクサンドル・スクリャービンさんの人気曲ランキングをご紹介しますので、近代音楽の美しさを感じてみてくださいね!
Alexander Scriabinの人気曲ランキング【2026】(1〜10)
幻想曲 Op.28Alexander Scriabin1位

ロシアの作曲家アレクサンドル・スクリャービンが1900年に作曲したピアノ独奏曲。
単一楽章のソナタ形式で書かれ、高度な技巧を要求する作品です。
冒頭のロ短調で始まり、その後ニ長調の美しい旋律が登場。
中盤では激しい対位法的な展開があり、両手のアルペジオが印象的。
フィナーレではロ長調での力強い終結部があり、ワーグナーの影響を感じさせるクライマックスを迎えます。
複雑なテクスチャと豊かな感情表現が特徴的な本作。
スクリャービンの中期作品としての重要性が高く、後期の抽象的な作品への橋渡し的役割を果たしています。
華やかで力強い一面を持つピアノ作品をお探しの方におすすめです。
12の練習曲第12番「悲愴」Alexander Scriabin2位

スクリャービンの特徴でもある激しい和音の連打や跳躍が劇的で印象的な曲です。
スクリャービン自身のお気に入りの曲でもあり、自らもよく演奏したそうです。
やや落ち着く中間部からの激しいクライマックスの展開は迫力があります。
8つの練習曲 Op.42 第5番Alexander Scriabin3位

20世紀現代音楽の先駆者であり、独自の音楽言語を開発したアレクサンドル・スクリャービン。
彼が1903年に作曲した『8つの練習曲 Op.42 第5番』には、メランコリックでドラマチックなムードが漂います。
非常に高揚感のある旋律は、演奏者の高い技術と表現力を要求します。
ロマンティズムからより実験的で先進的な音楽へと移行していく過程が垣間見える本曲の神秘的かつ哲学的なアプローチからは、深い音楽性が感じられるでしょう。
ピアノ学習者の皆さんには、技術向上はもちろん、音楽的感性を磨くチャンスとしてもおすすめです。
ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 Op.20Alexander Scriabin4位

スクリャービンは、19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍したロシアの作曲家にして、ピアニストでもあります。
彼の名を知らなくとも、美しくも情熱的なメロディに心を奪われた方は多いのではないでしょうか。
彼の代表的なピアノ協奏曲『ピアノ協奏曲 嬰ヘ短調 Op.20』は、スクリャービン24歳の若さで書かれた彼の才能の結晶。
初期の作品でありながら、すでに彼独自の音楽性が色濃く反映されています。
全3楽章で構成され、詩情豊かな表現とヴィルトゥオーソ的な技巧が絶妙に組み合わさった秀作です。
ロマン派からインスピレーションを得つつ、革新的な作風にも挑戦した意欲作を、ぜひ味わってみてください。
ワルツ 変イ長調 Op.38Alexander Scriabin5位

19世紀末から20世紀初頭にかけて活躍した作曲家アレクサンドル・スクリャービン。
初期の作品はショパンの影響を色濃く受けていますが、次第に独自の音楽スタイルを確立。
神秘的で情熱的な曲風は、聴く者の心に深く響きます。
『ワルツ』は、彼の代表的なピアノ曲の一つで、優美な旋律とともに、所々で激しさをはらんだフレーズが現れるのが特徴的です。
繊細さと力強さを兼ね備えた本作は、豊かな感性を持つ全てのピアノ音楽ファンにぜひ聴いていただきたい名曲です。
幻想曲 ロ短調 Op.28Alexander Scriabin6位

『幻想曲 ロ短調 Op.28』は、後期ロマン派の作曲家アレクサンドル・スクリャービンの音楽的変遷を感じさせる作品です。
彼特有の美しい旋律と複雑な和声が織りなす情熱的な音楽世界は、リストやワーグナーをほうふつとさせるドラマチックな展開を見せます。
華麗なアルペジオや対位法的なテクスチャーなど、高度な演奏技術が求められるこの曲。
スクリャービンの英雄的な書法が詰まった名曲を、ぜひあなたの手で弾いてみてください。
12の練習曲 Op.8 第12番「悲愴」Alexander Scriabin7位

ロシアのピアニスト、作曲家であるアレクサンドル・スクリャービンが、フレデリック・ショパンの練習曲を意識して作曲したとされている『12の練習曲 Op.8』。
その最後を飾る第12曲目『悲愴』は、音域の広い分散和音や激しくかき鳴らされる右手のオクターブのメロディや両手での和音の連打など、高難度のテクニックを要する作品です。
『悲愴』と名の付く有名なクラシック曲は数多く存在しますが、練習曲と言えどもそれらに引けをとらないほどやり場のない怒りや深い悲しみが伝わってくる作品です。