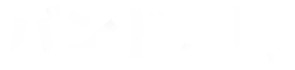「あの有名アーティストはどんな姿勢でレコーディングに挑んでたのか」
レコーディングにまつわるエピソードやトリビアなど、ちょっといい話をご紹介します。
- 5月の歌と共に贈る思い出。春の名曲と感動の歌物語
- 努力を歌った名曲。おすすめの人気曲
- 【変拍子の魅力】7拍子が使われている曲まとめ
- 【話題】オシャレすぎるCMソング。気になる楽曲の秘密
- 【作曲】定番コード進行を使っている有名曲まとめ【耳コピ】
- 【シチュエーション別】6種類のラブソング。心に響く恋愛ソング集
- 【聴き比べ】個性豊かな『シュガーソングとビターステップ』カバー曲
- さまざまな人生を歌った名曲。おすすめの人気曲
- 低音が魅力の男性アーティストの曲。邦楽の名曲、おすすめの人気曲
- 歌詞がいい応援ソング。心に残る素敵なメッセージ
- 人気アーティストにカバーされたスピッツの名曲
- 情熱を歌った名曲。おすすめの人気曲
- 高音が魅力の男性アーティストの名曲。おすすめの人気曲
レコーディングのちょっといい話
ロックバンドcoldrain、海外レコーディングドキュメント
静と動が交錯する極上の世界基準メロディアスラウドロックバンドcoldrain。
プロデューサーには日本人アーティスト初プロデュースとなるDavid Bendethを起用しました。
全世界デビューを果たし、自分達が理想とする制作環境に追い込む姿勢がハイエンドな音源を聴くと伝わってきます。
David Bendeth(デヴィッド・ベンデス)
ロンドンに生まれ、10代でトロントに移住。
PARAMORE、PAPA ROACH、KILLSWITCH ENGAGE、IN FLAMES、THE RED JUMPSUIT APPARATUS、UNDEROATHなどを手がけたレコード・プロデューサー。
日本のロックバンドcoldrainも絶大な信頼を寄せるプロデューサー、エンジニアです。
僕ら、今まで1枚のフルアルバムを通して同じエンジニアと一緒に作業していて。
シングル(「Fiction」「8AM」)と1stアルバム(「Final Destination」)は同じエンジニアで、最初のミニアルバム(「Nothing lasts forever」)と2ndアルバム(「The Enemy Inside」)がまた別のエンジニア。
で、今回もミニアルバム「Through Clarity」と同じ人(デビッド)っていう。
出会って間もない頃にシングルやミニアルバムでcoldrainのことをわかってもらった上で、本チャンっていうかフルアルバムに挑んでもらうのがいいなと勝手に思ってるんです。
デビッドも最初にミニアルバムを録ったときから「次のフルアルバムのときは、また一緒にやろう」みたいな話をしていたし、自然な流れだったと思いますよ。
レコーディング・メイキング映像
日本を代表する実力派ギタリスト、梶原順と安達久美による究極のギター・デュオ「J&K」の制作の裏側
2014年5月にエレクトリックアルバムとアコースティックアルバムの2タイトル同時発売する、梶原順&安達久美によるギター・デュオ「J&K」。
レコーディングエンジニアはスタジオラグの阪本大雅が担当。
機材やプレイだけではなく、エンジニアとのコミュニケーションも大切だということが伝わってきます。
梶原:アコースティックに関して、「いい音」で録ってもらいたいというのはあって、どれもそうなんですけど。
エレクトリックも当然「いい音」で録って欲しいんだけど、アコーステッィクに関してはエンジニアとのコミュニケーションというか。
僕らが「こんな音で録って欲しい」というのを理解してもらいつつ、それをどのマイクをどういう風に使って録るのかっていうのを決めるのはエンジニアなので、そこのへんのあるビジョンがエンジニアにちゃんと伝わって、それをエンジニアが理解して録ってくれるっていう、そこが一番大事なところかな。
エレクトリックギターに関しては、音色を自分の方でいじるというのも結構出来るので、アコギに関してはね、出た音を僕らはいじれないんで、どう録ってもらうかにかかってくるから。
前作と同じ阪本君にやってもらって、前作を踏まえてやってくれてるから、前作もすごい「いい音」だなと思ってたけど、比べてみると今回の方が格段にいいですね、さらに。
https://www.studiorag.com/interview/14/03/j_and_k/index.html
国民的人気アイドル、Perfumeのレコーディングの裏側
レコーディングを初めて行うアーティストにとっては、プロデューサーやエンジニアによって作品の出来が左右すると言っても過言ではありません。
国民的アイドルPerfumeもプロデューサーの中田ヤスタカと共に歩んできました。
中田はヴォーカルのレコーディングを行うに当たり、自宅兼スタジオで歌詞が書かれた紙を直前3人に渡してその場で覚えさせ、そのまま3人を電話ボックス大のブースの椅子に座らせて行う。
また、レコーディングにあたり中田から歌詞の意味を説明されることはなく、3人に対してなされる指示は「しゃべるように歌って」「そっけなく歌って」というようなものだけであることが多い。
中田から楽曲提供を受けることとなった当初、3人はテクノポップという音楽ジャンルが存在することを知らず、さらに以前通っていた広島アクターズスクールのレッスンでは楽曲に対してできる限り自分の感情をこめて歌うよう指導されていたことから、中田のこのような指示が理解できず、毎回のように泣きながらレコーディングを行っていたという。
このため、インディーズデビュー後間もない頃には、歌い上げるみたいな感じで歌い、反抗している感じの声がマッチしていない、理解できなくてただ歌わされているという感じであったといい、特に『スウィートドーナッツ』にはこのような印象が実際に表れているという。
当初は3人が中田の指示を理解できず、楽曲が好きになれない状態が続いたものの、メンバーがクラブイベントに参加した際に、フロアーがPerfumeの曲で楽しそうに踊っているところを目の当たりにするなどの経験から、自分達がかっこいい曲を作っているという自信につながり、曲作りにだんだんと主体的に取り組むようになった。
昭和の歌謡界を代表する歌手、美空ひばりの録音エピソード
「美空ひばりさんのレコーディングは、常に本番テイク1でOK!」
有名な「業界都市伝説」がありますね。
「本気で歌う」そして「高い表現力」が、レコーディングエンジニアにも伝わっていたのではないでしょうか。
そして日本人歌手初のデジタル録音は、日本が誇る歌手 美空ひばりさんです。
1973年1月、厚生年金会館でのライブを、試作1号機を使って収録しました。
そのときは試作1号機をトラックに載せていきました。
1本のVTRテープで録音できるのは約1時間。
休憩時間にテープを取り替えながら、コンサートの全曲を録音しました。
このときの録音はレコードとして発売され、売れ行きも良いものでした。
美空ひばりさんはその年、実は精神的に辛い時期でした。
しかし、ひばりさんはそのコンサートのとき楽屋で「せっかく新しい機械で録音してくれるんだから、私もがんばって歌います」と言ってくださったのをよく覚えています。
http://pr.denon.com/jp/Denon/Lists/Posts/Post.aspx?ID=262#.U3FH3NwvGTu
https://youtu.be/0fR3mDg9lHE?t=2m33s
hideのレコーディング方法
音楽に対する姿勢を常に高く持ち、生真面目すぎるぐらい勉強してたhide。
お客さんの前で最高のショーを見せるために、レコーディングでは様々なチャレンジや試行錯誤を繰り返されています。
hideはレコーディング前に一つの曲を何十回も何百回も録音してみるのだという。
そして、普通の人が聞いたら違いがわからないような細かい点まで、チェックしているのだそうだ。
ヴォイス・トレーナーが「なんでもうOKが出てるのに、そんなに歌い直すの?」と尋ねたら、「同じように聞こえるかもしれないけど、500回目に歌った歌よりも700回目に歌ったほうが絶対にいいんだよ。
ちょっとでもよくなるんだったら、ぼくは700回でも800回でも歌い直す」と、答えたという。
そんな不器用なまでの生真面目さが、彼の原点なのかもしれない。
韓国のフィギュアスケート選手 キム・ヨナのレコーディングの裏側
このような姿を見ると「スポーツに取り組む姿勢とも近いものがある」と感じさせられました。
サムスン電子によると、キム・ヨナは歌唱力が必要とされる同曲を児童合唱団と共に完璧に歌うため、相当練習したという。
練習の結果、キム・ヨナは高音と低音を行き来する同曲を原曲キーで熱唱。
高音が印象的なクライマックス部分も地声で歌い、大きな問題もなくレコーディングを終えたという。
ビートルズ全盛期当時、レコーディング背景が伺えるエピソード
当時まだ発展途上のレコーディング技術の底上げは、ビートルズがいたからこそではないでしょうか。
ビートルズがレコーディングにおいて最初に導入したであろうと思われる技術は現在も使われており、基本になっております。
今では考えられないことですが、当時のレコーディングは4トラックで行なわれていました。
そこにボーカルや楽器などの様々な音を詰め込みエフェクトをかけるわけです。
ビートルズによって多重録音という方法が開発されたのです。
つまりビートルズの歴史はレコーディングの歴史でもあったということです。
これらの作業にビートルズは多くの時間を費やしました。
ところが完成したものにジョンは納得せず、ビートルズが演奏したヴァージョンと、プロデューサーのジョージ・マーチンの管弦楽ヴァージョンをつなぎ合わせて一つにまとめるよう要求します。
キーもテンポも違う二つのトラックを一つにまとめることなど当時は不可能な話です。
ジョージ・マーチンは「無理だ」と答えます。
しかしジョンは「いや、ジョージ、君ならできるよ」と譲りません。
こうしてアビーロード・スタジオでは、それまで経験したことのない実験が始まりました。
それはまさに月に行くアポロ計画のようなものです。
そして奇跡は起きたのです。
最初のヴァージョンの速度を上げ、もう一つのヴァージョンの速度を下げれば2曲はうまくつながることをジョージ・マーチンは発見したのです。
こうしてジョンの意図したサウンドに仕上がったのです。
それを成しえたのは、ジョージ・マーチンとそのスタッフの努力に他なりません。
ちなみに二つのヴァージョンがつなぎあわせられているのは、スタートからちょうど60秒のところです。
最後に
音源自体の良さは、ミュージシャンの妥協しない姿勢、そしてエンジニアやプロデューサーの力が合わさることで生み出されます。
ベストな音源を制作することに集中したいものですね。
次の「いい話」の主人公はそう、あなたです。