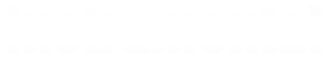【2026】洋楽のおすすめインストバンド。海外の人気バンド
皆さんは、インストゥルメンタル主体の楽曲を主にプレイするバンドに対して、どのようなイメージをお持ちでしょうか。
何となく興味はあるけどボーカルがない曲を聴く習慣もないし……といった風に先入観で苦手意識を持っている方もいらっしゃるかもしれません。
今回の記事では、そんな方々に向けて海外のおすすめインストバンドを紹介しています。
あえて往年のジャズやプログレッシブロックといったインスト主体のバンドではなく、1990年代以降のポストロックやマスロック、近年のジャズ周辺など新世代のグループなども多数紹介していますから、インストバンドに詳しい方もぜひチェックしてみてくださいね!
【2026】洋楽のおすすめインストバンド。海外の人気バンド(1〜10)
Ego Death feat. Steve VaiPolyphia

2020年代の今、最も注目を集めているインストバンドの1つといっても過言ではないでしょう。
新世代のギターヒーロー、ティモシー・ヘンソンさんとスコット・ルペイジさんを中心として2010年にテキサスにて結成されたポリフィアは、卓越したテクニックで魅せるハイブリッドかつプログレッシブなサウンドと、端正なルックスで高いスター性を誇る4人組です。
2014年にデビューアルバム『Muse』をリリース、プログレッシブメタルと呼ばれるテクニカルなインストバンドの音楽ファンの間で話題となり、2016年にはセカンドアルバム『Renaissance』のリリースと合わせて日本デビュー。
2017年には待望の初来日を果たし、オープニングアクトとして当時12歳の天才ギタリストLi-sa-Xさんが起用されたことも注目を集めました。
2020年にはあのBABYMETALのアルバム『Brand New Day』にゲスト参加するなど、ここ日本においてもコアな音楽好き以外でも着実にファン層は拡大しています。
そんな彼らが2022年の10月に発表した通算4枚目アルバム『Remember That You Will Die』は、従来のインストゥルメンタルサウンドに加えて複数のボーカリストをフィーチャー、もはやメタルやプログレといったジャンルに全くとらわれない、洗練されたポリフィア独自の音楽を展開し、バンドとしてもネクストレベルへと到達。
全米ビルボードチャートで33位を記録して商業的な成功も果たし、ますます勢いに乗る彼らの快進撃が今後も続くことは間違いないでしょう。
White CrayonAthletic Progression

デンマークのオーフスを拠点とするアスレティック・プログレッションは、ジャズとヒップホップを融合させたトリオです。
J Dillaさんを連想させる「ヨレ」のあるグルーヴを生演奏で再現するセンスは衝撃的の一言。
2019年にEP『Dark Smoke』が公開され注目を集めたのですね。
2021年にはアルバム『cloud high in dreams, but heavy in the air』をリリース。
本作は2019年にコペンハーゲンにて1週間かけて録音され、iPhoneのメモから楽曲を発展させたという背景も興味深いですよね。
ジャズ系アワードにノミネートされるなど実力も確かで、UKジャズやビートミュージックを好む方には大推薦のバンドですよ!
MAGIC!Arch Echo

アメリカはナッシュビルを拠点として、2016年の結成からプログレッシブ・メタルとジャズを融合させたサウンドで注目を集めているのがArch Echoです。
バークリー音楽大学出身の5人組である彼らは、2025年にEP『3X3: Catalyst』を発表するなど精力的に活動しており、インスト好きの間では知られた存在なのですね。
人気ゲーム『原神』のコンサートでアレンジを担当した経歴もあり、ゲーム好きの方であれば周知かもしれません。
そんな彼らの音楽性は、超絶技巧ながらもキャッチーなメロディが特徴で、巨匠ジョージ・ベンソンさんもギタリストのアダム・ラフォウィッツさんを称賛するほどの実力派です。
テクニカルな演奏と聴きやすさを両立させた彼らの楽曲は、インスト初心者の方にもおすすめですよ!
EsperanzaHermanos Gutiérrez

スイスを拠点とし、エクアドル系の兄弟が2本のギターで荒野を描き出すのがエルマノス・グティエレスです。
兄のエステバン・グティエレスさんと弟のアレハンドロ・グティエレスさんによるデュオは、2015年より「ギターが歌う」と評されるスタイルを確立しているのですね。
2022年にダン・オーバックさん主宰のレーベルからアルバム『El Bueno y el Malo』を発表、続く2024年6月のアルバム『Sonido Cósmico』では砂漠から宇宙へと世界観を拡張しています。
短編映像が賞にノミネートされるなど映画的な情景喚起力を持つ彼らの音楽は、言葉を用いない対話で聴き手を非日常の旅へと連れ出してくれることでしょう。
喧騒を離れて没入できる音をお探しの方にぜひおすすめしたいですね!
DangerousSurprise Chef

メルボルン出身のサプライズ・シェフは、インスト界で異彩を放つ5人組です。
2017年末に結成された彼らは、情景を描く演奏スタイルを確立し、2020年のアルバム『All News Is Good News』で注目を集めました。
70年代の映画音楽やヒップホップの影響を受けたサウンドは「ムーディーなインスト・ジャズファンク」と称され、聴く者を架空の物語へと誘う独特の空気感を持っています。
2023年にはアルバム『Education & Recreation』がARIA賞のジャズ部門候補に挙がるなど実力は折り紙付きですね。
2025年5月にはアルバム『Superb』を公開するなど精力的に活動しており、ソウルやファンクを愛する方にも大推薦のバンドですよ!
AccordionAbstract Orchestra

アブストラクト・オーケストラ、という名前を聞くと前衛的なクラシック集団を想像してしまうかもしれませんが、彼らは英国リーズで2011年に始動したヒップホップとジャズを横断するビッグバンド。
サックス奏者のロブ・ミッチェルさんを中心とした大編成で、J・ディラさんなどのビートを生演奏で再構築するスタイルが高く評価されています。
アルバム『Dilla』やMF・ドゥームさんの楽曲を取り上げた『Madvillain Vol. 1』など、名作を金管や弦を含む重厚なアンサンブルで蘇らせる手法は圧巻ですよ。
スラム・ヴィレッジとの共同企画として2020年に公開されたプロジェクトなど、単なるカバーを超えた再解釈を行う彼らの音楽は、ヒップホップのグルーヴとジャズの即興性を同時に楽しみたい方に大推薦のバンドですよ!
A Dance with DeathWe Lost The Sea

悲劇を経て独自の音世界を構築した存在として、シドニー出身のWe Lost The Seaを紹介します。
2007年に結成された彼らは、2013年にボーカルのクリス・トーピーさんが逝去されたのを機にインストゥルメンタルへ転身した経緯を持つのですね。
2015年のアルバム『Departure Songs』収録の『A Gallant Gentleman』はNetflixドラマ『After Life』で使用され話題となり、2019年のアルバム『Triumph & Disaster』は豪チャート41位を記録。
2025年7月発売のアルバム『A Single Flower』でも叙情的な轟音サウンドは健在で、モグワイなどが好きな方なら間違いなく琴線に触れるはずです!