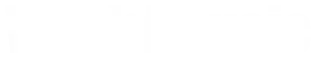アフリカ発祥の民族楽器まとめ
アフリカの楽器というと、あなたはどれくらいご存じでしょうか?
民族楽器としてポピュラーなアサラトやカリンバをはじめ、手で直接叩くパーカッションとして人気のジャンベもアフリカ発祥なんですよね。
しかし、アフリカにはもっともっとたくさんの民族楽器が根付いています。
この記事では先に挙げたような比較的知られている楽器はもちろん、日本ではあまり見かけない楽器まで、アフリカ発祥の民族楽器を一挙に紹介していきますね。
エキゾチックな雰囲気の音楽が好きな方はもちろん、ご自身で民族楽器を演奏してみたい方もぜひご覧ください。
アフリカ発祥の民族楽器まとめ(11〜20)
サカラ

サカラは、アフリカ・ナイジェリア北部のハウサ族が使用する片面太鼓の打楽器です。
タンバリンや沖縄の打楽器のバーランクのような大きさでアフリカの太鼓型の打楽器の中では比較的小さめです。
手に持って片手の指で打つ面を抑えることで音色を変え、もう片方の手のバチでたたきます。
フレームは焼き粘土で作られ、ドーナツ状になっています。
楽器本体の周りに間隔を置いて配置されたクサビは、皮の張りを調整するために使用されます。
トーキングドラム

トーキングドラムとは、その名の通り本来はコミュニケーションのために使用していた太鼓やその鳴らし方のことを指しています。
現在ではそこから転じて、打面の周りに固定されたヒモの張りを変えることで出音の音程を変えられる太鼓のことを指しています。
胴の両側に打面があるものと片側にしかないものがありますが、どちらも素手もしくは先の曲がった特徴的な形状のバチで叩いて演奏します。
一つの太鼓で高低さまざまな音色が出せるほか、1度叩いて出た音を途中で音程を変えるピッチベンド的な奏法が可能なため、自由度が高く特徴的なビートを作れます。
バラフォン

バラフォンは、西アフリカのグアン族が冠婚葬祭など場で使用する木琴です。
木の枠組の上に固定した木片をバーにして、下には共鳴するためのひょうたんががあることが特徴です。
伝統的なバラフォンだと、中がクモの巣やコウモリの羽などで薄い膜で覆われています。
これは、これらの薄い膜を振動させることで、ミルリトン効果によりビリビリとした独特な音を発生させる意図があります。
シロフォンやマリンバなどの西洋楽器のルーツである楽器です。
世襲制の職業音楽家「グリオ」だけが演奏できる楽器でもあります。
ボロン

ボロンは、マリやギニアなどの西アフリカで演奏されるハープ型の弦楽器です。
胴はひょうたんで、上部に毛の付いたままの獣皮が張られています。
この胴の部分に座って演奏します。
ネック部分である木の棒には3本の弦が張られ、ネックの先端には金属製の「ジャラジャラ」を付けることもあります。
胴に穴が空いており、胴をたたくことで打楽器としても使用でき、弦楽器と打楽器が一体になっています。
ハープ部分の音程は低めで、ボンボンという音色が特徴です。
オルトゥ

オルトゥはアフリカのケニアのオ族の弓奏の弦楽器で、ケニアやウガンダなどで演奏されます。
大きさは片手で支えられるくらい小さく、弦が1本しかないのが特徴です。
円筒のボディに皮が張ってあり、ネックは丸棒で指板はありません。
演奏は、弦楽器にはめずらしく楽器の底を腹部で支えて横向きに固定して演奏します。
歌の伴奏として使われることが多く、ベンガ・ビートと呼ばれる細かいリズムに合わせ、メロディと唄の合間のオブリガードを演奏します。
エコンティン

エコンティンは、西アフリカのセネガルやガンビア、ギニアビサウに住むジョラ族が愛用する、ギター型の弦楽器です。
ひょうたんのボディに獣の皮が張っています。
棒状の長いネックが特徴で、本の弦の長さが違い、長い弦でメロディが短い弦で装飾音が演奏されます。
また、アメリカで生まれたバンジョーの起源とされています。
奴隷としてアメリカへ連れてこられた西アフリカの人たちが、このエコンティンを元に弦楽器を作ったと言われています。
おわりに
アフリカ発祥の民族楽器を一挙に紹介しました。
アサラトやカリンバなどの民族楽器としては比較的ポピュラーなものから、日本ではほとんどしられていない楽器までさまざまな楽器の音色が聴けたと思います。
街の楽器店で手に入るものもありますので、この機会に興味を引かれた楽器を始めてみてはいかがでしょうか?