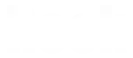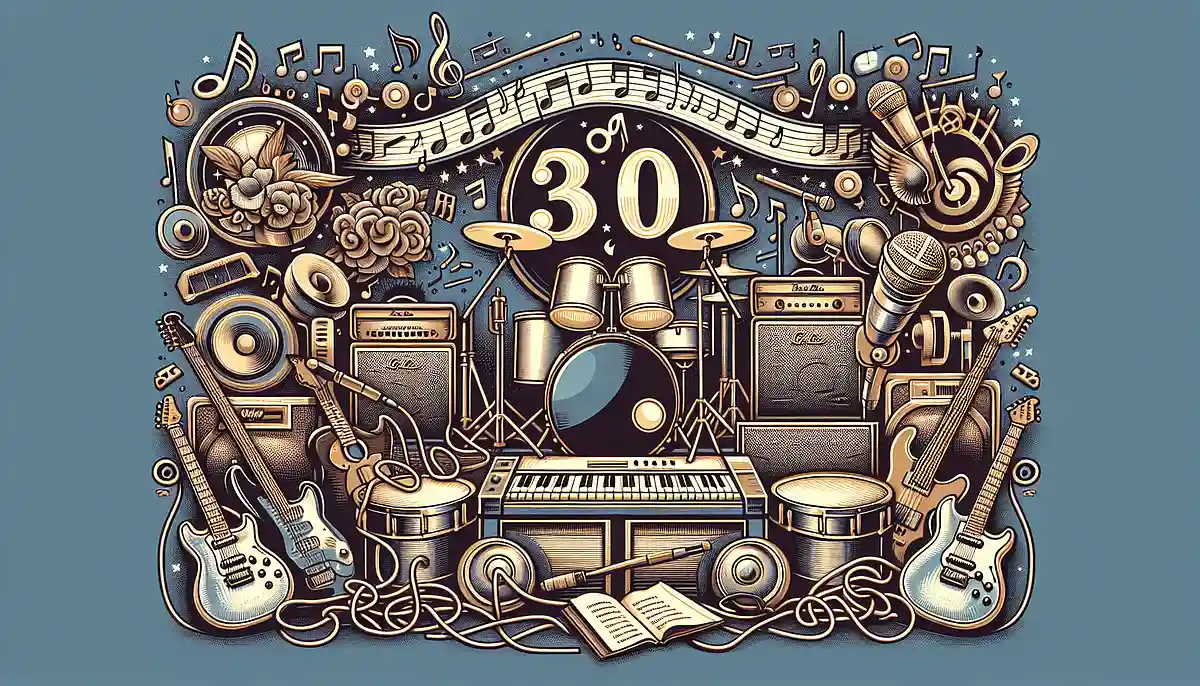独自の楽曲とともに時代を渡り歩いてきた日本のロックバンド、BUCK-TICK。
現役バリバリのバンドですが、まだ聴いたことがない方がおられたら、ぜひこの記事を一読してみてください。
それでは魅力と楽曲に迫ってみたいと思います。
- 【BUCK-TICKの名曲】圧倒的な存在感を放つ伝説のバンドの人気曲
- BUCK-TICKの人気曲ランキング【2026】
- 40代に人気のバンドランキング【2026】
- ヒットソングから隠れた名曲まで!30代におすすめの春ソング
- Acid Black Cherryの人気曲。耽美性やコンセプト性が光る名曲
- L'Arc~en~Cielの名曲|大ヒット曲から隠れた名曲まで一挙紹介
- ヴィジュアル系の名曲。V系ロックを代表する定番の人気曲
- LUNA SEAの名曲。通も唸る深い魅力を持つ楽曲たち
- DIR EN GREY(ディル・アン・グレイ)の名曲・人気曲
- 【BOØWYの名曲】隠れた人気曲から代表曲まで一挙紹介!
- 90年代のビジュアル系バンドのデビュー曲
- 古き良きロックサウンド!The Birthdayの人気曲とは
- 凛として時雨の名曲・人気曲
BUCK-TICK(バクチク)とは?
BUCK-TICK、と名前を聞くと一定の年齢の方々は「あの頃人気あったなあ」とか「惡の華」とかそんなイメージを思い浮かべると思います。
まさにあの人は今、状態です。
世間からはそう思われているBUCK-TICKですが、実際はコンスタントに活動を続けてもう結成から30年になります。
その間に一度もメンバーチェンジもなく、根強い固定ファンも居ます。
そういうタイプのバンドで他に知ってるのはエレファントカシマシくらいでしょうか。
しかし、私はバンドのすごさの本質はそこにはないと思っています。
彼らの楽曲を聴くとわかるのですが常に時代の最先端を走り続けています。
決して懐古趣味だからとかそういった理由で支えられている人気ではありません。
実際今でもアニメやインターネットの影響で若いファンがいますし、今をときめくアーティストだと[Alexandros]のドラム、庄村聡泰が好きなバンドであると雑誌で公言していたこともあります。
しかし、ここまで人を引きつけるBUCK-TICKの楽曲とは何なのでしょうか?
今回はそこにスポットライトを当てたいと思います。
メンバー編成
BUCK-TICKは1987年に群馬で結成されたバンドで、全員が群馬県出身です。
メンバーは5人で、
- 櫻井敦司(さくらい あつし 1966年3月7日 ):ボーカル・作詞。
- 今井寿(いまい ひさし 1965年10月21日 ):ギター・ノイズ・コーラス・作詞・作曲。
- 星野英彦(ほしの ひでひこ 1966年6月16日 ):ギター・キーボード・コーラス・作曲。
- 樋口豊(ひぐち ゆたか 1967年1月24日 ):ベース。
- ヤガミトール(1962年8月19日 ):ドラムス。
(敬称略)
この5人で構成されています。
1988年のメジャー初シングル「JUST ONE MORE KISS」はラジカセ「CDian」のタイアップに使用され大ブレイクしました。
その頃の「逆立てた金髪+化粧」のインパクトによって、「X JAPAN」などと並ぶビジュアル系の元祖的な位置付けをされました。
そしてバンドブーム時からメジャーレーベルで活動し続けている数少ない現役のバンドでもあります。
ビジュアル系というのは音楽の定義ではないので、扱いが難しいのですが、ビジュアル系というジャンルにおいてBUCK-TICKに影響を受けた人間は多く、J、SUGIZO(ともにLUNA SEA)、yukihiro(L’Arc~en~Ciel)、逹瑯(MUCC) とそのシーンではそうそうたるメンバーです(敬称略)。
そしてBUCK-TICKはビジュアル系の先駆者であって本人自体はビジュアル系ではないため「ビジュアル系は苦手だけどBUCK-TICKは好き」というファンも多いです。
そのため、畑違いのジャンルであるような氣志團のボーカル、綾小路翔やCoaltar of the DeppersのNARASAKIもリスペクトを公言、トリビュートアルバムに参加しているなど、ビジュアル系以外に与えた影響もあったりします。
楽曲の魅力
このバンドの魅力といえば、櫻井敦司さんの常人離れしたルックスと蠱惑的な歌声、そこに今井寿さんのトリッキーなギター、そしてリズムギターとベース、ドラムの生み出す、一聴すると聴きやすいのに奥が深い、どこか奇妙でポップなロック、ということがあげられるでしょう。
彼らが91年のアルバム「狂った太陽」リリース後から一貫している行っていることにクラブミュージックや電子音楽へのアプローチが挙げられます。
その「狂った太陽」の直近のアルバムである「darker than darkness-style 93-」ではヘビーでノイジーなギターをダブやヒップホップ的なリズムに乗せて披露するということも行っておりますし、97年のアルバム「SEXY STREAM LINER」では当時、世界的に流行していた、ドラムン・ベースやデトロイト・テクノの影響が垣間見えるような楽曲を数多く作り、近年では「アトム 未来派 No.9」のようにエレクトロニカ的な旋律とバンドサウンドを密に組み合わせ、こん然一体としたどこかサイバーパンク的な楽曲を生み出すなど、いわゆる普通のバンドサウンドに縛られない姿勢を一貫して見せ続けています。
そうやって核を保ちながらも時代に対して存在を変化させ続けることが、バンドとしていつまでも新しい存在でいられる理由なのだと思います。
聴けばハマる、とは保証できませんが、結成30年になろうともするバンド、という固定観念の曲ではないことは確かなのでぜひ聴いてみて頂きたいです。
おすすめ曲
BUCK-TICKは30年にも及ぶキャリアを誇るため多彩な楽曲がそろっています。
今回はその中でもおすすめの曲を年代がある程度バラけるように11曲をピックアップしてみようと思います。
1. ICONOCLASM
BUCK-TICKが初めてオリコン1位を獲得した1988年のアルバム「TABOO」と過去の楽曲をセルフカバーした1992年の「殺シノ調べ this is not greatest hits」に収録されたのを始め、ベストアルバムにもよく収録されている楽曲です。
楽曲はインダストリアルで無機質なドラムフレーズにどこかメロディーとずれたギターが乗っかり、独特なグルーヴを生み出しています。
88年、かなり初期のインダストリアルに影響を受けていながらもジャンルの祖とも言えるようなThrobbing GristleやFoetus ほどマニアックではなく、どこかポップさを持たせているのが実にBUCK-TICKらしいです。
オリコン1位のアルバムの最初とは思えない曲で最初聴いたときは非常に驚きました。
2. 惡の華
BUCK-TICKの代表曲とも言えるナンバーです。
1990年の同名のアルバム「悪の華」に収録されています。
疾走感のある曲に櫻井敦司のビジュアルと声、そして今井寿のトリッキーなギターというBUCK-TICKの王道スタイルがここで完成したような印象を受けます。
当時のビジュアルイメージがなかなかに真っ黒なのですが、それとあいまって、いわゆる「ゴシック的なバンド=BUCK-TICK」と思っている人も多いです。
フランスの詩人、シャルル・ボードレールの著作にも同じ名前の詩集があるのですが、関係は不明です。
どこかちょっと暗そう、というまさに世間がイメージするBUCK-TICKを決定づけたような楽曲です。
このアルバムもオリコン1位を獲得しています。
3. die
1993年「darker than darkness -style93-」に収録されたナンバーです。
この頃のBUCK-TICKはパブリック・イメージから離れ始め、非常に暗く重い作風の作品をたくさんリリースした時期になります。
ノイジーなギターとアコースティック・ギターの対比が非常に美しいミドルナンバーですが、歌詞の内容は非常に暗く、この時期のBUCK-TICKがいかに重苦しいヘビーな作風に進んだのか窺い知れるナンバーです。
さらに、この時期にリズム隊が8ビートな縦ノリ主体から16ビート的な横ノリに変化し始めているので、その違いをJUST ONE MORE KISSと聴き比べると面白かったりします。
ちなみに、この頃の櫻井敦司さんはストレートロングで女性と見間違うほどの美しさです。
4. 見えない物を見ようとする誤解 全て誤解だ
1995年、BUCK-TICK最大の問題作と言われているアルバム「Six/NiNe」に収録されています。
タイトルの長さもさることながら、ひたすらに暗い歌詞と非常にヘビーなリフを合わせ、さらにリズムの気だるさとが相まってとてつもなく暗い楽曲に仕上がっています。
特にこれと言って盛り上がるような要素もなく淡々とサビまで自己問答とも取れる歌詞が歌われるため、聴いているとこっちまで不安になってくること間違いないです。
そもそも、このアルバム自体に櫻井敦司さんの非常に暗い精神状態が反映されており、その影響かアルバム自体が非常に重い雰囲気に包まれています。
5. ヒロイン
1997年のアルバム「SEXY STREAM LINER」に収録された楽曲です。
この曲の特徴というとなんといってもドラムで、明らかにドラムン・ベースを意識した楽曲になっています。
イングランドで90年代初頭に発祥したとされているジャンルですが、インターネットが十分に発達してるとはいえない97年にいち早く世界の潮流を楽曲に取り込み表現するそのセンスには脱帽するばかりです。
クラブミュージック的なアプローチはギターシンセの導入から始まり一貫して続けていたのですが、このアルバムで一気に振り切れた印象があります。
アルバムを通してどこかテクノだったりもはやドラム自体がなくても良い楽曲まで作り上げました。
バンドの出した音とは思えないほどです。
ここからBUCK-TICKはクラブミュージックや電子音楽とバンドサウンドを融合させることに力を入れ始め、どちらか一色!
というのは非常に少なくなるので、「ヒロイン」はある意味貴重なアプローチの楽曲になります。
6. 極東より愛をこめて
2002年のアルバム「極東 I LOVE YOU」に収録された楽曲です。
この曲は2001年のアメリカ同時多発テロに影響を受けていると関連付けられることもあり、歌詞にも所々に彼らなりのメッセージを感じる、非常に象徴的な歌詞が多く含まれています。
サウンド自体はSEXY STREAM LINER以降目指すようになったクラブミュージック、電子音楽と有機的なバンドサウンドの融合を意識した最初期の作品であり、どこか有機的な電子音に疾走感のあるドラムと不思議な音色とフレーズのギターが載るという現在のBUCK-TICKの王道を貫いています。
ちなみにライブだと火柱を上げたり、今井がテルミンを使うなどなかなか自由な発想をしていておもしろいです。
7. 残骸
2003年のアルバム「Mona Lisa OVERDRIVE」に収録されています。
非常に攻撃的な歌詞と凶悪なリフでインパクトが強いため、実はBUCK-TICKでは珍しく初心者にも結構薦めやすい曲です。
俺という呼称が効果的に使われることで楽曲にかっこよさをプラスしているところもあるのですが、何と言ってもイントロや間奏のリフが非常に凶悪であり、この楽曲だけ聴くとJUST ONE MORE KISSを出してたような初期とはもはや別物のバンドになりました。
このアルバムではデジタルハードコアを基調としたアプローチが多いため楽曲全体に非常に攻撃的な雰囲気が満ちている。
ちなみに前作「極東I LOVE YOU」とはもともと二枚組でリリースする予定があったらしいです。
白黒で統一されたPVが非常に格好いい……のですがライブもまた格好いいです。
しかし、この曲に限らず今井寿さんはCDどおりに弾かないので、ライブではよくCDと違うフレーズを聴くことがあります。
この曲のPVでも変わったギターを持ってるので映像を何曲か見た方なら「こういう変なギター持ってる人なんだな今井寿さんって……」という認識がすぐでき上がるでしょう。
7. ROMANCE
2005年「十三階は月光」に収録されています。
惡の華以降、長らくゴシック的な路線から離れていたBUCK-TICKが満を持してゴシック路線に傾倒した楽曲であり、ボーカルの櫻井敦司さんがインターネット上で「魔王」と称されるようになったキッカケの曲でもあります。
ひたすらに耽美(たんび)な歌詞でギターもオーソドックスですが、楽曲のもつ雰囲気を十二分に引き出す歌詞とビジュアルでまさしく、後続のビジュアル系に対し、ゴシックとはこういうものだ、という本気を見せつけたように思います。
この曲のゴシックな雰囲気は「十三階は月光」にも受け継がれていて前編に渡りゴシック的でどこかサーカスのような雰囲気を醸し出しています。
このPVの櫻井敦司さんがひたすらに麗しいので必見です。
8. くちづけ
https://www.youtube.com/watch?v=b8X2NXAKteE
2010年「RAZZLE DAZZLE」に収録された楽曲。
アニメ「屍鬼」のOPを飾り、新規ファンを獲得するキッカケになった曲です。
BUCK-TICKらしい耽美(たんび)な世界観をPVでも歌詞でも表現しており、BUCK-TICKの持つ魅力を端的に表現できたナンバーでもあります。
ザクザクしたギターと4つ打ち主体のドラムなど実は今の若手バンドがやりそうなアプローチを5年以上前の2010年に行ったのだから驚きの一言です。
アルバムは全編にわたり踊れるようなテンポの曲が集まっています。
それもそのはず、「RAZZLE DAZZLE」とは「ばか騒ぎ」を意味する英単語ということで、ダンスミュージックを全編に渡って展開した曲だからです。
ちなみに「RAZZLE DAZZLE」のジャケットは宇野亜喜良さんという著名なグラフィックデザイナーの描き下ろしで、詩人で劇作家の寺山修司さんとも仕事をしていたほどの方です。
9. MISS TAKE~僕はミス・テイク~
2012年のアルバム「夢見る宇宙」に収録されています。
楽曲のアプローチ自体はBUCK-TICKの王道ですが、今までより少しストレートに攻めています。
特段、変わったリフもなく、そんなにひねくれた楽曲でもありません。
かなり彼らにしてはシンプルです。
しかし、それ故に非常に完成度が高い楽曲でもあります。
ツインギターでありつつも互いが明確にフレーズをわけずユニゾン的に弾くことでギターサウンド全体に厚みを持たせ、サビをコード弾きから始めることで一気に解放感をプラス、そして珍しくギターソロも入れるという、ロックの王道的な楽曲で個人的にも好みです。
歌詞が楽曲のリリースが東日本大震災後であることも相まって何とも言えない切なさ、そしてその後ろにある決意と強さを感じさせるように思われます。
アルバムには、画家グスタフ・クリムトの作品「金魚」を使用しておりジャケットが目を引きます。
震災後から約1年ということも相まってそこに影響された楽曲が多く、どこか内省的で生々しく、物悲しさと光の両方を感じるアルバムでもあります。
BUCK-TICKでは珍しくシューゲイザー的要素の「夢見る宇宙」という楽曲もあったりします。
10. 形而上 流星
2014年のアルバム「或いはアナーキー」に収録されています。
アルバムのメインテーマが「シュールレアリスム」だったこともあり、コンセプチュアルな内容に仕上がっています。
非常に効果的に使われている電子音、アルペジオと切ない歌声の対比、そしてサビでのボーカルとギターの開放感が楽曲の全編で美しさを付加しているバラードであり、BUCK-TICKらしい死への向き合い方が随所に見られる歌詞との相乗効果は圧巻の一言です。
ライブだと電子音の響き方がどこかスペーシーだったり、ギターとは思えないほどエフェクティブな音を使っていたりとシュールレアリスムというテーマに恥じない、既成概念にとらわれないアレンジをされており、原曲の魅力が十二分に引き出されています。
ライブでもそうなのですがシュールレアリスムというテーマが全編で貫かれた、アルバム「或いはアナーキー」はBUCK-TICKの中でもおそらく最もアーティスティックな作品に仕上がっており、中でも「無題」という楽曲はBUCK-TICKの自由さ、BUCK-TICKというバンドの真髄を垣間見ることができるものになっています。
11. New World
現時点での最新アルバム、2016年の「アトム 未来派 No.9」に収録された楽曲です。
全編を通してまばゆいばかりの前向きさと疾走感、結成30年になるバンドとは思えないほどのみずみずしい楽曲、この年月でなおNew Worldというタイトルが付けられるその姿勢が非常に素晴らしいと感じさせてくれる希望に満ちた曲です。
楽曲自体は、エレクトロニカ的な電子音とギターサウンドのバランスを大事にしている印象で、どちらかが脇役になることなく、主役として使われています。
特にサビの部分においてはむしろギターサウンドより電子音のほうが際立つアレンジがされ、さらに非常に前向きさと力強さを感じる歌詞の表現が多いです。
昔のBUCK-TICKではまずできなかったであろうアプローチや表現は、年月というものの重みというものと進化を止めないバンドの真価を存分に見せつけています。
アルバムに関しては長尺の曲が少ないかわりに、個々の楽曲に多様性を持たせ非常に攻めた楽曲が多い印象です。
「或いはアナーキー」はコンセプトも相まって、非常にアーティスティックでしたが、今作はもう少し自由にさまざまな方向性を持った曲を集めたことが結果的に1つの新たな方向性を持ったような印象です。
PVでは映像をコマ送りにしたり、早送りにしたりとさまざまな加工を施し、要所要所につなぎ合わせることでで楽曲をより魅力的なものにしています。
最後に
ここまで長々と書きましたが、僕がBUCK-TICKが大好きで絞るのは難しかったです。
彼らは過去も最高で、なおかつ「今」が最高のバンドです。
バンドが次々と解散や活動休止になる昨今の厳しい音楽事情の中でBUCK-TICKのような存在はまさに奇跡であり、30年の重みとみずみずしい楽曲の数々は僕を魅了してやまないのです。
そのように思える音楽に、皆さんも出会えることを願っています。