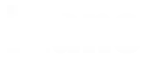バレエ音楽をピアノで弾こう!名シーンを彩る珠玉の名曲を厳選
美しい衣装を身にまとったダンサーたちの華麗な舞に心奪われる「バレエ」。
ダンスもさることながら、物語が展開していくうえで欠かせない音楽も非常に魅力的で、印象に残る曲ばかりですよね。
今回は、そんなバレエ音楽の中でも特に知名度が高く、バレエに詳しくない方でもきっとどこかで耳にしたことのある名曲ばかりをピックアップ!
ピアノ演奏の動画とともに、曲の背景や魅力をお伝えしていきます。
バレエ音楽はオーケストラで演奏されるのが一般的ですが、今回ご紹介する作品の中には、バレエ音楽をもとにピアノ独奏用作品に編曲したものも含まれています。
原曲との違いも楽しみつつ、バレエの世界をご堪能ください!
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- バレエ音楽の名曲|定番のクラシックを紹介
- 美しすぎるクラシックピアノの名曲。心洗われる繊細な音色の集い
- 【ワルツの名曲】ピアノのために書かれたクラシック作品を一挙紹介!
- 【本日のピアノ】繊細な音色で紡がれる珠玉の名曲・人気曲
- 【中級者】オススメのピアノ連弾曲|かっこいい&華やかな作品を厳選
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- 【クラシック音楽】全曲3分以内!短くてかっこいいピアノ曲まとめ
- 【難易度低め】チャイコフスキーのおすすめピアノ曲【中級】
- 【中級レベル】華やかな旋律が印象的なピアノの名曲を厳選!
- 切なく美しい!おすすめのピアノ曲まとめ
- ピアノで弾いてもかっこいい!ヴァイオリンが主役の名曲を厳選
バレエ音楽をピアノで弾こう!名シーンを彩る珠玉の名曲を厳選(1〜10)
ボレロMaurice Ravel

20世紀前半を代表するフランスの作曲家、モーリス・ラヴェルの代表作の一つである管弦楽作品『ボレロ』。
1928年11月22日にパリ・オペラ座で初演されたこの作品は、ロシア人ダンサーのイダ・ルビンシュタインの依頼で作曲されました。
『ボレロ』はオリジナルの二部形式のテーマが18回変奏されるという独特な構成をしており、スネアドラムによる単調なリズムと、さまざまな楽器が次々とメロディを奏でていくオーケストレーションが特徴的です。
この組み合わせにより、曲が進行するにつれて音量と強さが増していき、聴き手を圧倒するような印象的なクライマックスへと導かれます。
特徴的なリズムを刻むパーカッションとピアノのアンサンブルで演奏するのもオススメですよ!
シェヘラザード Op.35Nikolai Rimsky-Korsakov

ニコライ・リムスキー=コルサコフは、ロシア五人組の一人として知られ、民族色豊かなオペラや色彩感あふれる管弦楽曲を数多く残しました。
彼の代表作『シェヘラザード Op.35』は、1888年に完成した『アラビアンナイト』の物語をテーマとした交響組曲です。
この作品は鮮やかなオーケストレーションと独奏ヴァイオリンを用いて、物語の世界観を巧みに描き出しています。
4つの楽章はそれぞれ異なる物語を表現しており、聴く者の想像力を刺激します。
本作は音楽的な美しさと物語性で聴衆を魅了し続け、リムスキー=コルサコフの創造性と技巧を示す名曲といえるでしょう。
劇付随音楽「真夏の夜の夢」Op.61より「結婚行進曲」Felix Mendelssohn

フェリックス・メンデルスゾーンは、初期ロマン派を代表するドイツの作曲家です。
彼の作品は古典主義の様式を尊重しつつ、ロマン主義の感情や想像力を取り入れたものとして知られています。
『劇付随音楽「真夏の夜の夢」Op.61』は1842年に発表された作品で、特に『結婚行進曲』は結婚式のBGMとして広く親しまれています。
この曲は華やかで威風堂々とした旋律が特徴的で、妖精たちの楽しげな歓声や恋人たちの幸せな様子を思わせます。
メンデルスゾーンが描く夢のような世界観を、優雅なメロディで表現した名曲を、ピアノ演奏でも楽しんでみてはいかがでしょうか?
バレエ音楽をピアノで弾こう!名シーンを彩る珠玉の名曲を厳選(11〜20)
舞踏への勧誘 Op.65Carl Maria von Weber

ドイツのロマン派音楽の初期に活躍し、ドイツ・ロマンティック・オペラの発展に決定的な役割を果たしたカール・マリア・フォン・ウェーバー。
『舞踏への勧誘 Op.65』は、そんな彼が残したピアノ作品の一つで、『華麗なるロンド』とも呼ばれる人気の高い曲です。
1819年に妻のカロリーネのために作曲され、1821年にパリで初出版された本作は、序奏とコーダを伴うワルツ集の形をとっており、ドラマ的なストーリーを描いています。
細かい音の粒をそろえ優雅さと情熱を表現するのはもちろん、ベルリオーズによる管弦楽版など多彩な編曲にも注目です!
バレエ音楽「白鳥の湖」より「ワルツ」Pyotr Tchaikovsky

ロシアを代表する作曲家ピョートル・イリイチ・チャイコフスキーは、『白鳥の湖』『眠れる森の美女』『くるみ割り人形』など、数多くの名作バレエ音楽を残しています。
彼のバレエ音楽は、ピアノ独奏用にも数多く編曲されており、中でも『白鳥の湖』より『ワルツ』は人気の1曲。
原曲はオーケストラによって演奏されますが、ピアノ版は軽快なリズムと優雅なメロディが特徴です。
ぜひ原曲と聴き比べながら、ピアノならではの表現を探ってみてください。
軽快なワルツを楽しく、華やかに演奏できるよう練習を重ねましょう!
バレエ音楽「マ・メール・ロワ」より「5. 妖精の園」Maurice Ravel

フランスを代表する作曲家モーリス・ラヴェルは、幼年期の記憶や想像力をかきたてる童話の世界を音楽で表現することに長けていました。
特に1908年から1910年にかけて作曲されたピアノ連弾組曲『マ・メール・ロワ』は、シャルル・ペローの『マザー・グースの物語』などを題材とした、ラヴェルならではの繊細で色彩豊かな作品です。
第5曲『妖精の園』は、組曲の終曲を飾るにふさわしい美しい旋律が印象的。
バイオリンの官能的な音色が物語のクライマックスを思わせ、聴く者を童話の世界へといざないます。
『眠れる森の美女』のワンシーンのようにも感じられるこの曲は、フィナーレにふさわしい華やかで幻想的な輝きを放つ本作は、ラヴェルの作品を初めて聴く方にもおすすめの1曲です。
バレエ音楽「ジゼル」より「ジゼルのヴァリエーション」Adolphe Adam

アドルフ・アダンは、19世紀フランスの作曲家・音楽教師・音楽批評家として活躍しました。
彼の代表作であるバレエ『ジゼル』より、ヒロインの重要なソロ場面である『ジゼルのヴァリエーション』は、物語の山場を盛り上げる印象的な音楽です。
中世ドイツの村を舞台に、心優しい村娘ジゼルが恋人の裏切りにより亡くなり、ウィリとなって彼を救うという悲劇的な愛の物語。
主人公の純粋な愛情と悲しみ、そして強い意志が表現された曲です。
特に、踊りを愛するジゼルの無邪気さや喜びが感じられるフレーズは、彼女の人間性を象徴しているでしょう。