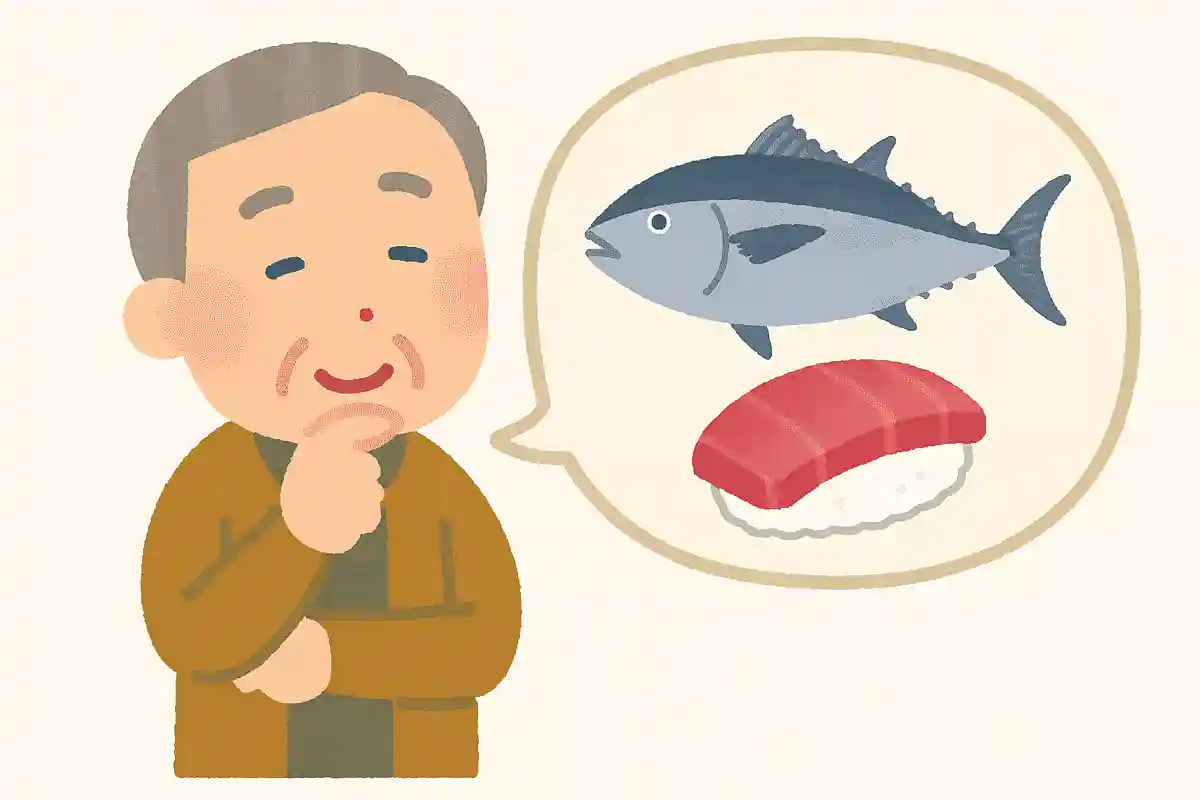【高齢者向け】何問解ける?おもしろい寿司の雑学クイズ&豆知識問題
お寿司にまつわる面白い雑学クイズに挑戦してみませんか?
軍艦巻きの由来から、お寿司屋さんならではの隠語まで、驚きの豆知識がいっぱいです。
高齢者の方と一緒に考えながら、昔のお寿司にまつわる思い出話に花を咲かせるのも楽しいですね。
「ギョク」や「むらさき」など、普段何気なく使っている言葉の意外な由来に、思わず「なるほど!」と声が出てしまうかもしれません。
お寿司の奥深い世界を、みんなで和気あいあいと学んでみましょう。
【高齢者向け】何問解ける?おもしろい寿司の雑学クイズ&豆知識問題(1〜10)
お寿司のネタで「トロ」と呼ばれるのは、魚のどの部位でしょうか?
- 背中の部分
- 尾びれの部分
- お腹の部分
こたえを見る
お腹の部分
「トロ」とは主にマグロなどの、魚のお腹の部分のことで、特に脂が乗ったところを指します。お腹の部分は脂が多く、口の中で柔らかくとろける食感が特徴です。背中や尾の部分に比べて脂質が豊富なため、お寿司でも高級なネタとされています。
お寿司を握る際に、ネタとシャリをくっつけるために使われるものは何でしょうか?
- 酢
- 砂糖
- わさび
こたえを見る
わさび
お寿司を握るとき、ネタとシャリの間には少量のわさびが塗られ、これにより接着剤のような役割も果たします。風味づけと同時に、ネタとシャリがバラバラになりにくくなるような工夫の意味があるんですよ。
次のうち、鉄火巻きの名前の由来として正しいのはどれでしょうか?
- 中のマグロが赤く、火のようだから
- お寿司を焼いて食べたから
- 鉄火場で人気だったから
こたえを見る
鉄火場で人気だったから
鉄火巻きの「鉄火」は、もともと賭博場=鉄火場にちなんで名付けられました。賭博場で手軽に食べられる巻き寿司としてマグロの赤身の巻き寿司が人気だったことから、この名前が付けられたと言われています。
お寿司を1つ、2つ……と数えるときの一般的な数え方は何でしょうか?
- 個
- 巻
- 貫
こたえを見る
貫
お寿司は通常「一貫、二貫」と数えます。江戸時代の貨幣や重さの単位である「貫」が語源で、主に握り寿司を数える時によく使われます。ちなみに巻き寿司や押し寿司は、切る前は「一本」、切った後は「一個」と数えますね。
お寿司屋さんで「ギョク」と呼ばれるものは何でしょうか?
- まぐろ
- いくら
- たまご焼き
こたえを見る
たまご焼き
お寿司屋さんで「ギョク」とは「玉子焼き」を意味しています。「玉」という漢字を使い、「ギョク」と音読みで呼んだことが由来とされています。熟練の職人が焼き上げる甘くてふんわりした玉子焼きは、お寿司屋さんの腕の見せどころとされています。
お寿司屋さんでは「わさび」のことを何と呼ぶでしょうか?
- なみだ
- おろし
- みどり
こたえを見る
なみだ
お寿司屋さんでは、わさびのことを「なみだ」と呼びます。これは、わさびのツーンとくる辛さによって涙が出ることに由来していると言われています。大正時代以降からこの呼び方がされるようになり、江戸時代ではカツオにつける辛子のことをなみだと呼んでいたんだそうですよ。
お寿司屋さんで「お茶」のことを何と言うでしょうか?
- あがり
- さび
- がり
こたえを見る
あがり
お寿司屋さんではお茶のことを「上がり」と呼びます。これは、江戸時代に芸妓の世界で使われていた「上がり花」という言い回しに由来しているそう。当時、客がつかない暇な状態を「お茶をひく」と呼んでいただため、お茶という言葉は縁起がよくないものとされていたんだそうですよ。