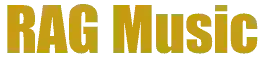演歌と言えば、抜群の歌唱力でこぶしを効かせた独特の歌いまわし、ビブラートの多用などカラオケなどで歌うには水準以上のレベルが要求されるジャンルですよね。
もちろん歌いやすい曲も存在しますが、こちらの記事では歌うのが難しい演歌の名曲たちをまとめています。
最初に書いたような演歌特有の特徴的な歌い方はもちろん、音域の幅の広さなども踏まえて高い表現力が必要とされる高難易度の楽曲がずらりと並びました。
本稿では女性の演歌歌手による名曲を紹介していますが、男性歌手による歌うのが難しい演歌の名曲も他の記事で紹介していますからそちらもチェックしてみてください。
- 【2026】歌えたらすごい!演歌の名曲【女性歌手編】
- 【2026】歌うのが難しい演歌~男性歌手編
- 【2026】カラオケでおすすめの簡単な演歌~女性歌手編
- 【2026】歌いやすい演歌~往年の名曲から最近のヒット曲まで【女性歌手編】
- 【女性向け】難易度の高い演歌の名曲
- 女の演歌。女性の心情を歌った演歌の名曲まとめ
- 【2026】60代の女性演歌歌手まとめ。日本の演歌を支える歌手
- 【2026】演歌の最近のヒット曲。要注目の歌謡人気曲
- 【2026】演歌の代表的な有名曲。定番の人気曲まとめ【初心者向け】
- 【女性向け】カラオケで高得点を狙える演歌の曲まとめ
- 【初心者向け】カラオケでおすすめの演歌の名曲~女性歌手編
- 【2026】高音が魅力的な男性歌手のオススメ演歌
- 大人の魅力あふれる50代の女性演歌歌手まとめ【2026】
【2026】歌うのが難しい演歌~女性歌手編(1〜10)
天城越え石川さゆり

恐らく演歌というジャンルの中でも特に有名な曲の一つ、と言っても過言ではないでしょう。
石川さゆりさんが1986年にリリースした『天城越え』は第28回日本レコード大賞の金賞受賞曲でもあり、NHK紅白歌合戦では石川さんのもう一つの代表曲『津軽海峡・冬景色』と交互に歌っていることもあって国民的な認知度は高く、カラオケでも大人気の名曲です。
とはいえこの曲、実際に歌ってみれば分かりますが簡単に歌いこなせるものではなく、Aメロにおける淡々とした歌唱から盛り上がるサビとのコントラストを際立たせる音程の上下の激しさ、ゆったりとしたテンポだからこその伸びやかなビブラートやこぶしをきかせた歌唱など、演歌特有のテクニックも当然ながら要求されますね。
強烈な恨み節で女の情念が見事な日本語で描かれた歌詞をしっかりと読みこんで、自分なりの表現で『天城越え』を再現してみてください!
無言坂香西かおり

香西かおりさんが1993年にリリースした『無言坂』は、同年のレコード大賞を受賞してNHK紅白歌合戦では数回にわたって披露された代表曲の一つであり平成初期の演歌の名曲ですね。
久世光彦さんが別名義で作詞、作曲はあの玉置浩二さんが担当したことでも知られています。
久世さんの出身地である富山県富山市の坂をテーマとしているご当地ソングで、玉置さんによるメロディは王道の演歌というよりはどこか都会的で洗練されているというのも興味深いですよね。
香西さんはさらりと歌いこなしているように聞こえますが、実際にカラオケなどで歌ってみるとかなり難易度の高い楽曲です。
幅広い音域はもちろん、丁寧に言葉をつむいでいくAメロのリズムなど細やかな技術が要求されますから、うまく歌いこなせればあなたの歌のレベルは格段に上達するはず。
伸びやかな高音のサビを、あくまで力み過ぎずに歌うというのもポイントですね!
越冬つばめ森昌子

聴けば一発で覚えてしまう擬音語を使ったサビを聴けば、多くの人が一度は耳にしたことがあると感じるでしょう。
森昌子さんの美しくもどこか切ないハイトーンボーカルが際立つ名曲『越冬つばめ』は、演歌歌手としての彼女のキャリアの中でも代表曲の一つと言える名曲です。
第25回日本レコード大賞最優秀歌唱賞の受賞、第34回NHK紅白歌合戦においても披露されたことを懐かしく思い出される世代の方も多いはず。
そんな名曲『越冬つばめ』ですが、カラオケで歌うには正直言って難易度が高いです。
森さんの澄み切った歌声で歌われるメロディは全体的にキーが非常に高く、伸びやかなロングトーンも慣れないうちは息が続かないのですよね。
演歌というジャンルながら演歌特有のこぶしを効かせて情念たっぷりに歌う、というタイプとは趣が異なるため、切ないメロディを素直に歌うように心がけるといいでしょう。
また高音が苦手、という方はキーを下げて練習してみることをおすすめします。
じょんがら女節長山洋子

大々的にフィーチャーされた津軽三味線の音色が特徴的なこちらの『じょんから女節』は、純邦楽的な要素と演歌やポップス、ロックなどが見事に融合したまさに日本ならではの名曲です。
元々はアイドル歌手としてデビューを果たし、本格的に演歌歌手としての活動以降もポップスや歌謡曲など幅広く歌いこなす長山洋子さんならではの楽曲と言えましょう。
長山さん自身が自らが津軽三味線を立ち弾きして歌う姿も最高にかっこいい大ヒット曲ですが、歌唱という面においても決して簡単に歌いこなせる楽曲ではないですし、幅広い音域などクリアすべき点は多くあるのですね。
王道の演歌節ながら先述したようにポップスやロック的なアップテンポのビートの楽曲ですから、ゆったりとした演歌に慣れている方には特に難しく感じるかもしれません。
逆に演歌的な歌唱に慣れていない方は、情感たっぷりの歌いまわしを最初はあまり意識せずにロックなどを歌うつもりで挑戦してみるのもいいですよ。
あなたなりの『じょんから女節』を模索しつつノリノリで歌いこなしてくださいね!
鳰の湖丘みどり

鳰の湖、という言葉を目にしても何と読んでいいのか分からない方も多いかもしれませんね。
「におのうみ」と読み、実はあの琵琶湖の別名なのですよ。
そんな『鳰の湖』を曲名とするこちらの楽曲は、2018年に人気演歌歌手の丘みどりさんがリリースした通算9枚目のシングルです。
平成後期の演歌の名曲であり、第69回NHK紅白歌合戦で披露されたことを覚えている方もいるでしょう。
王道の演歌らしい高い歌唱力を要求される楽曲ですが、特に注意してほしいのが幅広い音域という点でしょう。
Aメロに登場する最低音をはっきりと明瞭に歌うのは、ある意味高音を出すより難しいですから重点的に練習してみてください。
全体的な音域自体はそこまで高いものではないですから、低い音とサビの高音とのコントラストを意識して歌うと表現力のアップも期待できますよ!
おんな港町八代亜紀

演歌や歌謡曲というジャンルのみならず、ジャズにブルースといった分野においても素晴らしい功績を遺した偉大な歌手、八代亜紀さん。
八代さんが歌った名曲たちはカラオケでの人気も非常に高いものばかりですが、抜群の歌唱力と表現力、天性のハスキーな歌声で歌われる楽曲は実際に歌ってみると一筋縄ではいかないものばかりですよね。
今回は1977年にリリース、第28回NHK紅白歌合戦でも披露された人気曲『おんな港町』を紹介します。
当時20代の八代さんの歌唱はパワフルで艶っぽく、ばっちり歌いこなせたらカラオケ仲間からの拍手喝采は間違いないですね。
全体的に音域は高めでビブラートの多用、特にAメロにおけるリズミカルな歌いまわしなど難しいポイントは多いです。
楽曲自体が演歌と歌謡曲の間をいくような作風で、通常の演歌とは違うファンキーなリズムに乗って歌うことは、むしろ王道の演歌に慣れている方であればこそ難しいものでしょう。
軽やかなリズムと伸びやかな歌唱、このどちらもクリアできるようにパートごとに何度も練習してみてくださいね。
女がひとり藤あや子

昭和の終りごろにデビューを果たし、平成と令和を駆け抜けて今もバリバリの現役として活躍する人気演歌歌手の藤あや子さん。
カラオケでも人気の名曲を多数持つ藤さんですが、今回紹介している楽曲『女がひとり』は、北島三郎さんの名曲のカバーで藤さんのデビュー35周年を記念して2023年にリリースされたシングル曲です。
原曲の素晴らしさは言うまでもないですが、藤さんバージョンを聴けば分かるように艶やかな歌唱で丁寧に歌い上げる彼女にぴったりの曲なのですよね。
王道の演歌曲で一聴するとそれほど難しくはないように感じますが、音程の上下が非常に激しく低音と高音をスムーズに行き来するには慣れと練習が必要ですね。
ゆったりとした4分の3拍子、つまりワルツのリズムを感じながら伸びやかに、そして滑らかに歌うことも意識してみてください。