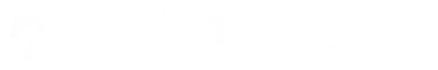紫陽花の雑学。アジサイにまつわる豆知識まとめ
梅雨の時期になると公園や街中、お寺などでよく見かけるようになるアジサイ。
青や紫、赤色などさまざまな色があって、雨に打たれた姿に風情を感じる方も多いと思います。
この記事では、そんな初夏の風物詩であるアジサイの雑学を一挙に紹介していきますね!
アジサイの構造や名前の由来、花の色についてなど、さまざまな視点から情報を集めましたので、この記事がアジサイについて深く知るキッカケになればうれしいです。
この記事をご覧いただいた後は、ぜひ本物のアジサイを観察してみてくださいね!
紫陽花の雑学。アジサイにまつわる豆知識まとめ(1〜10)
日光が苦手
梅雨の時期になると一斉に美しく咲き誇るアジサイですが、実は直射日光が苦手だとご存じでしたか?
アジサイは、水を吸収し、風通しの良い場所を好む植物。
あまり強い日光を浴び続けると、葉焼けを起こしたり、水分不足による生育不良を引き起こしてしまうのです。
そのため、屋内に置く場合は、西日や直射日光が長時間当たる場所を避け、屋外で植え付ける場合は木や塀の陰になる場所を選んでくださいね!
お寺で育てられていることが多いのには理由がある
「アジサイ寺」という言葉がよく聞かれるほど、アジサイが植えられたお寺って多いですよね。
どうして古くからお寺にはアジサイが欠かせない存在だったのでしょうか。
アジサイは、とくに手をかけずに育ち、手入れがしやすい植物。
医療技術が発達していなかった時代、季節の変わり目で亡くなる人が多い6月に、仏花として調達しやすかったということが考えられます。
また、4つの花弁を持つことから「4=死」を象徴するという説や、仏教と関わりの深い甘茶に関係していたという説もあります。
ガクアジサイの装飾花はひっくり返る
アジサイには色鮮やかな花びらで咲き誇るイメージがありませんか?
実は一般的にアジサイの花びらと思われている部分は、花ではありません。
花びらを囲む一番外側の器官で、装飾花と呼ばれています。
装飾花の中心にあるつぶつぶした部分が花の部分にあたりますよ。
ガクアジサイの装飾花が鮮やかになる理由として、蜂など虫をおびき寄せて受粉させる目的があるそうです。
目的が達成され、中心部分の花に種ができると装飾花はひっくり返ります。
その理由はできた種を遠くに飛ばすためにじゃまにならないようにだそうです。
アジサイの見た目のきれいな姿から想像ができないぐらい、戦略的な理由ですね。
紫陽花の雑学。アジサイにまつわる豆知識まとめ(11〜20)
アジサイは夏の季語
俳句にある決まりごとといえば、五七五であること、そして季語を含むことです。
そんな俳句を扱った大人気バラエティー番組『プレバト!!』は、厳しくも丁寧な解説が人気を集めていますよね。
ところで、アジサイはいつの季語として扱われているかご存じですか?
俳句の季語は旧暦で設定されていることが多く、その中でアジサイは夏の季語として扱われています。
もっと細かく分類して「仲夏」の季語とすることも。
アジサイを使って俳句を作るときは、あてられた季節を意識しながら作るのがいいかもしれませんね。
アンティークカラーに変化するアジサイを「秋色アジサイ」という
アジサイの色というと、どんな色を思い浮かべるでしょうか?
落ち着いた紫や青色、しとしとと降る雨を明るく照らすようなピンクや白色。
どの色もその景色に合った趣があっていいものですよね。
そんな中で、花が咲いて、季節がめぐるのに合わせて渋いアンティークカラーに変化するアジサイがあるんです!
めずらしい種類にも思えますが、すでに生花店でも販売されています。
アンティークカラーにするのは難易度が高いそうですが、できた際にはその姿でぜひ飾ってみてはいかがでしょうか。
花びらなどが緑に変色する「アジサイ葉化病」という病気にかかることがある
七変化するその色から園芸会では愛好者も多いアジサイ。
そんなアジサイには「アジサイ葉化病」という、花やガクが緑色になってしまう病気があるんです。
ファイトプラズマという微生物が原因で起こる病害で、治療法はありません。
そのため、病気にかかってしまうと枯れていきます。
もし、そばに別のアジサイの株がある場合は、そちらに感染が広がる恐れもあるため、感染がわかったら病気の株はすぐによけるようにしましょう。
全ての株に影響が出ないように、日々の観察が大切ですよ!
アジサイを使った金運アップのおまじないがある
アジサイに金運アップのご利益があることをご存じでしょうか?
蜂の巣を縁起物として軒下や室内に飾ったことが由来です。
蜂の黄色はお金を連想し、働き者で繁殖力も強いので商売繫盛の象徴だったそうですよ。
そしてアジサイの花の作りと蜂の巣の作りが似ているところから、蜂の巣の代わりに飾られるようになりました。
6月の6の付く日や夏至、土用の丑の日に玄関などにつるすと、金運アップが期待できるそうです。
とくに6月26日は効果が一番高い日とされていますよ。