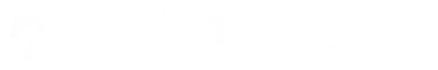紫陽花の雑学。アジサイにまつわる豆知識まとめ
梅雨の時期になると公園や街中、お寺などでよく見かけるようになるアジサイ。
青や紫、赤色などさまざまな色があって、雨に打たれた姿に風情を感じる方も多いと思います。
この記事では、そんな初夏の風物詩であるアジサイの雑学を一挙に紹介していきますね!
アジサイの構造や名前の由来、花の色についてなど、さまざまな視点から情報を集めましたので、この記事がアジサイについて深く知るキッカケになればうれしいです。
この記事をご覧いただいた後は、ぜひ本物のアジサイを観察してみてくださいね!
紫陽花の雑学。アジサイにまつわる豆知識まとめ(11〜20)
土のpHによって花の色が変わる
赤、青、紫、ピンクなどいろいろな色の花を咲かせるアジサイ。
色が変わることから「移り気」「七変化」といった花言葉もあるほどですが、どうして花の色が変化するのでしょうか。
アジサイは、花に含まれるアントシアニンと、土壌に含まれるアルミニウムの化学反応によって色が変化します。
そのため、土壌が酸性であるほどアルミニウムが溶けやすく、青色に傾く傾向があるのだそう。
他にも品種の特性や土壌の水分量、リン酸含有量などいろんな要素に反応するそうで、その奥深さも魅力の一つかもしれませんね。
日本原産の植物である
6月ごろになると、青色や白色やピンク色などさまざまな色で楽しませてくれるアジサイ。
品種も色も豊富なアジサイですが、実は日本が原産国なんです。
ちなみに、江戸時代に来日していたドイツ人医師のシーボルトが、ヨーロッパにアジサイなどいろいろな植物を持ち帰って品種改良が進み、現在のようにバラエティーに富んだ西洋産アジサイが誕生したそうです。
その後、日本に逆輸入されました。
ちなみにシーボルトが書いた本の中で、西洋アジサイをハイドランジアオタクサと表記されています。
ハイドランジアは西洋アジサイで、オタクサはシーボルトの日本人の妻の愛称から来ているそうですよ。
アジサイを「紫陽花」と書くのは勘違いがキッカケ
日本語ではアジサイを紫陽花と書きますよね。
実は、勘違いから紫陽花と書くようになったそうですよ。
平安時代の中期の歌人である源順が、当時の中国の詩を日本に紹介した際に間違った解釈をしてしまいました。
当時の中国で活躍していた歌人の詩に出てくる紫陽花を、アジサイだと思い込んでしまったそうです。
アジサイに紫陽花の漢字をあててしまったので、そのまま日本で定着したそうですよ。
ちなみに、中国の詩の中に出てくる紫陽花は、いまだに何の花なのか判明していません。
大きく分けて手まり咲き、ガク咲きの2種類がある
アジサイにはいろいろな種類があり、大きく2種類に分けられるそうです。
アジサイは装飾花と両性花の2つの部分で構成されています。
実はアジサイの花びらのように見える部分が装飾花になり、花びらを囲む一番外側の器官です。
装飾花の中央にあるのが、花の部分で両性花だそうですよ。
つぶつぶとした両性花を取り囲むように装飾花が縁取っているのがガク咲きと呼ばれています。
ガク咲きを品種改良したのが手まり咲きで、両性花がほとんどありません。
手まりのように装飾花が丸く半球状に咲くのが特徴です。
梅雨の時期のアジサイシーズンに、アジサイの違いを探してみるのも面白そうですね。
真夏に咲く種類のアジサイもある
梅雨の時期に咲く花というイメージの強いアジサイですが、中には真夏に咲く種類もありますよ。
タマアジサイは、一般的なアジサイが終わる7月頃から秋まで花を咲かせます。
名前の由来になった玉のようなツボミも愛らしい魅力の一つ。
また7月から9月にかけて花が咲くノリウツギは円すい形の花房を持ち、白い花が華やかです。
その名の通り三角すい状の花が爽やかなピラミッドアジサイも夏に咲きますよ。
涼しげな花々を眺めていると、夏の暑さを忘れさせてくれそうですね。
アジサイの語源は「青いがたくさん集まっている」という「集真藍」
ジメジメと雨が降る6月の風物詩としても親しまれているアジサイ。
道端などにも植えてあることが多いので、目にする機会も多いですよね。
日本が原産であるアジサイの語源は、あづさいからきています。
あづさいは集真藍と書きますが、藍で染めたような小さな花が集まったという意味があるそうです。
ちなみに、藍色とは少し緑がかった青色のことをさしますよ。
アジサイは土壌の成分の違いで、青色や紫色などになる植物です。
土壌の成分が青色なら酸性、紫色やピンク色ならアルカリ性を示します。
このことから、本来日本の土壌は酸性だったこともわかりますね。
紫陽花の雑学。アジサイにまつわる豆知識まとめ(21〜30)
フラワー・オブ・ザ・イヤーを受賞したアジサイがある
アジサイというと、主に鉢植えや地植えなどで鑑賞されることが多いのですが、ジャパンフラワーセレクションにて、フラワー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたことも何度かあります。
たとえば、2011年に鉢物部門で最優秀賞に輝いたのは二色の月虹という品種で、咲き進むにつれてがく型から徐々に手まり型に変わっていくそうです。
また、万華鏡や銀河など、島根県産のアジサイも高く評価され、フラワー・オブ・ザ・イヤーに選ばれたことがあります。