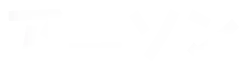【クセになる】変拍子が使われているアニソンまとめ
まずはめちゃくちゃ簡単に変拍子について説明をします。
みなさんがよく耳にするJ-POPなどの音楽は、ざっくりと表現しますが基本的には4拍子。
曲に合わせて手拍子を4回すると、メロディーなんかとそのリズムがループするみたいに合います。
が、変拍子は合いません。
「あれ、いつのまにサビに入ったの?」「ノリノリだったのにタイミングがいきなりずれてびっくりした」などと混乱してしまうビート……この体験がね、聴いているうちクセになっちゃうんですよ。
今回は変拍子が登場するアニソン特集です。
ぜひ最後までお付き合いください。
- 【変拍子の魅力】5拍子が使われている曲まとめ
- 【変拍子の魅力】7拍子が使われている曲まとめ
- 魅惑の変拍子。奇数拍子や複雑なリズムを持つ不思議な音楽
- 【燃える】テンションが上がる熱いアニソン集
- 【アニソン×ロック】ロックバンドが歌うアニメソングまとめ
- 【三拍子の名曲】あのヒットソングも!?邦楽&洋楽の人気曲を厳選
- 小学生に人気のアニソン。話題のアニメ主題歌・挿入歌
- 【神曲集結】アニメ好きが選ぶかっこいいアニソン集
- もっと聴いて!アニソンの隠れた名曲集
- ボカロのアニソンまとめ【OP・ED主題歌からカバー作品まで】
- 【懐かしい】30代におすすめなアニソン名曲、人気曲
- 子供におすすめのアニメ主題歌。一度は聴きたいアニメソングの名曲
- 転調が気持ちいい曲。自然&印象が変わるJ-POPや邦楽の名曲
【クセになる】変拍子が使われているアニソンまとめ(11〜20)
夕焼けといっしょにSTARTails☆

テレビアニメ『スロウスタート』の主要キャラクターを務める声優4人による音楽ユニット・STARTails☆の楽曲。
同作品のオープニングテーマ『ne! ne! ne!』のカップリング曲として発表された楽曲で、オルゴールやアコーディオンの音色を使ったイントロがあたたかい気持ちにさせてくれますよね。
Aメロで突然5拍子になるトリッキーなアレンジでありながら、キュートな歌声を聴いているとこれがベストと感じさせられる方も多いのではないでしょうか。
やわらかい雰囲気でありながら実はスリリングなビートが展開している、変拍子を意識して聴いてほしいアニソンです。
その声が地図になる早見沙織

90年代生まれの声優陣の中でもトップクラスの実力と人気を誇り、多くの有名作品に出演している早見沙織さん。
2022年の5月、早見さんが声優を目指すきっかけとなった名作映画『ローマの休日』において、オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えを担当して話題を呼んだことも記憶に新しいですね。
そんな早見さんは声優アーティストとしても活動しており、その歌唱力は業界内においても高い評価を得ています。
今回紹介している楽曲『その声が地図になる』は2016年に両A面シングルとして発表されたセカンド・シングル曲で、本人が主演を務めたテレビアニメ『赤髪の白雪姫』のオープニングテーマとして起用されています。
早見さん自身も作詞と作曲に参加したこの楽曲、アップテンポな8ビートを基調としたデビュー曲『やさしい希望』と比べても変わったリズムが採用されていることに気付きませんか?
サビは通常の4拍子ですが、イントロは5拍子でAメロとBメロが3拍子というプログレッシブな展開を見せ、シンフォニックでクラシカルな要素も含む一筋縄ではいかない楽曲となっているのですね。
5拍子を使ったポップスはあまり見られませんし、実際に聴きながらリズムを取ってもらえれば、なかなか挑戦的なアレンジであることが理解できるはず。
拍子が変われば当然メロディ・ラインを追うことも難しくなりますが、伸びやかな歌唱で難なく歌いこなす早見さんのボーカリストとしての実力にも改めて驚かされます!
キグルミ惑星柊(CV;高垣彩陽)

テレビアニメ『はなまる幼稚園』の登場人物・柊による、アニメ第2話のエンディングテーマとして起用された楽曲。
声優・高垣彩陽さんによるキャラクターを維持したキュートな歌声と、日本のロックシーンにおける凄腕ミュージシャンによる重厚なアンサンブルがテンションを上げてくれますよね。
7分弱の楽曲に重厚かつクラシカルなアレンジが盛り込まれており、メタル然とした変拍子が楽曲の個性をさらに際立たせています。
アニソンというイメージで聴くと衝撃を受けることまちがいなしの壮大なナンバーです。
THE LAST PARTY10年黒組

テレビアニメ『悪魔のリドル』の作品内に登場する特別クラス・10年黒組の楽曲。
ピアノとストリングスによる奥行きとノイジーなロックサウンドの融合がテンションを上げてくれるナンバーです。
イントロからいきなりスリリングな変拍子のアレンジが盛り込まれており、疾走感のあるメロディーに進行していくアレンジは難解でありながら独特なポップ性を生み出していますよね。
畳みかけるようなボーカルワークと間奏での複雑なビートがテンションを上げてくれる、息つくひまさえ与えないヒステリックなアニソンです。
RoundaboutYES

プログレッシブロックの代表格として知られ、世界中にファンを持つイギリス出身のロックバンド・イエスの楽曲。
1971年に発表された楽曲でありながら、テレビアニメ『ジョジョの奇妙な冒険』のエンディングテーマとして起用されたことから話題を集めました。
アコースティックギターによるスパニッシュな空気感やグルービーなベースラインなど聴きどころが満載で、曲中にちりばめられた変拍子のアレンジが緊張感をさらに高めています。
1970年代の楽曲とは思えないハイレベルなアンサンブルが秀逸な、アニメとの親和性も高いテクニカルなナンバーです。
産巣日の時戸松遥

声優として数多くの作品で活躍してきたシンガー・戸松遥さんの3作目のシングル曲。
テレビアニメ『かんなぎ』エンディングテーマとして起用された楽曲で、幻想的なアンサンブルによる荘厳な空気感が心地いいですよね。
三拍子を基本としながらもメロディーの流れに沿った不規則な変拍子のアレンジが、歌声とともに独特の浮遊感を生み出していますよね。
奥行きのあるコーラスが変拍子の違和感すら感じさせない、神々しさすら感じられるナンバーです。
【クセになる】変拍子が使われているアニソンまとめ(21〜30)
美しい鰭スピッツ

流れに逆らう強さと美しさを歌った楽曲は、7拍子の変拍子を巧みに織り込んだスピッツらしい透明感あふれる名曲です。
Aメロ部分で採用された7拍子はさりげない形で盛り込まれていますが、スピッツの高度なバンドアンサンブル能力ならではのものですし、聴き手を前へ引っ張る独特な浮遊感と緊張感を演出しています。
2023年4月に公開された『名探偵コナン 黒鉄の魚影』の主題歌として話題を集めた本作は、通算46枚目のシングルでありオリコン週間ランキング1位を獲得しました。
逆境に立ち向かう勇気や自分らしさを貫く大切さをテーマにした歌詞は、人生の転機を迎えている方や新しい挑戦を始める方におすすめの楽曲ですよ!