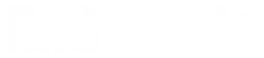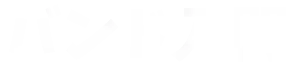行政書士が教える。音楽制作における著作権の基礎知識
前回の記事で著作権についての基本的なことを取り上げましたが、今回は音楽制作分野に関係する著作権について、もう少し詳細にその内容を見ていこうと思います。
- 作曲初心者も必見!定番のコード進行まとめ
- 秋元康プロデュースの名曲|アイドルソングから感動のヒット曲まで一挙紹介!
- ピアノ伴奏パターン|伴奏付けや弾き語りに役立つアレンジをピックアップ
- 【ピアノ初級楽譜】最新ヒットソングの簡単アレンジをピックアップ
- 【最新】保育士試験ピアノ課題曲|2023年度&過去の課題曲で徹底対策!
- 【ピアノ楽譜】憧れのクラシック|著作権フリーの作品を一挙紹介
- 【学べる】勉強になるボカロ曲をまとめてご紹介!
- 【作曲】定番コード進行を使っている有名曲まとめ【耳コピ】
- 【邦楽】新感覚!マッシュアップ作品まとめ
- 【ディズニー】心揺さぶる名曲を楽譜付きで紹介~初級・中級・上級~
- コードでピアノ弾き語りに挑戦したい方必見!懐メロ~最新曲まで一挙紹介
- 【乃木坂46】ピアノ演奏にピッタリの人気曲を楽譜とともに紹介!
- 【ピアノ無料楽譜】初心者向け!今すぐダウンロード可能な作品を厳選
演奏者や歌手に関係する権利
歌や曲を歌ったり演奏したりすることを「実演」といい、その歌手や演奏者、さらにその実演を指揮する指揮者などを「実演家」といいます。
歌詞やメロディーといった著作物を創作したわけではないので著作権は付与されませんが、でもその著作物を表現し広めるために重要な役割を担っていますので、「著作隣接権」という権利が与えられるようになっています。
実演家に関係する主な著作隣接権には次のものがあります。
- 録音権・録画権(法第91条)
- 送信可能化権(法第92条の2)
- 他には放送権、譲渡権、貸与権があり、著作隣接権ではありませんが放送などに対する二次使用料請求権、レンタルや再放送などに関する報酬請求権などもあります
ちなみに、流通するCDを制作する際には実演家の著作隣接権は原盤権者に譲渡することが一般的ですので、歌手やバンド自身がこの権利行使することはありません。
(譲渡する代わりに、原盤権者から印税を受け取ります)
「録音権・録画権」とは、文字通り録音・録画する権利で、実演家の実演を録音・録画するには実演家の許諾が必要で、勝手に行うことはできない、ということです。
なお、この権利は、実演家が許諾して録音・録画されたものを複製することも含みますので、例えばAというバンドのファンがAのライブを動画撮影し、その動画や動画内の音源をコピーして他のファンに配るという場合にはバンドAの許諾が必要です。
もちろん、コピーする曲(歌詞・メロディー)の著作権者からも許諾が必要です。
著作権の支分権である複製権と似ていますが、あらゆる再製が対象となる複製権とは異なり、こちらは録音または録画に限られる点に要注意です。
例えば、モノマネタレントBさんが、歌手Cさんの歌唱を歌マネした場合はCさんの歌唱(実演)の複製ですが、録音でも録画でもないため、CさんはBさんに対して権利侵害だという主張はできません。
「送信可能化権」については、作詞者などに付与される公衆送信権の中で取り上げていますのでそちらを参照してください。
ただし、実演家の許諾を得て「録画」された実演を送信可能化する場合には権利が働きません。
(「録音」の場合は権利を主張できます)
実演家だけが持つ人格権
実演家にも、著作者と同様に人格権(実演家人格権)が与えられますが、著作者と同じではなく氏名表示権と同一性保持権のみとなり、さらにその範囲も狭まっています。
特に同一性保持権については、著作者であれば「意に反する改変」について禁止する権利がありますが、実演家においては「名誉又は声望を害する場合」に限定されます。
なお、この実演家人格権も著作者人格権と同様、譲渡や相続ができません。
(法第101条の2)
原盤制作者に関係する権利
スタジオ使用料やミュージシャンのギャラなどの経費を支払って楽曲を録音し、レコード原盤(マスターテープ)を作成した者(実際には会社であることが多いですが)には「レコード製作者」(法第89条第2項)として著作隣接権が与えられます。
音楽業界では、このレコード製作者としての著作隣接権と二次使用料請求権、レンタルなどに対する報酬請求権、私的録音録画補償金請求権、さらにマスターテープ制作時に実演家から譲渡される実演家の著作隣接権(実演家に印税を払うという義務付き)を含めて「原盤権」と呼ぶことが多いです。
通常、レコード製作者となるのは以下の者(会社)が多いです。
- CDを発売するレコード会社
- 音楽出版社(※)
- アーティストの所属事務所(※)
なお、(※)の場合はCDをプレスして流通させる機能がないため、その機能を持つレコード会社に原盤を譲渡または供給(ライセンス)することが多いです。
レコード製作者に関係する主な著作隣接権には次のものがあります。
- 複製権(法第96条)
- 送信可能化権(法第96条の2)
- 他に譲渡権、貸与権等があり、さらに著作隣接権ではありませんが二次使用料請求権、報酬請求権、私的録音録画補償金請求権という権利もあります。
「複製権」とは著作権者の複製権と同様、マスターテープを複製(コピー)する権利で、この権利によってマスターテープを複製・プレスしてCDを大量生産したり、ネット配信したり、音源をCMに使ったりができます。
なお、この複製とはマスターテープを複製するだけでなく、そのマスターテープに録音されている音を再生して別の媒体に録音することも含まれますので、次の例のようにCDや配信音源をそのまま利用(録音)する場合は原盤権者の許諾が必要です。
- CDに収録されている音をPCに取り込んで結婚式で上映する動画のBGMとして使用する
- ダンス大会でCD音源に合わせて踊った模様をビデオ撮影し、後日それを販売する
- YouTubeやニコニコ動画に音源をそのままアップする
「送信可能化権」は実演家のそれと同様です。
権利者としての自覚を持とう
以上、長々と音楽制作に関するさまざまな著作権について取り上げてきましたが、いかがでしょうか。
意外と権利が細かく、また関係する権利者が多いことに驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
著作権とは実は結構複雑で難解な権利だとは思いますが、音楽制作においては多くの人が権利者となり得ますので、音楽制作に関わったら自分がどのような権利を持つことになるのかを知っておくことはとても重要です。
ライタープロフィール
![]()
行政書士
遠藤正樹
行政書士。
ビーンズ行政書士事務所代表。
都内の音楽専門学校を卒業後、音楽制作会社所属のマニピュレーター兼雑用係として活動後、独立。
フリーランスの作曲・編曲家として主にゲーム系音楽の作編曲に携わりつつ、同時にウェブデザイナーとしても活動。
その後行政書士登録し、著作権だけでなく各種契約書の作成・リーガルチェックを中心に奮闘している毎日です。
著作権に関するネタを発信するブログ『著作権のネタ帳』も運営し、一人でも多くの人に身近な権利として意識してもらえるよう啓蒙活動を続けています。
ブログ『著作権のネタ帳』:
ウェブサイト:http://beans-g.jp
Twitter:beansgyosei
Facebook:beansgyosei