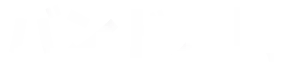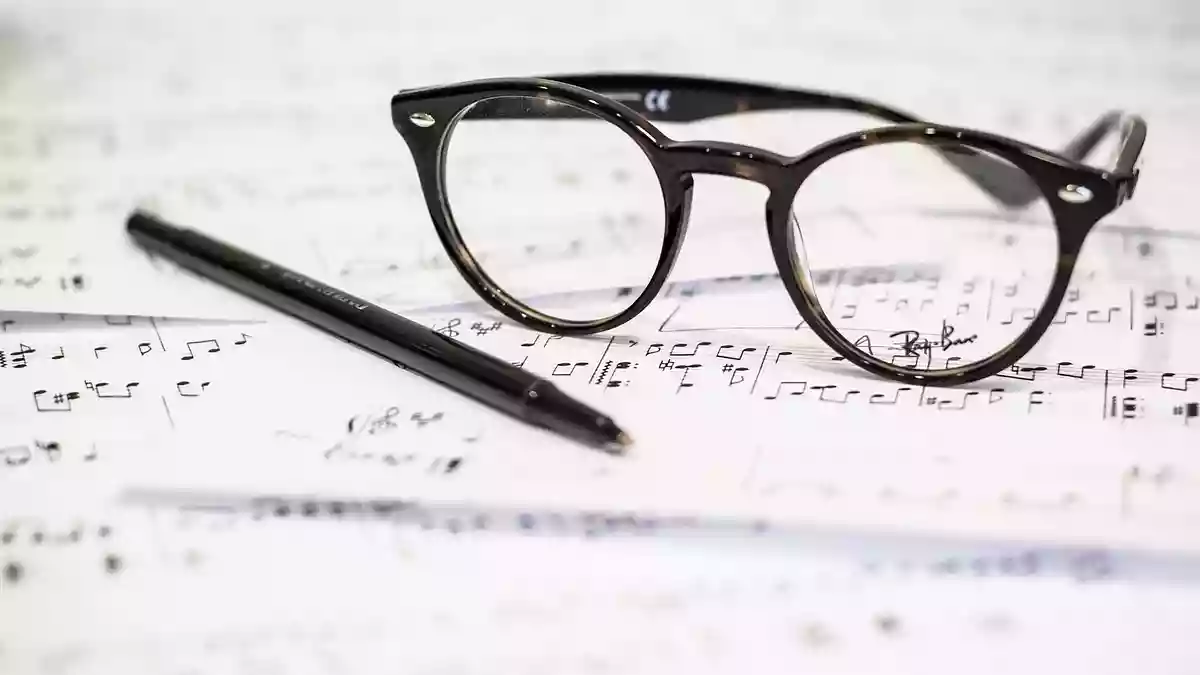行政書士が教える。音楽制作における著作権の基礎知識
前回の記事で著作権についての基本的なことを取り上げましたが、今回は音楽制作分野に関係する著作権について、もう少し詳細にその内容を見ていこうと思います。
作詞者、作曲者、編曲者に関係する権利
前回の記事で、著作権とは複数の権利(支分権)をまとめたものだと説明しましたが、作詞や作曲、そして編曲を行った者に関係する支分権は次のものがあります。
- 複製権(法第21条)
- 上演権・演奏権(法第22条)
- 公衆送信権(法第23条)
- 譲渡権(法第26条の2)
- 貸与権(法第26条の3)
- 翻訳権、翻案権等(法第27条)
- 二次的著作物の利用権(法第28条) (※著作権の支分権としては、他に展示権や口述権、頒布権があります)
この中で特に大きく関わるのが「複製権」「上演権・演奏権」「公衆送信権」そして「翻訳権、翻案権等」ですので、これらについては少し具体的に考えていきたいと思います。
なお、編曲者が創作したものは、作曲者の著作物(メロディー)を基に創作された二次的著作物という扱いになり、編曲者はその二次的著作物に対して著作者として著作権を有します。
ただ、CDを制作する際は原盤制作者から編曲者にギャラが支払われますが、その支払をもって原盤権者に権利が移っている(買い取っている)と判断されることが多いため、編曲者が権利行使できるケースというのは少ないのが実情です。
これぞコピーライト!
な複製権
著作権のことを英語ではcopyrightと言うことからも分かるとおり、著作権とはまさに「複製(copy)する権利(right)」が基本となっていることから、数ある著作者の権利の中でもこの複製権はとても重要です。
音楽で複製と言えば、歌詞やメロディーをそのまま使用するというケースが想定されると思いますが、他にも次のような行為は複製となります。
- メロディーを楽器で演奏して録音する
- 鼻歌で歌ったメロディーを楽譜にする
- 歌詞を書いた紙をカメラで撮影する
つまり「有形的に再製すること」(法第2条第1項第15号)はすべて複製です。
文字通り、演奏する権利である演奏権
歌詞とメロディーからなる音楽という著作物を公に演奏(歌唱、CDの再生を含む)できる権利です。
ここで「公に」という言葉が出てきましたが、これは著作権法には何度も出てくる言葉で、「公衆に直接見せ又は聞かせることを目的」にすることを言います。
なお、「公衆」とは一般的には少数・多数を問わず不特定の者を指しますが、著作権法においては特定多数も含みます。
つまり、街中の見ず知らずの1人(不特定)であっても、学校のクラスメート全員(特定多数)であっても「公衆」です。
逆に言えば「公衆」に該当しないのは特定少数の者ということですので、例えば5~6人が参加する有料セミナーでCDを再生することまでは権利者の権利は及びません。
ネット時代には欠かせない公衆送信権
公衆送信とは「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信~(略)~を行うことをいう」(法第2条第1項第7号の2)と定められていますが、これではよくわかりませんので簡単に言うと、「テレビやラジオ、有線放送などを利用して著作物を送信し広めること」ということです。
さらに、「公衆からの求めに応じ自動的に行うもの」を「自動公衆送信」とし、これには主にインターネット上での送信・配信が該当するのですが、ネットにつながれたサーバーに音楽をアップロードすることにより自動公衆送信できる状態にすることを「送信可能化」と言い、この送信可能化すること自体も公衆送信権の範囲内です。
つまり、他人の曲をネットにアップするには権利者の許諾が必要ということです。
これはホームページ、ブログ、動画サービスなどアップ先を問いません。
※YouTubeやニコニコ動画、アメブロなど一部のSNSサービスはJASRACと包括契約を結んでいるため、JASRACが管理する歌詞と楽曲については申請手続き不要でアップできます。
(対象となる具体的なサービスはこちらです)
ただし、あくまでアップが許されているのは歌詞と楽曲のみですので、後述する原盤権の関係から、市販CDや配信曲に収録されている音源を使う場合は、原盤権者の許諾が必要です。
形を変えるのが翻案権(編曲権)
法律上「翻訳権、翻案権等」という見出しが付いており、一見音楽には関係無いように感じられますが、実は大いに関係があります。
それが「編曲」で、条文中にも明記されていますから、ここでは分かりやすいよう編曲権と呼ぶことにします。
この編曲権、つまり編曲できる権利は権利者が持っているわけですから、他の人が無断で編曲することは編曲権の侵害ということです。
(なお、JASRACでは編曲権は扱いませんので、作曲者や音楽出版社などが権利者となります)
よく「カバー」と称して勝手に(無許諾で)原曲とは違うアレンジで演奏や録音することもあると思いますが、厳密に言えばダメなのです。
人格を保護する権利
著作者には、財産権としての著作権の他に、人格的利益の保護のために著作者人格権という権利も与えられます。
これも複数の権利をまとめた名称で、具体的には「公表権」「氏名表示権」「同一性保持権」の三つを指します。
「公表権」(法第18条)とは、未公表の著作物を「いつ」「どのように」公表するかどうかを決定できる権利です。
歌詞を書いてみたけど、それを公表するかどうかは書いた人が決める、ということです。
なお、すでに公表されている著作物については、この権利は働きません。
「氏名表示権」(法第19条)とは、著作物の著作者名として、本名やペンネーム、あるいは匿名など、どのような名前で表示するかを決めることができる権利です。
例えば、日本テレビ「24時間テレビ」のテーマ曲としておなじみの「サライ」。
作曲者は加山雄三さんであることはみなさんご存じだと思いますが、作曲名義としては「弾厚作」ですので、クレジット表示の際は「加山雄三」ではなく「弾厚作」と表示しなければなりません。
なお、著作者名は常に表示が必要なのではなく、表示を省略できる場合もあります。
(テレビ番組や商店街でのBGMなど、著作者の人格的利益を損なわない場合など)
「同一性保持権」(法第20条)とは、著作者の意思に反した改変などを禁止できる権利です。
一部の歌詞を変えて歌う「替え歌」だったり、メロディーが大きく変わるほどフェイクしまくっているような場合は、この同一性保持権の侵害となる場合があります。
また、この権利にはタイトルを変えないという権利も含まれますので「First Love」というタイトルの曲を勝手に「初恋」に変えて演奏などできません。
著作者人格権はこの3つの権利ですが、さらに著作者人格権の侵害とみなす場合があり、タイトルも歌詞も変えずにそのまま利用した場合であっても、それが著作者の名誉や声望を害する利用方法であるときです。
(法第113条第6項)
例えば、嫌煙家として有名な人の楽曲をタバコのCMで使うような場合が該当します。
なお、この著作者人格権でもっとも注意が必要な点は、著作権とは異なり「譲渡や放棄、相続ができない」(法第59条)ことです。
お互いが譲渡に合意していてしっかりと契約を取り交わしていても、それは無効となります。
演奏者や歌手に関係する権利
歌や曲を歌ったり演奏したりすることを「実演」といい、その歌手や演奏者、さらにその実演を指揮する指揮者などを「実演家」といいます。
歌詞やメロディーといった著作物を創作したわけではないので著作権は付与されませんが、でもその著作物を表現し広めるために重要な役割を担っていますので、「著作隣接権」という権利が与えられるようになっています。
実演家に関係する主な著作隣接権には次のものがあります。
- 録音権・録画権(法第91条)
- 送信可能化権(法第92条の2)
- 他には放送権、譲渡権、貸与権があり、著作隣接権ではありませんが放送などに対する二次使用料請求権、レンタルや再放送などに関する報酬請求権などもあります
ちなみに、流通するCDを制作する際には実演家の著作隣接権は原盤権者に譲渡することが一般的ですので、歌手やバンド自身がこの権利行使することはありません。
(譲渡する代わりに、原盤権者から印税を受け取ります)
「録音権・録画権」とは、文字通り録音・録画する権利で、実演家の実演を録音・録画するには実演家の許諾が必要で、勝手に行うことはできない、ということです。
なお、この権利は、実演家が許諾して録音・録画されたものを複製することも含みますので、例えばAというバンドのファンがAのライブを動画撮影し、その動画や動画内の音源をコピーして他のファンに配るという場合にはバンドAの許諾が必要です。
もちろん、コピーする曲(歌詞・メロディー)の著作権者からも許諾が必要です。
著作権の支分権である複製権と似ていますが、あらゆる再製が対象となる複製権とは異なり、こちらは録音または録画に限られる点に要注意です。
例えば、モノマネタレントBさんが、歌手Cさんの歌唱を歌マネした場合はCさんの歌唱(実演)の複製ですが、録音でも録画でもないため、CさんはBさんに対して権利侵害だという主張はできません。
「送信可能化権」については、作詞者などに付与される公衆送信権の中で取り上げていますのでそちらを参照してください。
ただし、実演家の許諾を得て「録画」された実演を送信可能化する場合には権利が働きません。
(「録音」の場合は権利を主張できます)
実演家だけが持つ人格権
実演家にも、著作者と同様に人格権(実演家人格権)が与えられますが、著作者と同じではなく氏名表示権と同一性保持権のみとなり、さらにその範囲も狭まっています。
特に同一性保持権については、著作者であれば「意に反する改変」について禁止する権利がありますが、実演家においては「名誉又は声望を害する場合」に限定されます。
なお、この実演家人格権も著作者人格権と同様、譲渡や相続ができません。
(法第101条の2)
原盤制作者に関係する権利
スタジオ使用料やミュージシャンのギャラなどの経費を支払って楽曲を録音し、レコード原盤(マスターテープ)を作成した者(実際には会社であることが多いですが)には「レコード製作者」(法第89条第2項)として著作隣接権が与えられます。
音楽業界では、このレコード製作者としての著作隣接権と二次使用料請求権、レンタルなどに対する報酬請求権、私的録音録画補償金請求権、さらにマスターテープ制作時に実演家から譲渡される実演家の著作隣接権(実演家に印税を払うという義務付き)を含めて「原盤権」と呼ぶことが多いです。
通常、レコード製作者となるのは以下の者(会社)が多いです。
- CDを発売するレコード会社
- 音楽出版社(※)
- アーティストの所属事務所(※)
なお、(※)の場合はCDをプレスして流通させる機能がないため、その機能を持つレコード会社に原盤を譲渡または供給(ライセンス)することが多いです。
レコード製作者に関係する主な著作隣接権には次のものがあります。
- 複製権(法第96条)
- 送信可能化権(法第96条の2)
- 他に譲渡権、貸与権等があり、さらに著作隣接権ではありませんが二次使用料請求権、報酬請求権、私的録音録画補償金請求権という権利もあります。
「複製権」とは著作権者の複製権と同様、マスターテープを複製(コピー)する権利で、この権利によってマスターテープを複製・プレスしてCDを大量生産したり、ネット配信したり、音源をCMに使ったりができます。
なお、この複製とはマスターテープを複製するだけでなく、そのマスターテープに録音されている音を再生して別の媒体に録音することも含まれますので、次の例のようにCDや配信音源をそのまま利用(録音)する場合は原盤権者の許諾が必要です。
- CDに収録されている音をPCに取り込んで結婚式で上映する動画のBGMとして使用する
- ダンス大会でCD音源に合わせて踊った模様をビデオ撮影し、後日それを販売する
- YouTubeやニコニコ動画に音源をそのままアップする
「送信可能化権」は実演家のそれと同様です。
権利者としての自覚を持とう
以上、長々と音楽制作に関するさまざまな著作権について取り上げてきましたが、いかがでしょうか。
意外と権利が細かく、また関係する権利者が多いことに驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
著作権とは実は結構複雑で難解な権利だとは思いますが、音楽制作においては多くの人が権利者となり得ますので、音楽制作に関わったら自分がどのような権利を持つことになるのかを知っておくことはとても重要です。