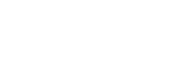【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ
洋楽や邦楽を問わず、エモやラウドといった形で紹介されるバンドをお好きな方であれば、一度は「ポストハードコア」なるジャンルを目にしたことがありますよね。
1970年代後半から始まったハードコアパンクを出自とするバンドたちの中で、既存のハードコアに収まりきらない独自の音を鳴らす面々が「ポストハードコア」と呼ばれるようになったのですが、さらにエモコアやスクリーモなどの派生ジャンルが生まれ、2000年代以降はより広い意味で使われており、定義付けが非常に難しいジャンルです。
今回の記事では、そんなポストハードコアの形成という意味で重要な役割を果たした、1980年代から1990年代にかけてデビューしたバンドを一挙紹介します!
- 【洋楽】ハードコアパンクの名曲・人気曲~入門編
- 【洋楽】90年代エモコアの名盤。まずは聴いてほしい1枚
- 【激しさと美しさの共存】日本のスクリーモ・ポストハードコアバンドまとめ
- 【2026】海外の人気タルコアバンドまとめ【初心者向け】
- 洋楽のおすすめスクリーモのバンド。海外の人気バンド
- ニューメタルの名曲。おすすめの人気曲
- 洋楽エモが聴きたければここから!海外のエモバンド一覧
- ハードコアパンクの名曲。おすすめの人気曲
- 根強い人気!洋楽のエモの名曲
- 【2026】メロコアの名曲。新旧の人気曲まとめ
- 邦楽のエモの名曲。おすすめの人気曲
- 【2026】日本のハードロックバンド。海外でも人気のバンドまとめ
- エモーショナルな楽曲から爽快な楽曲まで!平成の青春ソング
【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ(1〜10)
Rather Be DeadRefused
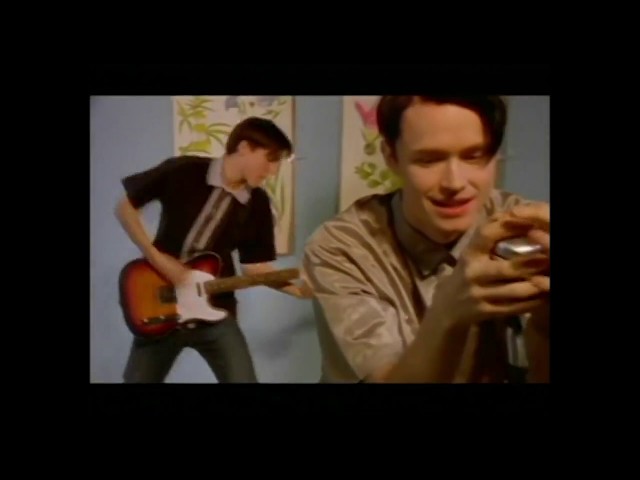
スウェーデンが世界に誇る伝説的なニュースクールハードコア~ポストハードコアバンド、リフューズド。
ザ・(インターナショナル)・ノイズ・コンスピラシィなど複数のバンドでも活躍するスウェーデンハードコアのカリスマ的な存在のフロントマン、デニス・リクセゼンさんを中心として1991年に結成されたリフューズドは、1998年に解散するまでに3枚のアルバムをリリース。
2010年代にはまさかの再結成を果たして奇跡的な来日が実現、2枚の新作アルバムも発表しています。
そんな彼ら、最初期はハードコアパンクの影響下にある荒々しい音を鳴らしていたのですが、1996年のセカンドアルバム『Songs to Fan the Flames of Discontent』からメタリックなギターが盛り込まれ、デニスさんのボーカルもより激しいシャウトへと変化、いわゆるニュースクールハードコアにおける傑作の誉れ高い名盤を生み出しました。
作品をリリースするごとにさまざまな音楽的実験を繰り返してきた彼らの集大成となったのが、1998年リリースの傑作サードアルバム『The Shape of Punk to Come』です。
インダストリアルやエレクトロニカにポストロック、ジャズなどの要素も大胆に導入された独創的なハードコアはまさに「ポストハードコア」であり、凡百のポストハードコアとは全く違う次元に達したフリーキーな音楽性は世界中の音楽ファンやミュージシャンたちに衝撃を与えたのです。
デニスさんは左派思想の持ち主でもあり、権力や資本主義に対する痛烈な批判といったテーマも掲げており、膨大な知識に裏打ちされたインテリジェンスな小説や映画からの引用なども彼ら独自の音楽性を特徴づけるものですね。
前述した再結成後の作品も素晴らしいものですから、合わせてチェック必須です!
NubTHE JESUS LIZARD

恐ろしいほどの緊張感、ひりついた空気が支配する強烈極まりない独自のヘヴィネスを追求し続けたザ・ジーザス・リザード。
テキサス出身のメンバーによって1987年に結成され、活動初期の段階でシカゴへと移住、あのニルヴァーナの『In Utero』を手掛けたことでも知られる名エンジニアのスティーヴ・アルビニさんと組んでインディーズシーンにおいて強烈な存在感を放ちます。
アメリカの著名なインディーズレーベル「Touch and Go」にてアルビニさんとともに発表した4枚のアルバムはどれもバンド独自の世界観が生み出した異形のヘビーサウンドが素晴らしく、同時に多くの人が楽しめるような内容とは言えない、まさに90年代アンダーグラウンドな音楽性です。
フロントマンのデヴィッド・ヨウさんによる狂気的なヴォーカル、ロック的なアプローチとは一線を画すポストパンクからの影響も感じさせる変則的なギタープレイ、グルーヴの中心としてサウンドを引っ張るベース、無機質なドラムスによるバンドアンサンブルは今聴いても衝撃的ですね。
メンバーのプレイヤーとしてのスキルも高く、スプリット盤をリリースしたニルヴァーナを始めとして多くのアーティストたちが影響を受けています。
メジャー進出後の2枚のアルバムは比較的聴きやすい作風へとシフトしていますが、それでもバンドの持つ狂気は変わらず、ミリオンセラーを出せるようなバンドではないというメンバー自身の言葉通りの音楽性を貫いたのです。
This Ain’t No PicnicMinutemen

アメリカはカリフォルニア州出身のミニットメンは、1980年の結成から5年程度の短い活動期間ながら後のポストハードコアやオルタナティブロックに影響を与え、まさにパンクやハードコアの次なる展開をいち早く提示していたバンドです。
2005年にはバンドのドキュメンタリー映画『WeJam Econo – The Story Of The Minutemen』が公開されていることからも分かるように、彼らがシーンに与えたインパクトは非常に大きなものだったのですね。
そんな彼らは80年代ハードコアシーンのカリスマ、ブラックフラッグのグレッグ・ギンさんが運営するレーベル「SSTレコーズ」にて1981年にデビューアルバム『The Punch Line』をリリースします。
一曲目からファンキーなギターのカッティングとうねるようなベースライン、しなやかなドラムスが織り成すトリオならではの隙間の多いアンサンブルから生まれる独自の楽曲にハードコアというイメージで作品を手にした方は思わず驚かれるのではないでしょうか。
独自のセンスと高い演奏技術を武器としてシーンにおいて知名度を上げていく彼らの集大成的なアルバムは、やはり1984年にリリースされた怒涛の4枚組という大作『Double Nickels on the Dime』でしょう!
ジャズやファンク、スポークンワードなどハードコアの枠内から大きく足を踏み外したような音楽性、社会問題に言語学など幅広いテーマを掲げた歌詞といった要素を内包した楽曲群はまさにミニットメン独自の音世界であり、1980年代のアメリカにインディーズシーンにおける素晴らしい偉業を成し遂げたのですね。
残念ながら1985年にフロントマンのD・ブーンさんが事故でこの世を去ってしまい、バンドは解散を余儀なくされてしまいます。
【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ(11〜20)
PorcelainThursday

今回の記事では2000年代以降のいわゆるスクリーモと呼ばれたバンドは取り上げていないのですが、その走りとも言えるサーズデイはポストハードコアという流れにおいても重要なバンドですから、00年代初頭のスクリーモを代表するという意味でも今回紹介させていただきます。
1997年にニュージャージーにて結成されたサーズデイは、初期のスクリーモの中ではザ・ユーズドやフィンチといったバンドよりも少し先輩格にあたる存在であり、記念すべきデビューアルバム『Waiting』が1999年に発表されていることも踏まえて、サーズデイの存在が90年代のアンダーグラウンドなポストハードコアと00年代以降の商業的にも大きな成功を収めるスクリーモシーンを繋いだといっても過言ではありません。
彼らの名をシーンに知らしめるのは名門エピタフレコーズにて発表した大傑作セカンド『Full Collapse』ですが、後にあのマイ・ケミカル・ロマンスを輩出したことでも知られている「Eyeball Records」よりリリースされた前述の『Waiting』を聴けば、ニューメタルが支配していた1990年代末期のアメリカのロックシーンの裏側で新たな可能性が芽生えていたことが理解できるはずです。
サウンドプロダクションや演奏能力はインディーズらしくまで稚拙ながら、フロントマンのジェフ・リックリーによる内省的な歌詞とナイーブなボーカルとスクリームが交差するコントラストはまさにスクリーモの走りですし、収録曲に『Ian Curtis』という楽曲があることからも分かるように、ニューウェーブなどのUKロックから影響を受けていることも注目すべき点でしょう。
ラウドでメタリックなスクリーモとは違う繊細なエモーションが渦巻くサーズデイの音世界もまた、ポストハードコアが生んだ素晴らしい可能性の一つであったと言えそうです。
FazerQuicksand
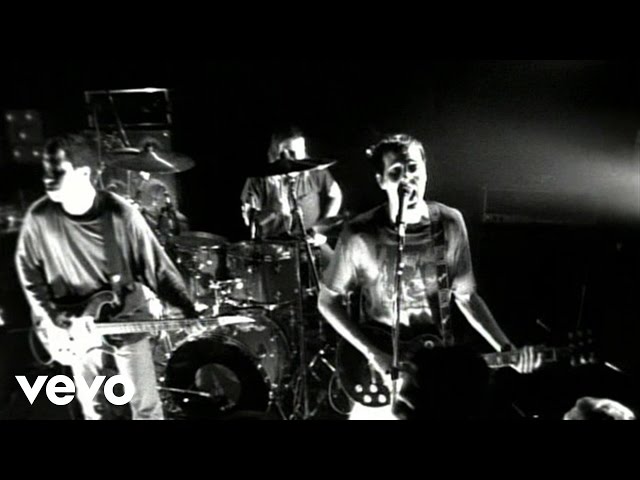
2022年の11月に再来日公演が決定している伝説のポストハードコアバンド、クイックサンド。
1980年代後半のニューヨークハードコアシーンにおいて象徴的なバンドの一つ、ゴリラ・ビスケッツのギタリストとして著名なウォルター・シュライフェルズさんを中心として1990年に結成され、1990年代に2枚のアルバムを、2012年にまさかの再結成を果たして5年後には復活作となるサード作、2021年には4枚目のアルバム『Distant Populations』を発表しています。
彼らのディスコグラフィを眺めていて興味深いのは、デビューEPこそハードコアの名門レーベルである「Revelation Records」よりリリースしていますが、1993年のデビューアルバム『Slip』の時点で早速メジャーデビューを果たしているのですよね。
期待されていたということの証左とも言えそうですが、残念ながら商業的な成功は収められませんでした。
とはいえ彼らの生み出したポストハードコアサウンドからの影響を口にする後続のバンドは多く、やはりクイックサンドもポストハードコア史における重要なバンドであることには変わりません。
そんな彼らの音楽性は、フガジやジョーボックスなどの影響を感じさせつつも、メタリックで硬質なギターのリフが随所に盛り込まれているというのが特徴的。
ヘルメットなどのバンドによるオルタナティブメタルと呼ばれるジャンルに近しい質感であり、そのような感性から生まれる独自のソリッドなグルーヴは彼らならではのものですね。
さらに言えば初期の頃にザ・スミスの名曲『How Soon Is Now?』をカバーするなど、UKロックへの憧れも感じさせる音作りにも注目してみてほしいですね。
Mistakes And Regrets…And You Will Know Us by the Trail of Dead

長いバンド名が印象的なアンド・ユー・ウィル・ノウ・アス・バイ・ザ・トレイル・オブ・デッドは、1994年にテキサス州オースティンにて結成されたポストハードコア~オルタナティブロックバンドです。
2022年には最新アルバム『XI: Bleed Here Now』をリリース、現在もバリバリの現役として長きに渡って活動を続ける彼らは、マルチプレイヤーであるオリジナルメンバーの2人が核となっており、それ以外のメンバーは流動的というのも特徴的ですね。
そんな彼らの名前を一躍世間に知らしめたのは、1999年にリリースされたセカンド作『Madonna』です。
アメリカの著名なインディーズレーベルのマージレコードからリリースされ、ヒンズー教の女神の肖像画をジャケットに用いたアートワークのインパクトもさることながら、ソニック・ユースばりのノイズや時に叙情的なギター、手数の多いダイナミックなドラムス、美しいメロディとポストロックからの影響も感じさせるドラマチックな楽曲展開で魅せるサウンドは高く評価され、2019年にはリリース20周年を記念してここ日本でも単独の来日公演が実現したほどなのですね。
2002年には傑作と名高いメジャー第一弾『Source Tags & Codes』を発表、オルタナティブロックやポストハードコアといった枠内をこえる芸術的な音世界で世間をあっと言わせました。
その後も彼らの創造性は衰えることもなく、自らの美学に基づいた作品をリリースし続けています。
早々に解散してしまうバンドも多い中、彼らのように高い水準を保ちながら活動を続けている存在は、実に貴重だと言えるでしょう。
For Want OfRites of Spring

ポストハードコア黎明期の1980年代前半から中盤にかけて活動、アルバムとEP作品を1枚ずつ発表して解散したバンドながら、後続のエモやポストハードコア系のバンドの先駆的な存在としてリスペクトされているのが、ライツ・オブ・スプリングです。
ワシントンD.C.のハードコアパンクシーンにおいても欠かせない存在であり、メンバーのギィ・ピチョットさんとブレンダン・キャンティさんは後にフガジとして活躍することでも知られています。
年代的にもまだまだゴリゴリのハードコアパンクが中心のシーンの中で、ほとばしるエモーションに満ちたメロディと、単純なパワーコードとは一線を画す繊細なギターワーク、性急なリズムを駆使した楽曲を展開していたというのは本当にすごいですよね。
間違いなく1990年代以降のエモコアやポストハードコアの原型であり、歴史を探っていく上でも確実におさえるべきバンドだと言えましょう。
ディスコードレコードよりディスコグラフィ盤『End on End』がリリースされていますから、オリジナル盤がほしいといったこだわりがなく、とりあえず聴いてみたいという方はこちらを入手することをおすすめします!