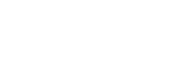【2026】海外の人気タルコアバンドまとめ【初心者向け】
メロディックデスメタルやハードコアから派生し、2000年代以降のラウドミュージックシーンにおいて中心的なジャンルのひとつとなったメタルコア。
ヘヴィメタルらしいアグレッシブなリフやメロディアスなギターソロ、ハードコア由来のブレイクダウンなどのブルータリティが融合し、デスボイスとクリーンパートを自在に行き来するスタイルなども見せ、商業的な成功を収めるバンドも多く輩出しました。
2010年代以降はより多様化したメタルコアは、2020年代の今も素晴らしい名盤の数々が誕生しています。
こちらの記事では、そんなメタルコアシーンを代表する海外のバンドを幅広い視点で紹介します!
【2026】海外の人気タルコアバンドまとめ【初心者向け】(1〜10)
My Own GraveAs I Lay Dying

2001年結成、人気・実力共にアメリカのメタルコア・バンドを代表する存在です。
最初期から流麗なツイン・リードと強烈なグロウル、哀愁のクリーン・パートが同居するメタルコア・サウンドを展開しており、日本でも高い人気を誇っていました。
商業的にも成功し、順風満帆のキャリアを積み上げていましたが、2013年にボーカリストのティム・ランベシスが不祥事により逮捕されてしまいます。
残されたメンバーは新たなボーカリストを迎えて、バンド名も変えて活動を続けますが、その後活動を休止。
2018年6月に活動休止前のバンド・メンバーで見事に復活を遂げ、2019年には待望の復活アルバム『シェイプド・バイ・ファイア』をリリース、健在ぶりを証明しました。
The Signal FireKillswitch Engage

2000年代以降のメタルコア・ブームを牽引し、現在も高い人気を誇る5人組です。
1999年に元OVERCAST、AFTERSHOCKといったバンドのメンバーで結成され、初期から攻撃的なハードコアとヘヴィメタルの様式美に、デスメタル的なブルータリティを高い演奏能力で融合させ、ソウルフルな泣きのメロディをフィーチャーしたスタイルで一気にシーンのトップへと上り詰めました。
当時は、出身地のマサチューセッツ州にちなんで、MAメタルなどと呼ばれていたこともありましたね。
バンドのキャリアの中で、デビューから2002年まではジェシー・リーチが、2002年から2012年まではハワード・ジョーンズがボーカルを担当しており、ハワード脱退後はジェシーが再びボーカリストに戻っています。
2人とも、甲乙つけがたい才能の持ち主ですよ。
ThroneBring Me The Horizon

ジャンルの壁を壊し続ける、現代ロックシーンの革命児!
イギリス出身のブリング・ミー・ザ・ホライズンは、デスコアからキャリアをスタートさせました。
初期は批評家から厳しい評価を受けることもありましたが、アルバムを出すたびにまるで別バンドのように姿を変え、エレクトロニカやポップまで飲み込む唯一無二のサウンドを築き上げたのです。
特に3rdアルバム『There Is a Hell…』以降の変貌は劇的で、彼らのディスコグラフィーを遡る旅は、ロックの進化史を追体験するかのようですね。
獰猛なサウンドから美しいメロディーまで、彼らの音楽的冒険にきっとあなたも夢中になるはずですよ!
The Final EpisodeAsking Alexandria

イギリス出身のメタルコア~ポスト・ハードコア系のバンドの中でも、本国のみならずアメリカでも商業的な成功を収めるなど高い人気を誇る5人組です。
初期の2枚は、いかにも2000年代後半から2010年代前半といった時代を感じさせる、エレクトロニック・サウンドを導入した若さあふれるメタルコア~ポスト・ハードコアを鳴らして人気を集めていましたが、2013年にリリースされたサード・アルバム『フロム・デス・トゥ・デスティニー』辺りから、往年のハードロック的なスタイルに接近し、硬派な音へとシフトしていきます。
一時期はボーカリストが脱退して後任のメンバーが加入するも、アルバム1枚で元のボーカリストが復帰を果たすというちょっとしたトラブルを経て、2020年の時点でも安定した活動を続けています。
Dark DaysParkway Drive

熱心にメタルコアやポスト・ハードコアといったジャンルを追いかけている人にとって、オーストラリアは多くの名バンドを輩出している土地として認識されています。
2003年に結成された5人組、パークウェイ・ドライヴもその1つです。
メタルコア・シーンにおいてはカリスマ的な人気を誇るバンドで、激しくもメロディックなメタルコア・サウンドを生み出し続けています。
2018年にリリースされた6枚目のアルバム『Reverence』では、よりメタル的なサウンドへと舵を切り、彼らにしか成しえないヘビーロックを提示してみせました。
音楽以外にも、熱心な環境保護の活動でも知られており、歌詞にも環境保護をテーマにしたものが多く見受けられますね。
2020年代以降は世界のメタル系のフェスティバルでトリの常連となるほどの巨大なバンドへと成長、2025年には日本でもラウドパークのヘッドライナーに抜擢されました!
MeddlerAugust Burns Red

現代メタルコア・バンドの中でも群を抜いた人気と実力を誇る、ペンシルベニア州の5人組。
クリスチャン・バンドとしても知られており、敬虔な信仰心が歌詞にも表れています。
2011年にはインストゥルメンタルによるクリスマス・ソングのカバー集もリリースしていますよ。
メロディック・メタルコアと呼ばれることもある彼らのスタイルは、突出したテクニックに裏打ちされた緻密なバンド・アンサンブルを軸に強烈なブレイクダウンも盛り込まれ、複雑に展開していくプログレッシブな要素が多く含まれていることが特徴です。
攻撃的なグロウルがメインでクリーンのメロディは基本的に使用しておらず、ハードコア的な面も変わらずに感じ取れるところが最高にカッコいい。
PiscesJINJER

ウクライナ出身のプログレッシブ・メタルバンド、ジンジャー。
ボーカルのタティアナ・シュマイルクさんが披露する、妖艶なクリーンボイスから驚異的なグロウルまでを自在に操る圧巻の歌唱が、多くのリスナーに衝撃を与えているバンドです。
プログレやグルーヴメタルを軸に、ジャズやレゲエの要素まで大胆に融合させた予測不能なサウンドは、テクニカルでありながらも非常にキャッチーな仕上がりに。
代表曲「Pisces」のライブ映像で世界的な評価を獲得し、困難な状況下でも音楽で力強いメッセージを発信し続ける彼らの姿は、多くの人の心を揺さぶっています。
その凄まじい強度と芸術性に、きっとあなたも圧倒されてしまうかもしれませんね!