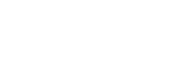【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ
洋楽や邦楽を問わず、エモやラウドといった形で紹介されるバンドをお好きな方であれば、一度は「ポストハードコア」なるジャンルを目にしたことがありますよね。
1970年代後半から始まったハードコアパンクを出自とするバンドたちの中で、既存のハードコアに収まりきらない独自の音を鳴らす面々が「ポストハードコア」と呼ばれるようになったのですが、さらにエモコアやスクリーモなどの派生ジャンルが生まれ、2000年代以降はより広い意味で使われており、定義付けが非常に難しいジャンルです。
今回の記事では、そんなポストハードコアの形成という意味で重要な役割を果たした、1980年代から1990年代にかけてデビューしたバンドを一挙紹介します!
- 【洋楽】ハードコアパンクの名曲・人気曲~入門編
- 【洋楽】90年代エモコアの名盤。まずは聴いてほしい1枚
- 【激しさと美しさの共存】日本のスクリーモ・ポストハードコアバンドまとめ
- 【2026】海外の人気タルコアバンドまとめ【初心者向け】
- 洋楽のおすすめスクリーモのバンド。海外の人気バンド
- ニューメタルの名曲。おすすめの人気曲
- 洋楽エモが聴きたければここから!海外のエモバンド一覧
- ハードコアパンクの名曲。おすすめの人気曲
- 根強い人気!洋楽のエモの名曲
- 【2026】メロコアの名曲。新旧の人気曲まとめ
- 邦楽のエモの名曲。おすすめの人気曲
- 【2026】日本のハードロックバンド。海外でも人気のバンドまとめ
- エモーショナルな楽曲から爽快な楽曲まで!平成の青春ソング
【洋楽】ポストハードコアとは~代表的なバンドまとめ(11〜20)
Altoids, Anyone?Tar
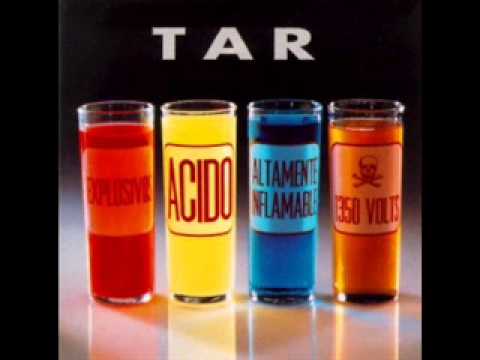
シカゴのポストハードコアやノイズロックと言えば、スティーヴ・アルビニさん率いるシェラックやジーザス・リザードといったレジェンドたちが筆頭に挙げられますが、マイナーな存在ながらぜひ知っておいていただきたいバンドが1988年から1995年まで活動した4人組のタールです。
もともとはハードコアパンクを演奏していたという彼らの音楽性は非常に興味深く、フリーキーなポストハードコアを軸としながらも独特のユーモアを兼ね備えたサウンドが他のバンドとはまた違った魅力を放っているのですね。
ノイジーなリフと時に変拍子も織り交ぜたリズムが織り成すグルーヴは混沌やダークさよりも奇妙な雰囲気を作り上げ、誤解を恐れずに言えばポップな要素さえ感じ取れるというのがおもしろい。
1991年のデビュー作『Roundhouse』の時点でその片鱗はうかがえるのですが、シカゴが誇る名門レーベル、タッチ・アンド・ゴー・レコーズよりリリースされたサード作『Toast』辺りから彼ら独自の個性がより明確となった印象ですね。
通算4枚目にしてラストアルバムとなった『Over and Out』は、スティーヴ・アルビニさんとボブ・ウェストンさんという名匠がエンジニアとして参加、彼らの追求してきた音楽性の完成形として推薦したい名盤です。
余談ですが、彼らはアルミニウム製のギターを使っていることでも知られており、EP作品『Clincher』のジャケットはそのギターの写真が使われていますよ。
Head ColdHeroin

2000年代においてサーズデイやザ・ユーズド、フィンチにセイオシンなどのスクリーモと呼ばれるバンドが商業的にも成功を収めて一大ムーブメントとなりましたが、スクリーモという言葉自体は1990年代から存在していました。
もちろん該当するバンドたち自身が言い出したジャンルではないのですが、音楽用語としてメディアの中ですでに使われていた、ということなのですね。
そんな「スクリーモ」の先駆的なバンドであり、ポストハードコア史においても重要なバンドがサンディエゴ出身のヒロインです。
サンディエゴのアンダーグラウンドシーンにおいて重要な役割を果たしたレーベル「Gravity Records」の発足初期を代表するバンドでもあり、1989年の結成から1993年の解散までの短い活動期間の中で残した数少ない音源は、後続のバンドたちに多大なる影響を及ぼしています。
タフなスクリームではなく、どこか悲哀を帯びた絶叫とナイーブなクリーンパートはまさに「プレスクリーモ」と呼びたいサウンドであり、内省的なエモーションが炸裂する様はまさに激情ハードコアの先駆的存在。
疾走パートもそれほど爽快なものではなく、どこか盛り上がりきらないようなやるせなさも漂う雰囲気がポストハードコア的で実に良いですね。
洗練されたスクリーモに慣れている方には物足りなさも感じるかもしれませんが、ポストハードコアやスクリーモの歴史に興味のある人であれば、バンドの解散後にリリースされた彼らのディスコグラフィ盤『Destination』は確実に入手しておくべきと断言しましょう。
Side Car FreddieHoover

実質的な活動期間は1992年から1994年にかけてのたったの2年、スプリット盤を含む数枚の7インチシングルと唯一のアルバム『The Lurid Traversal of Route 7』によって伝説となったバンドが、DCハードコアにその名を刻むフーバーです。
ワシントン出身ということで、フガジのイアン・マッケイさん率いるディスコードレコードにてアルバムをリリース、その独創的なハードコアサウンドはフガジからの影響を当然ながら感じさせるものですが、同時代のスリントなどのポストロックと呼ばれるジャンルの形成に一役買ったバンドたちともリンクしつつ、ミッドテンポ中心の楽曲の中で衝動的なエモーションと不穏かつダークな空気感が入り乱れた音像は彼らならではのものなのですね。
地を這うようなベースラインと手数の多いドラムスによる独特のグルーヴ、不協和音をまきちらすギターは混沌としていながらも、静と動のコントラストをうまく使った緩急自在のアンサンブルはオルタナティブロック的でもあります。
インストゥルメンタル曲やジャズ的なアプローチを見せる瞬間もあり、初めて彼らの世界に触れる方はその奥深い音楽性に驚かれることでしょう。
後にJune of 44といったアメリカンインディーズの重要なバンドとして活躍するメンバーも在籍している、という点にも注目してみてください。
Iron Clad LouHum

1990年代のオルタナティブロックと呼ばれるバンドたちの成功の裏で、知名度は劣るものの後続のアーティストたちに大きな影響を与えたというバンドは少なからず存在します。
本稿で紹介するハムはまさにそういったバンドの一つで、今回の記事のテーマであるポストハードコアとオルタナティブロックの橋渡し役のような音を鳴らしていたグループです。
1989年にイリノイ州にて結成、2000年に解散したということでまさに1990年代の激動の音楽シーンを駆け抜けたバンドなのですね。
インディーズ時代にリリースされた2枚のアルバムは、メジャー以降で見せる壮大なサウンドスケープはまだ感じ取れないものの、同時代のオルタナティブロックに影響を受けつつ、シューゲイザーやオルタナティブメタルなどの要素も取り入れて、音楽的にも自由度の高いポストハードコア的なアプローチを模索していることが分かるという意味で興味深い内容です。
そんな彼らの本領が発揮されるのが、1996年にリリースされたメジャー第一弾『You’d Prefer an Astronaut』でしょう。
スマッシング・パンプキンズ的なドラマチックなオルタナティブロックに加えて、スペースロックと呼ばれるスケールの大きい音響的な冒険を導入して独自の音楽性を手にしました。
収録曲の『Stars』がヒット、バンドとしては最も売れた作品となっています。
1998年の次作『Downward Is Heavenward』では完全に彼らならではの音世界を確立、包み込むような轟音ギターと静と動を駆使した叙情的かつ壮大な楽曲展開が見事な傑作を生みだしたのです。
ハードコアの要素は控えめでオルタナティブロック寄りではあるのですが、ポストハードコアのまた違った可能性を示したバンドとして、ぜひ知ってもらいたいですね!
MirrorMoss Icon
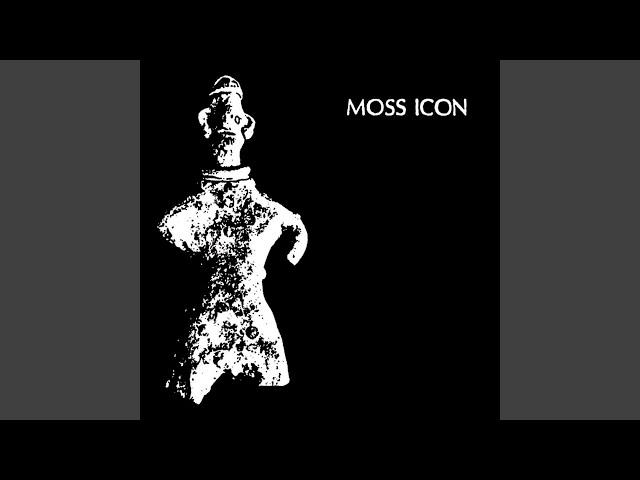
かなりマニアックな存在ですが、ポストハードコアの形成において重要な役割を果たしたと言われるバンドがアメリカはメリーランド州にて結成されたモス・アイコンです。
1986年から1991年までの数年間という短い活動期間、というのはこれまで紹介してきたポストハードコア系のバンドの中ではそれほど珍しいものではないですが、その活動歴と数えるほどの作品が独創的かつ個性的であったからこそ、後世においても高く評価されている最大の理由なのですね。
ボーン・アゲインストやグレート・アンラベリングといったさまざまなバンドで活躍したギタリスト、トニー・ジョイさんが在籍していたことでも知られており、トニーさんの一筋縄ではいかない変則的なギタープレイがモス・アイコンの一つの個性として最大限機能しています。
2012年にポストロックや先鋭的なエレクトロニカなどの作品を扱っているレーベル、テンポラリー・レジデンス・リミテッドよりモス・アイコンの音源をコンプリートしたディスコグラフィ盤『Complete Discography』がリリースされましたから、まずはこの作品を聴いてみるといいでしょう。
ハードコアらしい攻撃的なアプローチはもちろん、イギリスのポストパンク的な要素を感じさせるものから、ポストハードコアへとつながるねじれたギターリフ、緩急を使い分けたリズムチェンジ、スポークンワードのようなボーカルが織り成すサウンドは今聴いても新鮮です!
PickpocketAt The Drive-In

テキサスはエルパソにて1994年に結成されたアット・ザ・ドライヴインは、日本においても知名度の高い90年代ポストハードコア系の代表的なバンドです。
2000年代において先鋭的な音楽性を提示してシーンを席巻、2022年に久々に再結成を果たして新作をリリースしたマーズ・ヴォルタのメンバーセドリック・ビクスラーさんやオマー・ロドリゲスさんが在籍していることでも知られており、強烈極まりない破天荒なパフォーマンスはもはや伝説として語り継がれていますね。
2000年にリリースされたメジャーデビュー作『Relationship Of Command』は、当時コーンやリンプ・ビズキットにスリップ・ノットといった大物を手掛けたロス・ロビンソンさんがプロデュースしたこともあって大きな評判を呼びましたが、そのすぐ後に解散してしまいました。
2011年には再結成を果たして世界ツアーも実施、新作もリリースしていますがその後再度の活動休止を宣言しています。
そんな彼らが1990年代に残した作品、特に『In/Casino/Out』は間違いなく90年代におけるポストハードコアの傑作であり、荒削りだった初期のサウンドから演奏能力やプロダクションも格段に向上しつつ、変則的なギターのリフが絡み合い、セドリックさんのハイテンションなボーカルが自由奔放にわめきちらし、時にメロディアスに歌い上げるアット・ザ・ドライヴイン印のサウンドが明確に提示された重要な1枚なのですね。
『Relationship Of Command』しか聴いていないという方も、ぜひ90年代の彼らの作品を聴いてみてください!
おわりに
冒頭でも述べましたように、そもそもポストハードコアはジャンルの定義が曖昧で一口に語れるものではないのですが、さまざまな音楽ジャンルを内包しつつも根底にハードコアの魂が感じ取れる音楽こそが「ポストハードコア」と呼べるのかもしれません。
その起源がどこから来ているのか、ポストハードコアの歴史について今回の記事で少しでも興味を持っていただけたのであれば嬉しいです!