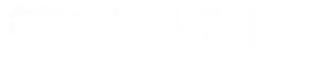むかし尺八は武術の道具だった!?日本の伝統楽器、尺八ってどんな楽器?
皆さん日本の楽器といわれたらどんな楽器を思い浮かべますか?
今回は、古くから伝わる日本の楽器「尺八」についてご紹介したいと思います。
尺八(しゃくはち)という名前の由来

http://www.irasutoya.com/
尺八は、一応、木管楽器に分類される楽器です。
助六とか、欽一とか、金八とか、そういう感じに聞こえなくもないですが、尺八という名称はその寸法に由来します。
数十年前まで一般的に用いられていた、尺貫法という度量衡の計り方でいう一尺八寸、今のメートル法でいうと約55センチが標準的な尺八の長さです。
寸(すん)は、尺貫法における長さの単位であり、日本では約 30.303 mmである。
尺の10分の1と定義される。
寸の10分の1が分(ぶ)である。
平安時代には「す」と書かれることもある。
古代の文献では訓で「き」と呼ぶこともある。
フルートをご存じの方でしたら、足部管(そくぶかん)を付けていない状態で、ほぼ尺八と同じ長さです。
尺八の素材

https://pixabay.com/
一般に尺八といえば、竹。
竹林に生えている竹を伐り出して、それを加工して作ります。
竹の種類にもいろいろありますが、尺八では、真竹(まだけ)という種類の竹を使います。
ざっくりいってしまえば、竹をくり抜いて手穴を開ければ音は出ます。
楽器として完成するには、いろいろ細かい調整が必要ですが、天然素材をそのまま使っているところが、他の楽器とは違った魅力ともいえます。
尺八は、演奏者自ら楽器を製作する方がけっこういらっしゃいます(私は、一度知り合いの方に付いて、尺八づくりを体験したことがありますが、もっぱら演奏だけです)。
素材が天然の竹であるだけに、それぞれの個性が出ます。
尺八の長さ
一尺八寸が標準的な長さといいましたが、実際には一寸刻みで、さまざまな長さのものがあります。
例えば、一尺六寸とか。
こういうのは「尺六」といいたいところですが、普通はあらゆる長さのものを総称して「尺八」と呼んでいます。
短いものは一尺一寸から、長いものは三尺以上のものまであります。
道具としての尺八
今でこそ、純粋に楽器として使われるようにもなりましたが、今の尺八のもとは江戸時代に虚無僧(こむそう)というお坊さんが、修行のために吹いていたものです。
虚無僧の宗派は、普化宗(ふけしゅう)という禅宗で、時には「武術の道具としても尺八を使った」ともいわれます。
そこで使われた小太刀の長さも一尺八寸だったらしいです。
要するに尺八は、禅宗や武術という音楽とは程遠い世界の道具だったということです。
尺八の歴史については謎の部分が多く、私もあまり深く理解してはおりませんが、そういった部分もミステリアスな魅力といえるかもしれません。
楽器としての尺八
禅の修行とはいえ、音楽的な笛のような要素もありますから(というか、笛そのもの?
)、民衆にも普及していたようです。
明治時代に普化宗が廃止されてからは、いっそう普及するようになり、お箏(一般的な読み:おこと)や三味線と合奏することが一般的になりました。
箏(そう)は、日本の伝統楽器。
十三本の糸を有するが、十七絃箏など種々の多絃箏がある。
箏は一面、二面(いちめん、にめん)と数える。
弦楽器のツィター属に分類される。
三味線(しゃみせん)は、日本の有棹弦楽器。
もっぱらはじいて演奏される撥弦楽器である。
四角状の扁平な木製の胴の両面に皮を張り、胴を貫通して伸びる棹に張られた弦を、通常、銀杏形の撥(ばち)で弾き演奏する。
そこに洋楽の要素も加わって、楽器としての役割が定着してきたということです。
今でも、お箏と三味線(三絃ともいいます)との合奏や、民謡の伴奏などはよく行われますが、邦楽器の枠を越えて、洋楽器などさまざまな楽器や音楽とも共演する機会が増えています。
すごく簡単に尺八という楽器について紹介しました。
もちろん歴史を知らなくても、尺八は吹けます。
知れば面白いかもしれませんが、はじめは知らなくても大丈夫です。
空きビンの口に息を吹き込んで「ボー」という音を出せれば、尺八を吹く素質があります。
まずはそんな気軽な感じで、尺八に興味を持っていただけたらうれしいです。