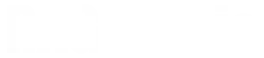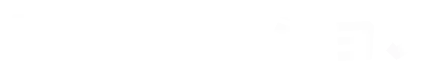昭和の暮らしが蘇る回想法!高齢者にオススメの懐かしい生活クイズ集
懐かしい思い出には不思議な力があります。
昭和の暮らしを振り返るクイズで心温まるひとときを過ごしませんか?
駅にあった伝言板から給食のメニュー、ブラウン管テレビまで、当時の日常が詰まった回想法クイズをご紹介します。
高齢者の方と一緒に思い出を共有することで、会話も自然と弾み、笑顔があふれる時間に。
脳のトレーニングにもつながる懐かしい昭和の暮らしクイズで、楽しみながら心と頭を活性化させましょう。
昭和の暮らし・懐かしい生活クイズ(6〜10)
一万円札が登場したのは昭和何年?
最初に一万円札が発行されたのは昭和33年、肖像は聖徳太子、裏面には鳳凰が描かれていました。
高齢者の方ではなくてもうっすらと記憶にある方は多いのではないでしょうか。
その後、高度成長期にともない1万円札の流通は大幅に流通量が増えていきました。
昔の小学校、昭和の時代には絶対にあった、今はもうないものは何でしょうか?
昭和の小学校では常識として「焼却炉」がありました。
清掃で出たゴミや、いらなくなった書類などを焼却炉で燃やして処分していたそうです。
ですが、ダイオキシンなどの有害物質を発生させるということが問題となり、平成12年には全国的に使用禁止となりました。
昭和30年代に「三種の神器」と呼ばれた家電製品は白黒テレビ、冷蔵庫、あと一つは何?
昭和30年代の初めの頃、白黒テレビと冷蔵庫と洗濯機が「三種の神器」として一般家庭に普及し始めました。
当時はとても高価な電化製品でテレビは街頭で見るものでしたがこの頃から各家庭に設置されるように。
昭和30年代後半あたりからはカラーテレビが普及し始めました。
昭和40年代に「新たな三種の神器」となった3Cとはカラーテレビ、クーラー、もうひとつは何でしょうか?
答えは自動車、英語ではCarのCでした。
それまでのテレビは白黒が一般的でしたが昭和39年の東京オリンピックの開催に合わせてカラーテレビが一気に普及、次いで自家用車が、最後にクーラーが各家庭に普及しました。
ちなみに昭和30年ごろの三種の神機は、電気洗濯機、電気冷蔵庫、白黒テレビだったそうです。
昭和42年に日本で始めて「動く歩道」が設置されたのはどこでしょうか?
今も梅田にある動く歩道「ムービングウォーク」は昭和42年、1967年に設置されました。
設置された理由として、駅設備移転にともなう他鉄道との乗り換え不便解消だそうです。
その3年後に大阪万博が開催されて有名な存在に。
今現在でも日本で一番大きな動く歩道として知られています。