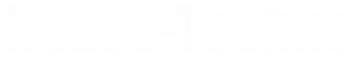80年代テクノ歌謡の魅力~テクノポップの名曲・人気曲
80年代の邦楽シーンを掘り下げていく中で、ディスクガイド本などで「テクノ歌謡」という言葉を目にされた方は多いでしょう。
70年代後半から80年代前半にかけて、YMOを中心とした先鋭的なアーティストたちがテクノの要素を取り入れたサウンドを展開、それらの要素を歌謡曲へと落とし込んで生まれたのが「テクノ歌謡」です。
大ヒットした曲もあれば、ほとんど知られることもなく後に再評価された曲などもあり、知れば知るほど楽しめるジャンルなのですね。
今回の記事では、そんなテクノ歌謡の名曲たちを厳選してお届けします。
「この曲ってテクノ歌謡だったの?」といった発見もあるかもしれませんよ!
- 日本発!テクノポップの名曲・オススメの人気曲
- 邦楽テクノの名曲、人気曲
- 80年代の歌謡曲の名曲・ヒット曲
- 1980年代に活躍したバンドの名曲&ヒットソング特集
- 50代の方が聴いていた邦楽のダンスミュージック。懐かしの名曲
- 80年代懐かしの邦楽ポップスの名曲・ヒット曲
- 邦楽のおすすめテクノバンド。テクノポップサウンドの人気曲・代表曲
- ハウス・テクノの人気曲ランキング
- 1980年代にヒットした失恋ソング。邦楽の名曲、人気曲
- 【若者にリバイバル?】80年代にヒットした邦楽ダンスミュージック。昭和のダンス曲
- 【Happy!!】サイケデリックトランスの名曲。おすすめの人気曲
- デトロイト・テクノの名曲。まずは聴いてほしい有名曲・人気曲
- 人気の懐メロ・名曲ランキング【80年代邦楽ランキング】
80年代テクノ歌謡の魅力~テクノポップの名曲・人気曲(21〜30)
俺は絶対テクニシャンビートたけし

「ビートたけしさんって歌を出していたの?」と知らない方であれば、思わず驚かれるかもしれませんね。
しかもタイトルが『俺は絶対テクニシャン』という強烈すぎるタイトル……たけしさんらしい1981年のデビュー曲です。
詳しく説明すると、たけしさんがビートきよしさんと結成した漫才コンビのツービートとしてのデビューシングルであり、それぞれがソロ曲を歌って7インチ・シングルとしてリリースされたもの。
2018年に、あの石野卓球さんが『』のカバー曲を披露したことからもわかるように、テクノポップ~テクノ歌謡の名曲として評価の高い珍品なのですね。
作詞に来生えつこさん、作曲には遠藤賢司さんという豪華な作家陣が参加しており、とんでもない歌詞を歌というよりはラップ調の語り口で披露するたけしさんがおもしろすぎます。
サウンド自体は完全にテクノ歌謡であって、実際に歌詞にも「テクノ」というワードが飛び交うところにも注目ですよ。
ひょうきんパラダイスひょうきんディレクターズ
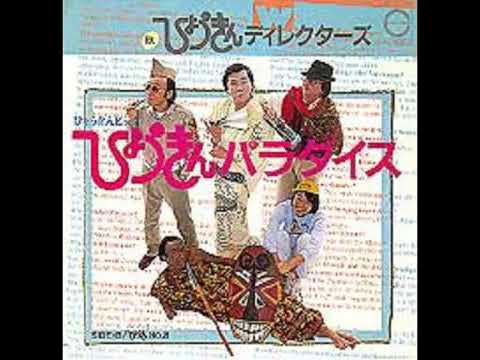
1981年より放送され、国民的な大人気となったお笑いバラエティ番組の『オレたちひょうきん族』。
ビートたけしさんや明石家さんまさん、島田紳助さんといったビッグネームがレギュラーを務め、後のお笑い番組に多大なる影響を及ぼしたということは、あえて説明するまでもないことですよね。
そんな『オレたちひょうきん族』を担当していたディレクター達が「ひょうきんディレクターズ」という直球の名義でユニットを結成、楽曲までリリースしてしまったのが、今回紹介している『ひょうきんパラダイス』です。
1982年に7インチ・シングルとしてリリースされ、フジテレビが掲げていた「楽しくなければテレビじゃない」の精神をそのまま反映したような、チープな電子音と素人丸出しな歌唱が良い意味での悪ノリといった雰囲気で、80年代という時代の空気感を濃厚に伝える珍品なのですね。
後にテクノ歌謡を集めたオムニバス・アルバムなどにも収録され、マニアの間では評価の高い楽曲です。
こういった曲を掘り下げて発見する楽しみも、テクノ歌謡というジャンルのおもしろみと言えましょう。
おわりに
こうして改めて多くの名曲たちを聴いてみると、80年代のテクノ歌謡は名だたるクリエイターたちが歌謡曲という枠内の中で、それぞれの個性を思う存分発揮した結果生まれた実に興味深いジャンルだということが理解できたのではないでしょうか。
当時は先鋭的過ぎて理解されなかった楽曲たちを、何十年も経った後でフラットな気持ちで楽しめるのは後追い世代の特権です!
ぜひ、奥深いテクノ歌謡の世界へと飛び込んでみてくださいね。