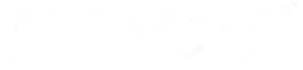1980年代にヒットした失恋ソング。邦楽の名曲、人気曲
80年代の名曲の中から「失恋ソング」をピックアップ!
失恋ソングといえば哀愁ただようメロディーに、まだ熱が冷めない情熱的な歌詞の対比がグッときますよね。
今回紹介する曲も悲しみの中に「まだ好き」という強い思いが詰め込まれている、涙なしには聴けない曲ばかりです。
「80年代の失恋ソングが知りたい」「青春時代のヒットソングをもう一度聴きたい」という方はぜひチェックしてみてくださいね。
80年代の曲ではありますが、名曲は時代に関係なく私たちに感動を与えてくれます。
若い方もこの機会に聴いてみてくださいね!
1980年代にヒットした失恋ソング。邦楽の名曲、人気曲(1〜10)
難破船中森明菜

最近はメディアに登場する回数も減った中森明菜さん。
80年~90年代にかけては「聖子派か明菜派か」とアイドルシーンを大きく二分する一大勢力を築きました。
アイドルとしての転換期、自身の失恋などを経てたどり着いたとされているのがこの『難破船』です。
「一つの恋が終わったとしてもそれを忘れて次の恋に進めばいい」と強がる歌詞には、その裏側の気持ち「それでもあなたを忘れられない……」が強く込められています。
失恋したあなたに静かに聴いてもらいたい1曲です。
終わった恋を「ゆくえを失った難破船」になぞりつづる加藤登紀子さん満身の歌詞にも要注目です!
木蓮の涙Stardust Revue

1981年にメジャーデビューし、数々の名曲を残してきたStardust Revue。
ボーカルである根本要さんのハスキーで聴き応えのある歌声がとっても魅力的ですよね!
この曲ではそんな彼の歌声が見事にマッチしており、失恋をテーマにした切ない歌詞がよりいっそう際立っていますよね。
さらにそのハスキーな歌声を支えるように美しく透き通るようなコーラスワークも見事。
また、歌詞を織りなす言葉や表現の一つひとつが美しいのもこの曲の魅力といえるでしょう。
悲しみがとまらない杏里

本人はそんな気はさらさらないと思いますが、名字がない名前だけの歌手・タレントの走りだったのかもしれません。
『地中海ドリーム』『思いきりアメリカン』など、彼女の曲はどこか日本の歌謡曲とは違った「洗練された異国の香り」がしましたよね。
彼氏を友達に取られてしまった「絶望的な失恋ソング」であるこの曲さえも、都会派らしいポップさでまとめられています。
『悲しみがとまらない』と歌いながらも失恋の息苦しさが感じられないのですから、これが杏里ソングの魅力の一つなのではないでしょうか!
失恋したばかりだけど元気を出したい、そんなあなたにオススメの1曲です。
駅竹内まりや

永遠のウーマンズポップ・竹内まりやさんの代表曲です。
失恋した後に聴くと絶対に泣くと思いますので、どうか気をつけて聴いてくださいね。
駅は失恋ソングで舞台になりやすい場所。
そこで昔の彼氏を偶然見かけてどうしていいのかわからなくなった……風の歌詞は純な乙女心そのもの。
恋愛の本能みたいなものも感じさせる歌詞です。
この曲はほかのアーティストにもたくさんカバーされているのですが、中森明菜さんが歌う『駅』も深い女の情を感じさせるすてきな曲に仕上がっています。
こちらもオススメです!
MPRINCESS PRINCESS

現在でも多くの世代から高い支持を受けている、PRINCESS PRINCESSの代表曲『M』。
現在でこそ、彼女たちを代表するヒットソングとして知られていますが、実は彼女たちのもう一つのヒットソングである『Diamonds』のB面としてリリースされました。
非常に切ないすてきなリリックなのですが、作曲する段階では元カレへの仕返しのつもりでリリックをつづったそうです。
意外に攻撃的な思いがこめられていた曲だったんですね(笑)。
つぐないテレサ・テン

今ほど外国人タレントがいなかった時代、日本、タイ、マレーシアなどアジア圏を所狭しと飛び回り、女性の本気の恋を歌い続けたのがテレサ・テンさんでした。
この歌も「あたなは優しかった、悪いのは私……」といさぎよくその恋から身を引く女性をつづっています。
失恋の曲とは裏腹にテレサ・テンさんの堂々とした歌いっぷりが未練に負けない強い女性を感じさせたものでした。
惜しまれつつこの世を去った彼女の歌は永遠に受け継がれると思います。
涙しながらも、一人でゆっくり聴きたい曲です。
ルビーの指環寺尾聰

1981年にリリースされた寺尾聰さんのヒットソング『ルビーの指環』。
1980年代を代表するヒットソングといっても過言ではないでしょうか?
売上やチャートの記録はすさまじく、週間オリコンでは10週間連続で1位を獲得し、人気番組『ザ・ベストテン』では12週連続で1位を獲得しています。
12月31日には、そのすさまじいヒットが認められ、日本レコード大賞を獲得しています。
80年代のムードにあふれたメロディーを象徴する作品です。