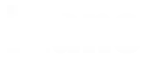【初級~中級向け】ピアノで弾きたい!バッハのおすすめ曲まとめ
「音楽の父」とも呼ばれるヨハン・ゼバスティアン・バッハが活躍したのは、ピアノが普及する前のバロック時代。
つまり、バッハ自身はピアノのための曲を作曲しておらず、現在ピアノで演奏されているバッハ作品のほとんどが、チェンバロ用の楽曲なのです!
複数のメロディラインが重なり合って構成されたバロック時代のポリフォニー音楽は、一見難しいと思われ敬遠されがちですが、実はバッハの作品になかにも比較的難易度が低く取り組みやすい作品が数多く存在します。
そこで本記事では、ピアノ初心者から中級者の方にオススメのバッハ作品をピックアップ!
バッハの音楽が好きな方や、バロック音楽に挑戦してみたい方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
- 【中級レベル】ピアノで弾けるかっこいい曲【発表会にもおすすめ】
- 【初級編】発表会で弾きたいおすすめのピアノ曲まとめ
- 【ピアノ名曲】難しそうで意外と簡単!?発表会にもオススメの作品を厳選
- ピアノで奏でるバロック音楽|発表会や演奏会におすすめの名曲を厳選
- 【中級者向け】挑戦!ピアノ発表会で聴き映えするおすすめの名曲
- 【小学生向け】ピアノ発表会で聴き映えする華やかな名曲たち
- 【初級~中級】難易度が低めなショパンの作品。おすすめのショパンの作品
- 【難易度低め】モーツァルトの簡単なピアノ曲。おすすめのモーツァルトの曲
- ブラームスのピアノ曲|難易度低め&挑戦しやすい作品を厳選!
- 【難易度低め】聴いた印象ほど難しくない!?ドビュッシーのピアノ曲
- 【ベートーヴェン】ピアノで簡単に弾ける珠玉の名曲をピックアップ
- ピアノをはじめた初心者におすすめ!大人も楽しめる楽譜10選
- 【難易度低め】易しく弾けるメンデルスゾーンのピアノ曲。おすすめのピアノ曲
【初級~中級向け】ピアノで弾きたい!バッハのおすすめ曲まとめ(1〜10)
5つの小前奏曲 第1番 BWV939 ハ長調J.S.Bach

『5つの小プレリュード』は、ヨハン・セバスティアン・バッハの信奉者であった ハン・ペーター・ケルナーによる筆写譜でのみ伝えられている作品。
実は、いまだにバッハの作品であるか否かの論争に決着がついていない状態なんです。
『第1番 BWV 939 ハ長調』には、「ゼクエンツ」と呼ばれる音程を変えて何度も現れる反復進行が使われています。
ただ繰り返すだけで平たんで退屈な音楽になってしまわないよう、進行や音程の高低によって表現を工夫できると、よりこの曲のおもしろさが伝わるでしょう。
フランス組曲 第3番 BWV 814 メヌエットJ.S.Bach

優雅で洗練された舞曲の魅力が詰まったこの楽曲は、1722年から1725年の間に作曲された組曲の一部として親しまれています。
三部形式で構成され、流れるような美しい旋律と内省的で繊細な表現が絶妙に対比されており、演奏者は多彩な音楽性を発揮できます。
バロック時代の装飾音やアーティキュレーションの理解が求められるものの、技巧的な難易度は比較的抑えられているため、音楽的な表現力や感性を重視して演奏に取り組みたい方におすすめです。
教育現場でも広く取り上げられており、演奏技術と音楽性の両面を養う重要なレパートリーとして活用されています。
インヴェンション8番 BWV779J.S.Bach

ファンファーレのような躍動感があふれる上行形の分散和音から始まり、明るく元気な雰囲気に満ちた3/4拍子のヘ長調の楽曲です。
上声部と下声部が1小節の時間差で追いかけ合うような掛け合いが生み出す独特のリズムが心地よく、聴く人の心を踊らせます。
本作は教育的な目的で書かれた作品ながら、その音楽的な魅力は聴衆の心をつかんで離しません。
左手の3、4、5指を使うパッセージは少々手強いものの、練習を重ねることで両手の技術向上が実感できる素晴らしい曲です。
明るく華やかな曲調と適度な技術的チャレンジが含まれているため、発表会で演奏する曲をお探しの方にぴったりでしょう。
【初級~中級向け】ピアノで弾きたい!バッハのおすすめ曲まとめ(11〜20)
フランス組曲 第2番 BWV 813 クーラントJ.S.Bach

フランス組曲のなかでも舞曲らしい魅力がつまったこの楽曲は、3拍子の優雅なリズムと流れるような旋律が印象的です。
1722年から1725年の間に作曲されたバロック音楽の傑作で、フランス風とイタリア風の舞曲スタイルを融合させた洗練された作品となっています。
歌詞はありませんが、楽曲そのものが語りかけるような表現力が豊かな旋律によって、宮廷での優雅な舞踏の情景が浮かび上がります。
ゆったりとしたテンポながらも複雑なリズムが織り込まれているため、演奏技術と音楽理論の習得を目指す方や、バロック音楽の魅力を味わいたい方におすすめです。
教育目的で作曲された本作は、弾きやすさと芸術性を兼ね備えた一曲です。
フランス組曲 第1番 BWV 812 メヌエットⅠJ.S.Bach

バロック時代の舞曲形式の中でも、この優雅な3拍子の楽曲は1722年から1725年頃に作曲され、「アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳」にも収録されています。
シンプルで親しみやすい旋律でありながら、対位法的な要素も含まれており、教会で響く上品な音色をイメージしながら演奏すると雰囲気が出てきます。
本作は技術的な難易度が比較的低いため、ピアノを始めて間もない方やバロック音楽に憧れを持つ方におすすめです。
音色や表現、強弱などが重視されるクラシックの場合は、ロングトーンの練習や良い音色の探求をしながら弾いてみましょう。
ミュゼット ニ長調J.S.Bach

バロック時代の家庭音楽の魅力を存分に味わえる「アンナ・マグダレーナ・バッハのための音楽帳」から生まれたこの楽曲は、バグパイプを模した左手の伴奏パターンが印象的です。
三部形式で構成され、ニ長調とイ長調を行き来する明るく親しみやすいメロディは、舞曲らしいリズミカルな動きが特徴的です。
1725年に編纂された音楽帳の一部として、家庭での音楽教育のために書かれた背景もあり、技巧的すぎず弾きやすい構成となっています。
バロック音楽に興味がある方や、ピアノで古典的な作品に挑戦したい方には特におすすめです。
アニメ「おさるのジョージ」でも使用されており、その親しみやすさが現代でも愛され続けている理由でしょう。
フランス組曲 第1番 BWV 812 サラバンドJ.S.Bach

バロック音楽に憧れはあるものの、複雑な対位法が苦手という方にはこの楽曲がおすすめです。
1722年頃に作曲されたこの作品は、アンナ・マグダレーナ・バッハの音楽帳に収められていることからも、家庭での演奏を意図した親しみやすい楽曲となっています。
3拍子のゆっくりとした舞曲で、シンプルな和声進行と美しい装飾音が特徴的です。
曲調もゆっくりですし、難しいフレーズも技巧的なところもないため、バロック音楽を弾き始めた方でも練習すればすぐに演奏できます。
音色や表現、強弱などが重視されるので、良い音色の探求をしながら弾きましょう。